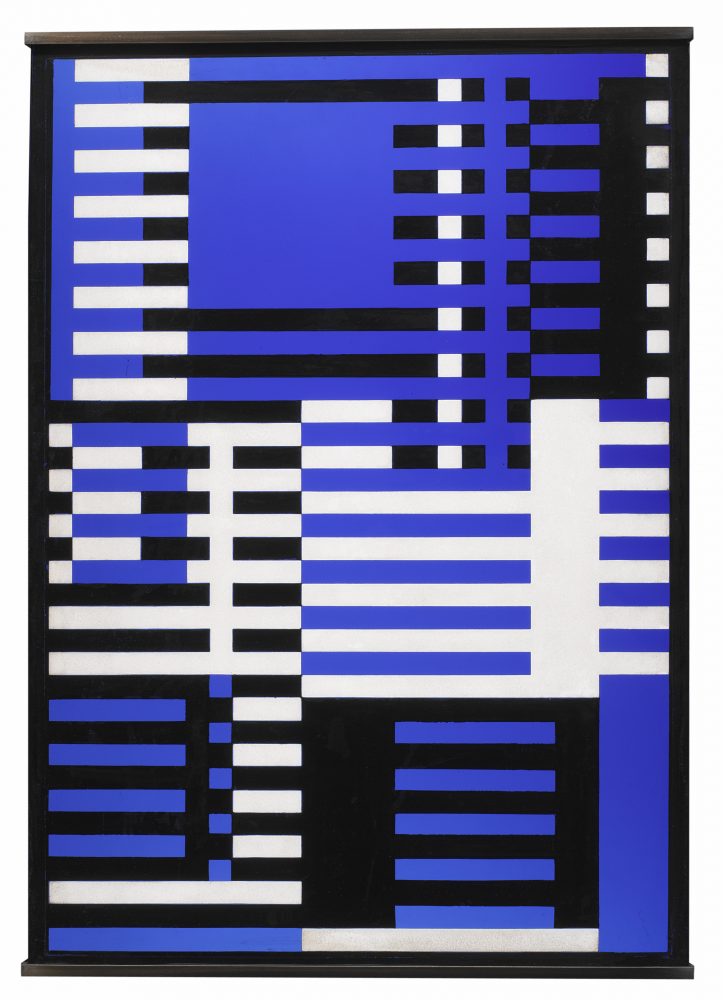スペインが生んだ奇才、サルバドール・ダリが描く窓
05 Dec 2016
2016年9月14日~12月12日、国立新美術館にてサルバドール・ダリの回顧展「ダリ展」が開催されている。約250点を展示する会場をめぐると、青年期、壮年期、晩年期のそれぞれで彼が窓を想起させる作品を残していたことがわかる。そこで本展の監修者である南雄介氏から、ダリの奇想と窓をめぐる関係について伺った。
伝統主義者としてのダリ
──本日はダリが生涯を通じて窓をどのように捉えてきたのかについてお聞きしていきたいと思います。国立新美術館で開催している「ダリ展」の展示作品には、窓を描いたものがいくつかありますね。
南雄介(以下:南) 今回のダリの回顧展では、彼が十代の頃に描いた絵画も展示しているのですが、そのなかでもたとえば《チェロ奏者リカール・ピチョットの肖像》(1920年)や《縫い物をする祖母アナの肖像》(1920年頃)などは、窓を描いた作品となっています。室内で楽器を演奏したり、縫い物する人物の姿を描写した作品ですが、窓の向こうに外の景色も描き込まれています。
-

サルバドール・ダリ 《縫い物をする祖母アナの肖像》 (1920年頃)
ガラ=サルバドール・ダリ財団蔵
Collection of the Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, JASPAR, Japan, 2016.
──どちらも海の風景ですね。これらの窓の向こうの風景は、どこかの現実の土地をモデルにしているのでしょうか?
-

サルバドール・ダリ 《チェロ奏者リカール・ピチョットの肖像》 (1920年)
ガラ=サルバドール・ダリ財団蔵
Collection of the Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, JASPAR, Japan, 2016.
南 ダリが幼少期から毎年夏を過ごしていたスペイン北東部のカダケスは地中海に面する地域なので、そこの風景が元になっていたと考えられます。自身の妹をモデルにして七人の女性の姿を描いた作品の背景にもやはり海が描かれているのですが、そのタイトルがずばり《カダケス》(1923年)だったりします。
-

サルバドール・ダリ 《カダケス》 (1923年)
サルバドール・ダリ美術館蔵
Collection of the Salvador Dalí Museum, St. Petersburg, Florida
Worldwide rights: © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, JASPAR, Japan, 2016.
In the USA: © Salvador Dalí Museum Inc. St. Petersburg, Florida, 2016.
──こうした風景描写は、ダリの故郷に対する愛着の表れだということでしょうか?
南 当時の彼にとっての日常的な風景だったのだと思います。後半生を過ごしたポルト・リガトのアトリエも、このカダケスの近郊にあるので、きっとこの地に愛着はあったと思います。
空間表現の観点でこれらの作品をみると、室内の風景の中に屋外の風景を挿入するために窓を用いていることがわかります。いわば、風景画と室内画の両者を一つの絵のなかに併存させ、空間を二重化しているわけですが、この手法はイタリア・ルネサンス絵画にも見られる伝統的な表現をベースとしたものなんです。
──ダリの空間表現の起源を辿っていくと、実は過去の芸術と地続きであったというのは意外です。その後のシュルレアリスム時代以降になると、窓の表現にはどのような変化が表れてくるのでしょうか?
南 ダリの作風は一見すると、十代の頃の作品から大きく様変わりしているように見えますが、空間表現の観点からすると、後年の作品の窓の用い方もやはり伝統的な手法を引き継いだものとなっていることがわかります。
たとえば後年の作品である《素早く動いている静物》(1956年頃)では、画面が複数のフレームで分割されています。
-

サルバドール・ダリ 《素早く動いている静物》 (1956年頃)
サルバドール・ダリ美術館蔵
Collection of the Salvador Dalí Museum, St. Petersburg, Florida
Worldwide rights: © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, JASPAR, Japan, 2016.
In the USA: © Salvador Dalí Museum Inc. St. Petersburg, Florida, 2016.
見方によっては、開口を設けることで異なる複数の空間を一枚の絵の中に同時に取り入れているのだとみなすこともできます。ルネサンス・バロック時代にしばしば制作された画中画とも同様の手法ですから、これもまたダリの伝統主義者としての側面だといえます。
──1930年代後半に制作された《狂えるトリスタン》(1938年)では三つの開口部が並んでいますが、中央のアーチ状の開口部から西洋建築の天井に見られる意匠が見受けられます。ダリは歴史的建造物にも関心があったのでしょうか?
南 この作品はもともとバレエの舞台美術のために制作されたものです。人間のかたちをした木の枝を列柱のように奥まで並べることで、奥行き感を表現している点が特徴です。
-

サルバドール・ダリ 《狂えるトリスタン》 (1938年)
サルバドール・ダリ美術館蔵
Collection of the Salvador Dalí Museum, St. Petersburg, Florida
Worldwide rights: © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, JASPAR, Japan, 2016.
In the USA: © Salvador Dalí Museum Inc. St. Petersburg, Florida, 2016.
同様のモチーフは《パッラーディオのタリア柱廊》(1938年頃)という作品にも認められるのですが、タイトルの通り16世紀イタリアの建築家アンドレア・パッラーディオが設計した劇場《テアトロ・オリンピコ》に想を得て制作されたものです。この劇場の舞台はそれほど奥行きがない空間なのですが、回廊を三方に展開することで遠近感を増幅させるという騙し絵的な工夫が施されています。《パッラーディオのタリア柱廊》や《狂えるトリスタン》も、これと同様の見かけの奥行き感が導入されています。
-

サルバドール・ダリ 《パッラーディオのタリア柱廊》 (1938年頃)
三重県立美術館蔵 © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, JASPAR, Japan, 2016.
──様々な表現を吸収しようとするダリの貪欲な姿勢が窺えます。《キュビスム風の自画像》 (1923年)と題する作品では、その名のとおり同時代のキュビスムの手法を採用していますね。
南 複数の表現手法を使いこなすだけの技量をダリは持ち得ていたということです。他にも《ラファエロ風の首をした自画像》(1921年頃)は、彼が敬愛するルネサンスの芸術家ラファエロの表現を下敷きにしたものですし、シュルレアリスム時代の作品である《謎めいた要素のある風景》(1934年)の光の表現は、17世紀オランダの画家ヨハネス・フェルメールから影響を受けたものであると指摘されています。
-

サルバドール・ダリ 《謎めいた要素のある風景》 (1934年)
ガラ=サルバドール・ダリ財団蔵
Collection of the Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, JASPAR, Japan, 2016.
そのように多種多様な表現を導入しながらも、芸術に対するスタンスは生涯ブレることがなかったのではないかと考えています。絵画における空間表現の歴史を振り返ると、そこには大きく2つのベクトルがあります。一つは「現実の空間をいかに再現するか」を重視する方向性であり、もう一つは「イメージを生産すること」を追求する方向性です。このうちダリは、とりわけ後者に非常に強い関心を持ち続けていた作家だと思います。
イメージを多重化するための窓
──1929年から1939年にかけてのシュルレアリスム時代にダリが編み出した方法に「パラノイア的=批判的方法」と呼ばれるものがありますが、この方法と窓の表現とのあいだにはどのような関係があるでしょうか?
南 パラノイア的=批判的方法とは簡単にいうと、無意識的な妄想を客観化して表現する方法のことです。この具体的実践として、ダリは「ダブル・イメージ」という技法を用いた作品を複数制作しています。
たとえば《奇妙なものたち》(1935年頃)では赤いソファの窪みが人の姿に見えるように表現されていたり、《姿の見えない眠る人、馬、獅子》(1930年)では横たわる女性の左腕が馬の頭で、馬の尻尾がライオンの頭にそれぞれ見えるようになっていたりする。このように一つの絵のなかに複数のイメージを重ねることで、単一のイメージに確定することができないようになっているのがダブル・イメージの特徴です。この技法で描かれたダリの作品は、人間の心の内に潜む無意識的、混乱的、妄想的なイメージを観る者に惹起させると言われています。
-

サルバドール・ダリ 《奇妙なものたち》 (1935年頃)
ガラ=サルバドール・ダリ財団蔵
Collection of the Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, JASPAR, Japan, 2016.
──ダブル・イメージの手法を用いた作品で、窓が登場するものはありますか?
南 《ウラニウムと原子による憂鬱な牧歌》(1945年)という作品があります。広島と長崎への原爆投下のニュースに衝撃を受けて描かれたものです。1950年代にダリの作品は「原子核神秘主義」と呼ばれるものへと転じていくのですが、本作はいわばシュルレアリスムから原子核神秘主義へ移行する過渡期の作品といえます。というのも、原子核神秘主義の絵画にはしばしば分裂した粒子が浮遊しているようなイメージが表れるのですが、本作にはまだそのような表現は見られず、むしろ戦前に用いていたダブル・イメージの手法で描かれているからです。
-

サルバドール・ダリ 《ウラニウムと原子による憂鬱な牧歌》(1945年)
国立ソフィア王妃芸術センター蔵
Collection of the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, JASPAR, Japan, 2016.
板張りの暗い室内を思わせる空間のなかに複数の未知のイメージが配置されていますが、ところどころに青空の風景も挿入されており、壁や天井に設けられた窓のように見えます。その青空の向こうに数羽の鳥が飛んでいる姿が描かれていますが、開口部の輪郭とあわせて見ると女性の顔のレリーフになっていることがわかります。
──窓と顔のダブル・イメージですね。その女性の顔の左下では、爆撃機が曇り空を背景に焼夷弾を投下している様子が描かれていますが、これも見方によっては人間の眼や鼻に見えます。
南 そのような解釈の余地が残されている作品だということですね。通常の絵画における窓は、空間の三次元的な奥行き感を生むために描かれることが多いわけですが、《ウラニウムと原子による憂鬱な牧歌》の窓は、あくまでも奥行きを欠いたフラットな存在であり、絵画の表面上でしか存在し得ないイメージを生産するための表現となっています。このときダブル・イメージの窓は、開口部であると同時に開口部ではないような、両義的存在だといえます。
──今のお話を聞いて、ルネ・マグリットの作品を連想しました。マグリットも、窓の向こうの風景なのか窓辺に立てかけたキャンバスなのかが定まらない《田園の鍵》(1933年)のような騙し絵的な作品を残していますね。
南 確かにそうですね。ただしマグリットにとって窓はとても重要なモティーフで、絵画を観る者の認識に揺さぶりをかけるような哲学的な深い意味が込められています。一方でダリによるダブル・イメージの窓にはそれほど深刻な意味が含まれているわけではなく、あくまでも表面的・遊戯的な在り方をしています。そうであるからこそ、彼の作品はとてもアクロバティックなものになっているわけです。
──ちなみにダリ以外の作品でもよいのですが、窓の描かれた絵画のなかで好きな作品はありますか?
南 アンリ・マティスの《コリウールのフランス窓》(1914年)という作品が一番好きですね。いちおうフランス窓を描いたものではあるのですが、窓の向こうが真っ黒に塗りつぶされてしまっているんです。なぜこの絵が好きなのかというと、この作品には20世紀絵画の在り方を予見するようなところがあるからです。
レオン・バッティスタ・アルベルティが『絵画論』(1435年)で遠近法の原理について論じた際に、絵画を「開かれた窓」に見立てているように、ルネサンスの時代において絵画を描くということは、窓の向こうの世界を映し出すことを意味していました。これに対して20世紀絵画は、そうした遠近法的な認識自体を否定するところから始まります。マティスによる《コリウールのフランス窓》も、遠近法的な奥行きは存在せず、絵の表面しか描かれていません。20世紀絵画に対するマティスのもの凄い決意があらわれているような気がします。
それからマルセル・デュシャンを研究していたこともあり、彼の《フレッシュ・ウイドウ》(1920年)も好きですね。黒い皮で窓を物理的に遮蔽した作品ですが、これも先述のマティスの作品と通じるところがあり、興味深い作品です。
──マティスやデュシャンとダリとの間に影響関係はあったのでしょうか?
南 デュシャンはダリより年上ですが、1950年代から1960年代にかけて交流が育まれたそうです。また1950年代後半に瀧口修造がポルト・リガトにあるダリの家を訪れた際、ダリを介してデュシャンと対面したという記録も残っています。
アトリエの窓辺から見える風景
南 このポルト・リガトのアトリエは、今では美術館として公開されており、私も訪ねたことがあります。はじめは漁師小屋程度の規模だったらしいのですが、何年もかけて徐々に新しい建物を継ぎ足していくうちに、今のような建物になったそうです。アトリエには窓がたくさんあって、そこから常にポルト・リガト湾の景色を望めるようになっていました。外の風景を切り取るように窓がつくられていたのが印象に残っています。屋外に少しだけ出られるテラスにも細長い窓が付いていて、そこから外の湾の景色が見えるようになっていました。
後期の作品には、アトリエの窓から見たポルト・リガト湾の眺望に似た風景がしばしば登場します。もしかしたらダリは、このアトリエの窓辺から見える風景を写しとっていたのかもしれませんね。祭壇画の形式を採用した《ポルト・リガトの聖母》(1950年)もまさしくそのような作品の一つで、背景に広がる水面はポルト・リガト湾の風景だとされています。
-

サルバドール・ダリ 《ポルト・リガトの聖母》 (1950年)
福岡市美術館蔵 © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, JASPAR, Japan, 2016. *東京会場のみ展示
聖母と幼子イエスを囲うように四つに分解された聖堂が浮遊していますが、これは先述の「原子核神秘主義」の絵画の特徴です。分裂した粒子が一定の距離を保ちながら浮かぶという原子物理学の知見に基づいているわけです。ちなみに中央の聖母はダリの妻のガラがモデルとなっています。
──聖母子の身体の中心に大小の四角い空洞が設けられていて、窓のようですね。この作品にはポルト・リガトとガラに対する思いが強く表れているように見えます。
南 ダリの作品にはしばしば机の引き出しのモチーフが登場するのですが、無意識を表現したものであると指摘されています。つまり「心の引き出し」というような意味合いですね。
──それと同じように《ポルト・リガトの聖母》の窓も、「心の窓」のような意味合いが込められているということでしょうか?
南 実際のところはわかりませんが、聖母子を描いた絵画ですから、聖母の中にイエスがいたということを示しているのかもしれません。
──なるほど。中央の空洞にはパンが配置されていますが、これもパンがキリストの肉であるとする教えを示したものだと考えられますね。
南 パンにかぎらず食べ物のモチーフは、ダリの作品にしばしば出てくる要素なんです。たとえば卵、ウニの殻、牡蠣、ムール貝、バラ肉の脂身などが描かれていたり、イカの甲が伸びてガラの姿になっている作品もあったりします。ここでのパンは、ひょっとしたらそのような日常的なものの中に神秘が宿ってるということなのかもしれません。ですが個人的には、ダリの日常的な食生活を想起させる点が興味深いと感じています。
──食べ物と同様に、窓もまた日常的なモチーフといえますね。そうした日常的なものが描かれているからこそ、違和感が挿入されている雰囲気がいっそう引き立ち、虚構と現実が織り交ざっていく印象が増幅しているように見えます。
南 それと同時に窓自身の在り方も、窓でありつつ窓ではないような存在になっています。この両義性こそが、ダリの描く窓の面白いところですね。
展覧会「ダリ展」
会場/国立新美術館、会期/2016年9月14日(水)~12月12日(月)
http://www.nact.jp/exhibition_special/2016/salvador-dali/
南雄介/Yusuke Minami
1959年生まれ。1986年東京芸術大学大学院修了。東京都美術館、東京都現代美術館を経て、2004年4月より国立新美術館設立準備室に勤務、2013年4月より現職。国立新美術館での展覧会に、「開館記念展 20世紀美術探検」、「光 松本陽子/野口里佳」展、「シュルレアリスム展」、「与えられた形象 辰野登恵子/柴田敏雄」展、「アメリカン・ポップ・アート展」、「中村一美展」、「マグリット展」など。