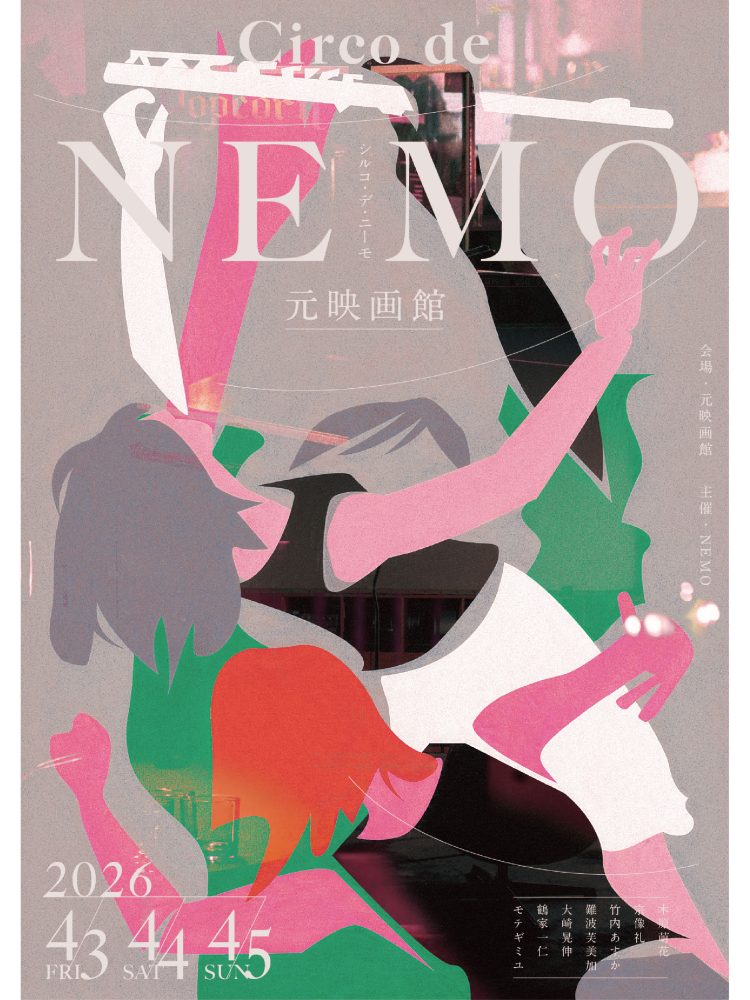心の窓 ─《聴竹居》
11 Dec 2024
1928年に建てられた藤井厚二(1888-1938)の自邸《聴竹居》。保存修理、整備が2023年に完了し、竣工当時の姿を取り戻した。クールチューブを取り入れるなど、当時の最先端の技術を用いたこの住宅は日本の気候風土と日本人の感性に適合した木造モダニズム建築の先駆けと近年再評価され、2017年に重要文化財にも指定された。今回、建築家の内藤廣が二十数年振りに現地を訪れ、空間を読み解き、藤井の心に思いを馳せる。
※2024年6月訪問。写真は一部を除き2023年12月に撮影
久々の再訪
二十数年ぶりに訪れた《聴竹居》(1928)は、かつての印象とはまるで違うものだった。庭も外構も整えられ、建物の構成や元々の意図がよりわかりやすくなった。サンルームの手前にあった大きな紅葉が台風でやられてしまい、二代目になった。大きさはまだ小振りだが、この建物が建ったときはこのくらいの大きさだったろう、との説明だった。そのせいか、庭も明るくなり、心持ちサンルームも明るくなったような印象を受けた。この木がやがて大樹になると、居室からの風景もまたかつての印象に近いものになっていくに違いない。
まず、《聴竹居》に対する松隈章さんの長年の努力と熱意に敬意を表したい。彼の情熱なくしては、この建物は荒れ果てて取り壊されたに違いない。藤井厚二の評価も今日のようにはならなかっただろう。藤井が勤めていたこともある竹中工務店が縁を感じて買い取ったこと、その後、文化財指定を受けたこと、松隈さんが引き寄せたいくつかの幸運が重なって、この建物は永く次の時代へ引き継がれることになった。
ウグイスの声
訪れた時は、ウグイスの鳴き声がしきりに聞こえた。あまりにハッキリといつまでも囀っているので、「スピーカーで流しているのか」と聞いたら、「とんでもない」と怒られた。しかし、それほどこの建物は茂みと一体になっているのだと言うこともできる。部屋の中にいても、薄いガラスと繊細な壁を抜けて、見事なウグイスの鳴き声が聞こえてくる。そういう家なのである。自然の移りかわりとともに風流を楽しむ暮らしを求めたのではないかと思う。断熱サッシとペアガラスですっかり重装備になった今日の住宅ではこんなことはあり得ない。
-

藤井が学んだ建築家・伊東忠太による怪獣の石像が玄関先に置かれている -

南側の庭からサンルーム部分を見る
以前見せてもらった時、どうしても気になるところがあった。ほぼ荒れ放題で廃墟になりかけていた別棟の下閑室、その床の切り方だ。尋常ではない。荒れた屋内に横一線、鋭く刃のように掛け渡された床の上の垂れ壁を押さえる一本の長い竹の印象が強く残っている。それが藤井の精神の躍動を表現しているように感じられたからだ。今回の訪問は窓の取材であるが、私の気分は、解体再現されたあの一本の竹に再会することであったことを白状しておく。床を景色に見立てるとすれば、この竹も窓と見立てることもできるかもしれない。
すっかり綺麗に再現された下閑室は面白く、アイデア満載で、客を楽しませる趣向があちこちに見受けられる。その面白さに水を差すような一本の竹は健在だった。廃墟と対峙しているあり方も凄みがあったが、復原された空間の目移りするような面白さに対峙しているあり方も見事だった。
鋭く架け渡された一本の竹は、木々を抜けてくるウグイスの清澄な鳴き声と響き合っているようにも思えた。
-

別棟の下閑室
構成に揺らぎを与える窓のこと
さて、窓のことだ。漢字学者の白川静によると、窓という漢字は、上半分が「ソウ」という音を表しているが、心という字を下に加えたことについては判然としない、とされている。しかし、建築を設計する立場からすると、窓という存在は心が満載で、窓の切り方で設計者の意図の全てがわかるような存在であることは間違いない。窓こそは設計者が求めようとした内と外をどのように切り結ぶかという心そのものなのだ。藤井の心は、どのような景色を眺めたかったのか。
形式的な話から入るが、《聴竹居》は強い全体構成と細部へのこだわり、この二項対立が面白さになっている。趣旨から言って全体構成に関してはこの稿ではあまり触れないが、比較的シンプルな矩形平面を斜めに横断する視線のつくり方が、さほど広くない平面を伸びやかで奥行きのある空間に見せている。これが大きな構成といえる。一方、この視線の先々に様々な工夫が凝らされていて、これが全体構成を分節化し、目線を誘う道具になっている。このやり方がかなり厳密に組み上げられた平面構成に揺らぎを与えている。
-

食事室から居室及び三畳の小上がりを見る
実は《桂離宮》も同じような構成をしている。常に視線が斜めに誘導され、その先々にいろいろな視覚的な仕掛けが現れる。私自身は、この感覚はあまり好きではない。常に仕掛けられている、という感覚を持つからだ。これを「数寄屋的な空間のつくり」と呼んでもよいだろう。《聴竹居》から数百メートルのところにある《待庵》はそれとは異なる。あの狭さに、目線ではなく身体そのものがギリギリと締めつけられるような抜き差しならない緊張感がある。あれを数寄とは呼べない。
しかし、視覚的な遊びがアチコチに仕掛けられたとしても、《聴竹居》は藤井の自邸であることを忘れてはいけない。桂的な視線の移り変わりがあるとしても、桂のように後水尾上皇に見せるためだけに用意された、用心深く周到な他者に対する配慮、いわば臆病なほど病的な視線の在り方とは違う。自分のためにつくったのだから、これを遊びごころということもできる。ある意味で純粋で無邪気なところがかわいい。
なぜ縁側ではないのか
いうまでもなく開口部は、強い全体構成をくずしていくマイナーコードの主役である。その中でも主役中の主役はこの建物の前面に張り出た空間だろう。前田圭介が復原した鞆の浦にある《後山山荘》にも似たようなスペースがある。
サンルーム、ウィンターガーデンといった、藤井がヨーロッパ滞在で目にしたであろうものが、かたちを変えてここに実現されている。どちらも木製カーテンウォールとでも言いたくなるような細い柱で構成している。説明では、細いサッシの方立と柱が一体化している。そこまでこだわるのか、と驚くようなディテールが凝らされている。左右の両角には柱がなく、ガラスが突きつけで収められている。これがこの空間の抜けの良さを際立たせている。屋根が軽いから成り立っているのだが、この辺りの軽業師的な意表の突き方は数寄の手法といえる。
普通の民家ならここに縁側をつくるだろう。日当たりがよく、風通しも良い。縁側は民家の伝統が生み出した機能的にも優れた装置だ。クールチューブから冷気を導き、天井で暖気を抜く。そこまで内部環境にこだわった藤井が、縁側の物理的な効果を知らないはずがない。一方で、縁側は寒さには弱い。内部の空気流通をちゃんとすれば、ここはサンルーム的に閉じてもよいのではないか、と考えたはずだ。それが内と外の間の新しい中間領域の在り方だ、と提案しているように思える。自宅であり実験住宅でもあるこの建物の面目躍如たる表現がここに集約されている。
世界は場所の集合体で出来上がっている
チャールズ・レニー・マッキントッシュの《ヒルハウス》にあるのとそっくりな時計が居室の壁に飾られている。なるほど、と思った。マッキントッシュの日本趣味と藤井のローカリズムがここでは響き合っている。
西欧に傾く、もっと言えば、やがてはグローバルスタンダードに行き着くモダニズムの正体に藤井は気づいていたに違いない。それに否と言うためだけに藤井はこの庵をつくったのだと推測する。合理性、経済性、その逆らい難い普遍性に対して、ローカルなその場所の気候や風土、すなわちゲニウス・ロキのみが揺らぎを与え、抗い得ることを証明して見せたかったのではないか。近代建築やモダニズムを熟知しつつ、それに抗う術を模索した果てに行き着いた試作のような建物がこの《聴竹居》だといってもよいかもしれない。
-

時計が飾られた居室と食事室
京都の郊外にある山崎、歴史的な戦場の天王山の麓。京都からすれば、街中からははずれた山の中である。富岡鉄斎の絵のなかに描かれた、木の間に隠れるような粗末な隠者の草庵。藤井の心にはその世界に憧れる思いがあったはずだ。草庵に隠棲し、思考し、哲学する。そんな暮らしの場を通して、「心の窓を開け」と言われているような気がする。
床に架け渡された一本の竹は、やはり藤井の決意と意志の表明だと思えてならない。姿を見せないウグイスの澄み渡った鳴き声は、一本の竹と響き合って藤井の心の所在を教えてくれているように思えた。
内藤廣/Hiroshi Naito
建築家、東京大学名誉教授。1950年生まれ。1976年早稲田大学大学院修士課程修了後、フェルナンド・イゲーラス建築設計事務所(スペイン・マドリッド)、菊竹清訓建築設計事務所を経て、1981年に内藤廣建築設計事務所を設立。2001〜11年東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻にて教授、同大学にて副学長を歴任。2011年〜同大学名誉教授。2023年4月から多摩美術大学学長。
主な建築作品に、《海の博物館》、《牧野富太郎記念館》、《倫理研究所富士高原研修所》、《島根県芸術文化センター》、《九州大学椎木講堂》、《静岡県草薙総合運動場体育館》、《富山県美術館》、《とらや赤坂店》、《高田松原津波復興祈念公園 国営 追悼・祈念施設》、《東京メトロ銀座線渋谷駅》、《京都鳩居堂》、《紀尾井清堂》など。
近著に『内藤廣と若者たち 人生をめぐる一八の対話』(鹿島出版会)、『内藤廣の頭と手』(彰国社)、『検証 平成建築史』(共著・日経BP社)、『クロノデザイン』(共著・彰国社)、『内藤廣設計図集』(オーム社)、『空間のちから』(王国社)、『建築の難問 〜新しい凡庸さのために』(みすず書房)、『建築家・内藤廣 Built と Unbuilt 赤鬼と青鬼の果てしなき戦い』(グラフィック社)などがある。
写真:今井智己