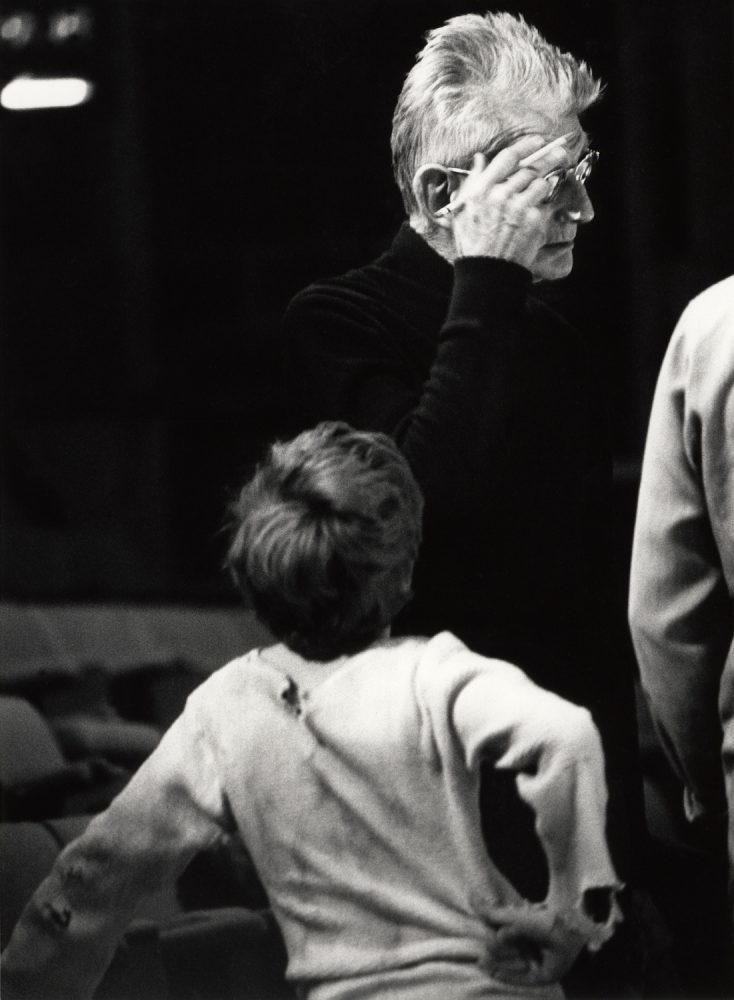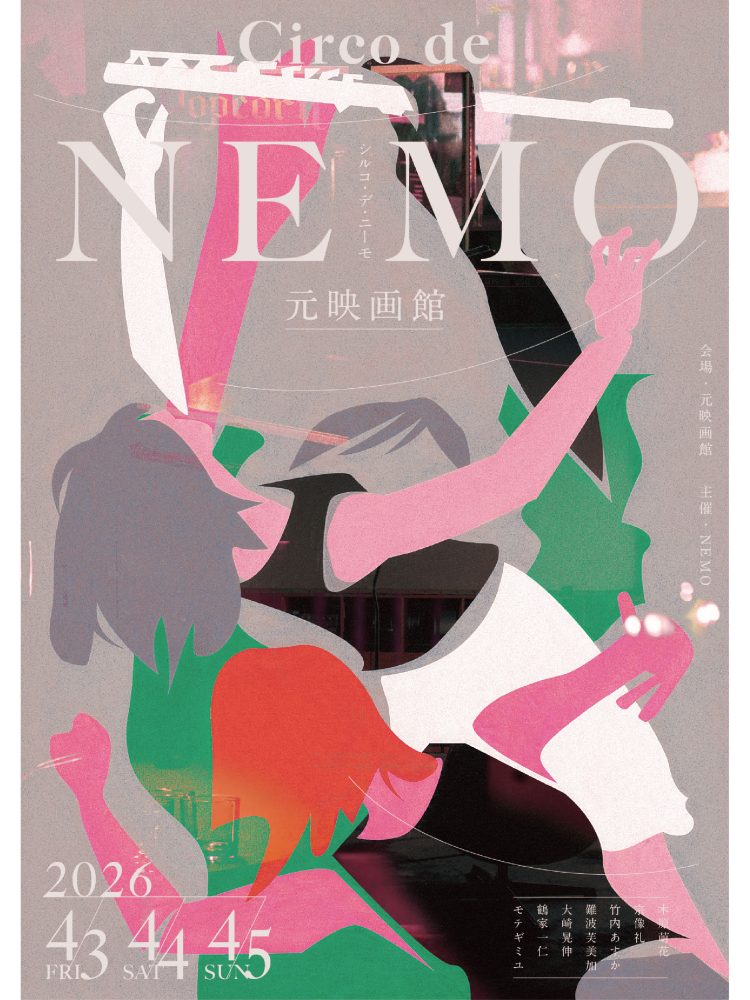滝口悠生|第5回 外を眺める娘
24 Aug 2021
- Keywords
- Columns
- Literature
窓からのぞく部屋の様子、窓から外を眺めると見える景色、移りゆく車窓の風景。人の生活に曖昧な境界線として存在し続ける窓は、当たり前のようにそこにありつつ、ときに風景を絵画のようにも切りとります。小説家 滝口悠生さんとともに窓のある風景を巡り、その窓に寄り添う人の様々に耳を傾けます。
第1回として滝口さんと幼稚園の窓を訪れたのは、2020年3月のことでした。それから1年半近く過ぎた今、新型コロナウイルスの影響のもとであらゆる窓との距離感が揺らぐ事態が今なお続いています。この大きな流れのなかにあっても、人それぞれの暮らしは着実に変わらぬ歩を進め、それぞれの窓として毅然とあり続けてもいます。最終回となる第5回は滝口さんの暮らしに灯った新たな窓辺の風景です。
娘は、よく窓の外を眺めている。
まだ自分ひとりでは自由に移動することもできないし、うまく体勢を変えることもできないから、彼女が外に目を向けられるのは、窓のそばで横になっているときか、誰かが窓のそばで彼女の体を支えているときだけだ。たまたま自分の近くにある窓の、そのガラス越しに外を見ている。
彼女の目に、その景色がどんなふうに見えているのか、それは誰にもわからない。いま両手で彼女の体を支えている親である私にもわからない。彼女を産んだ母親である妻にもわからない。彼女の視線の先にある庭の木の葉も、花も、空も、隣の敷地に建つ小学校の校舎も、それがなんであるのかを彼女はまだ知らないし、それらの名前も知らない。彼女に見えているのは、もしかしたら大人とそう変わらない景色かもしれないし、大人とは全然違う色や形を見ているのかもしれない。
乳児の視覚について科学的に知ろうとすれば、いくらでも方法はある。でも育児をしていると子どものことから離れられる時間は細切れで、本を読んだり、情報を検索したりすることがうまくできなくて、まだわからないままでいる。それに、いま自分の手がその体を支えている娘の視界について、親は、そこまで強く本当のこととか確かそうなことを知りたいと思っているわけでもなかった。それよりも、外を見ている娘の様子をそばで見ながら、娘の視界や内面についてのわからなさを認めることも大切な時間に思われていた。
その一方で、相反する気持ちもある。
そんなことは不可能だとわかりつつも、彼女のすべてを記録し記憶したい、と思ってしまう。せめて彼女が彼女自身について、自分で覚えて、忘れられるようになるまでのすべてを記録したい。彼女はたぶん、いまのこの時間のことを、覚えていられないから。それを覚えていられるのは、彼女以外のひとしかいないから。
実際、彼女の体も、表情も、しぐさも、毎日少しずつ変わっていくようだった。でもその変化をすべて確かめられるわけではなく、ある瞬間に、以前と違う、と気づくが、そのときにはすでにその変化の瞬間や過程は過ぎ去ってしまっている。そして、変わる前の彼女の体や表情やしぐさを、もううまく思い出せなくなっている。
*
娘が産まれて十日ほど経った頃のある日のこと。
娘の身の回りに必要なものを買いに行くために、近所のショッピングモールまでの道をひとりで歩いていた。冬の晴れた日で、中学校の校庭では学生が体育の授業を受けていた。私は校庭のトラックを走るジャージ姿の学生たちをなんとなく眺めながら、自然と娘の顔を思い浮かべた。
そのとき、いま自分ははじめて離れた場所から娘のことを思い出した、と気づいた。そのときまだ娘には名前がついていなかった。名前のない娘の、寝顔のような、目覚めているような、どちらともわからないようなまだぼんやりした印象の顔を、それでもちゃんと彼女の顔として思い出すことができた。離れた場所にいても、そばで顔を見ていなくても、顔を思い浮かべることができる程度には、娘が自分の世界に存在しはじめたことを知ったそのときのことを、私はきっと死ぬまで忘れないだろう。一緒にいなくても、離れていても、いま頃どこでどうしているかと思い出す相手が自分の人生にひとり増えた。それは子どもが生まれてよかったことのひとつだ。
*
でも結局、私が死ぬまで忘れないその冬の晴れた日の記憶にあるのは娘の姿ではなく、娘を思い出した自分のことに過ぎない。
文章を書くということは、過ぎ去った時間や、いまここにいない者を思い返すことでもある。言葉はそこにないものを、どうにか形にしようとする。だからそこには虚構が混ざり込む。現実を写していたつもりの言葉がだんだんと小説の形になる。
ある日私は、「私」という一人称を使って、娘の記録を書こうとしてみる。日付を記し、「私は」と書きつけてみる。その日の娘にあった出来事を、「私」という主語のもとで書き連ねてみる。彼女の見ている光景も、内面に生じる事柄も、毎日わからないと思いながらも、娘として「私」を名乗って、そこにどんな言葉が記されうるのか、試してみようとする。
まだ言葉を持たない彼女の一人称を奪う。そこには背徳感も罪悪感もあるが、小説を書くというのはそういう不遜で胡乱な手続きだと思う。ないものをあるという。私でない者になり代わって言葉を記す。
————私の父親がしているのは、そういう仕事である。
○月×日
今日から日記を書こうと思う。私は今日で、生まれてからちょうど3ヶ月が経った。日記を書きはじめるにはヘンなタイミングかもしれないが、今日は晴れて、気温も高く(夏日だ)、朝窓から見えた外の景色がきれいだった。寝室から見える、隣の小学校の敷地に生えている木。その枝葉に朝の日があたり、その向こうには青い空が見える。鳥の声がする。
いつまで続く日記かはわからない。私はまだ言葉をもたない。私が言葉を自分で書けるようになるときまでかもしれない。(……)
*
娘は平日の日中は保育園に通うようになった。
家で仕事をする父親にとって、娘が保育園に行っているあいだは、離ればなれになった娘を思い出すことができる時間でもある。でも、その時間に娘の写真を見たり、育児に関する調べ物などはしないように努めた。それをしはじめるといつの間にか時間が経っていて、自分の仕事が全然進まない。それでも、いつの間にか生後から撮りためられた娘の写真を延々眺めていて、はっと我に返ったりすることが度々あった。
スマートフォンで簡単に写真が撮れるようになって、生後半年ほどのあいだに娘が映された画像のデータはすでに数千枚に及んでいたが、どれだけ多くの瞬間の表情が記録に残っても、そこにある娘の顔は、父親が実際に見ている娘の顔とは同じではなかった。写真と実物が違うのは当たり前なのだが、自分の記憶を以てしても、カメラと写真を以てしても、娘の過ぎゆく現在を完璧に記録することはできない。そのことに、何度もたじろいでしまう。今日見る娘の顔からは、昨日の娘の顔がもうすでに消え去ってしまっていて、うまく思い出せない。ならば娘と離れているあいだに自分が思い出す娘の顔は、いったいいつの娘の顔なのか。というか、それは本当に娘の顔なのか。
娘の目に見えている景色がわからないばかりか、自分がいま見ている娘の姿が、自分の視界が、どこまで現実と隔たっているのかさえ、わからなくなってくる。
*
2021年の1月。娘が生まれたとき、東京は新型コロナウイルスの感染拡大による2度目の緊急事態宣言のさなかだった。それから半年が経ったが、いまのところ娘が過ごした時間の大半は緊急事態宣言下にある。父親の出産立ち会いはできず、産後6日目に母子が退院する日に、私ははじめて娘と対面した。
だから最初に娘の姿を見たのは、スマートフォンの画面越しだった。生まれて数十分後に妻が撮って送ってくれた写真には、妻の隣で目をつむり、口を開けている娘の顔が写っていた。その後も、写真や動画で娘を見ていたけれど、はじめて実物の娘を前にすると、その顔も体も想像していたよりもずっと小さかった。
生まれたときの体重は3000gを超えていたから平均より大きいくらいだったのに、スマートフォンの画面を通して見てもなかなかその大きさはわからなかった。画面で見るとどうしてか実物よりもずいぶん大きく見えてしまうというのは、私に限ったことではなく、写真を共有している私の母親つまり娘の祖母も、実際に娘と会ったときにはいつも写真で見るよりも小さい、と言った。
自分の目で見る娘と写真に写る娘のあいだにある齟齬がどういうわけで生じるのかはよくわからないが、そのことについて考えているうちに、ずっと昔に撮っていた一眼レフのフィルムカメラを久しぶりに使ってみたいと思うようになった。
友達から借りたそのカメラで写真を撮っていた頃、ひとを撮ることはあまりなかったが、出かけた先や公園などでファインダーをのぞきながら、その向こうにある対象の位置や厚み、周囲のものとの距離の有り様を自分の目は必死に測ろうとしていた。あの小さな窓をのぞき、いくつもの機構を通して見る景色は、裸の目で見るのとは全然違って、後に現像された写真が思うような出来映えだったことはほとんどなかったけれど、あの小さな窓からしか見えない景色があり、それを見ているいまの感覚をどこかに繋ぎ止めるようにシャッターを押した。記録するというよりは願う、あるいは祈る、そういう感触があった。
どんなカメラでどんな撮り方をしようとも、実物と写真の差がなくなるわけではないし、現実を完璧に写し取れるわけではない。目の前にあった景色が、失われてしまうことにも変わりがないし、久しぶりでうまく写せるかもわからない。でも、自分の目に映る景色に対して、為す術なくただ祈るしかない時間が、記録ではなく記憶の方を少し変えるのかもしれない。スマートフォンの画面に映し出される映像を一時停止させるような手続きではなく、カメラの小さな窓を通して娘を見て、祈るようにシャッターを切る手続きが、父親の記憶のなかの娘の有り様を少しだけ変えるかもしれない。あるいは娘の背後でカメラを構え、彼女が目を向けている先にレンズを向けてみたならば、どんな景色が見えるだろうか。
*
自分で思うように移動できない娘にとって、窓越しに眺める外の景色は、途方もない世界の広がりのそのはじまりだ。そしていまは親にしたって似たようなものだった。家の外に出たとしても、行きたい場所に行きたいように行くことや、好きな場所を自由に訪れることが、なかなかできない世界になってしまった。
まだ行ったことのないいろんな場所に行くことを思いながら、私たちはいま窓辺にいる。
滝口悠生/Yusho Takiguchi
1982年東京都生まれ。2011年「楽器」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2015年『愛と人生』で野間文芸新人賞、2016年「死んでいない者」で芥川賞を受賞。他の著書に『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』『高架線』『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』などがある。