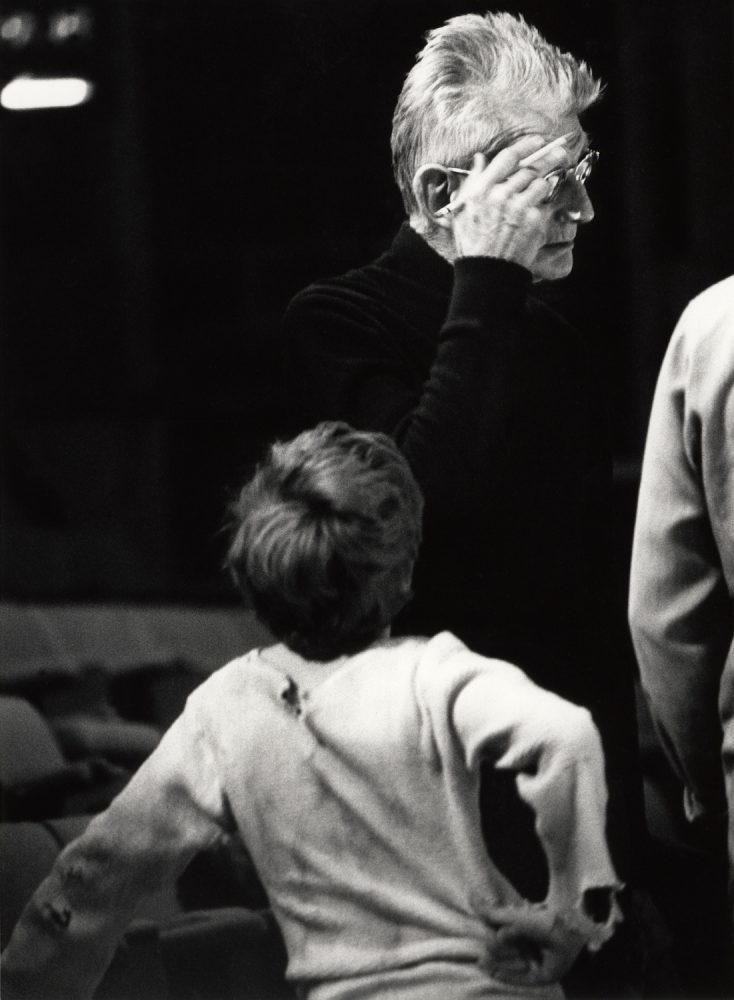滝口悠生|第2回 サジヤ(渋谷・神山町)
09 Jun 2020
- Keywords
- Columns
- Literature
窓からのぞく部屋の様子、窓から外を眺めると見える景色、
渋谷の喧騒を抜け、「奥渋」といわれるエリアに入る遊歩道沿いに料理とワインの店「サジヤ」があります。田中さんと池上さんのおふたりが10年近くこの場所で営んでいるお店です。まず目に入るのがふたつの古い窓で、なんとも愛嬌のある見た目。おふたりとこの窓との関係が気になり、滝口さんと訪問しました。
渋谷駅から文化村通りをあがってきて、東急を左手に見ながらそこから細くなる道をさらに奥に行く。個人的な土地勘としては、映画館のUPLINKや書店SPBSに行くときに通る道、と認識されているその道には、古い商店もあれば新しくできた店もあって、一本脇に入るとほぼ並行して延びる遊歩道もある。東京の遊歩道はむかし川だったところを暗渠にした道が多く、調べればここも渋谷川の支流の宇田川という川だったようで、ゆるやかな蛇行のあとを残している。
夜にこの遊歩道を歩くと、道沿いにふたつ並んだ窓とそこからこぼれるオレンジ色の灯りが見える。2011年、池上ひさかさんと田中篤さんがこの遊歩道沿いに残る古い小さなビルの1階に開いたビストロ「サジヤ」の窓。
「この窓を見たときに、ひと目で気に入って、ここで店をやろうって思った」と池上さんが教えてくれた。
木の枠で縁取られたガラス窓は外から見るより店内から見た方が大きく感じた。下辺は思いのほか床に近い低い位置にあって、上辺はパンの頭のようにアールがついた山型になっている。壁から少し奥まった出窓になっていて、その手前にはワインのボトルや植物などが飾ってある。並んだもうひとつの窓も同じ形で、オープンキッチンになったカウンターテーブルの横にある。
店内はだいたいコの字型をしている。遊歩道沿いの入口のドアから見て左手にカウンターとキッチンがある。キッチンでは田中さんが黙々と調理をしている。テーブルは右手の壁に沿って奥にふたつ並んでいて、そのまま左奥につながるスペースにもテーブル席がある。奥の部屋の手前はキッチンとのあいだを仕切る形で壁があり、ここはビルの階段の下にあたるようで壁につながる天井は壁のなか程の高さまで斜めに下がっている。内装は白く塗られた壁と棚やテーブルの木材が基調となっているけれど、カウンターのテーブルがカーブしていたり、間取りもアシンメトリーで斜めに下がる天井があったりと有機的で、店内のいろいろな線や形が窓の山型と呼応しているみたいに思えた。
キッチンと階段下の壁のあいだにつくられた通路が、池上さんの持ち場である。「その、床がいちばん黒いところ」と笑いながら池上さんが示した。コンクリートの床をよく見ると、なるほどその付近は色が濃くなっていて池上さんの動線がよくわかる。
田中さんが料理を、池上さんがワインとデザート、そして給仕の仕事をそれぞれ分担している。池上さんはキッチンと客席のあいだに立って、お客さんに料理の説明をして注文をとり、田中さんが仕上げた料理の皿を受け取ってテーブルに運ぶ。ワインの栓を開け、飲み物の用意をする。パンを切ったり、デザートをつくったりもする。各テーブルの様子をうかがいながら、皿を替えたり、追加の注文を聞いたり、お会計の伝票の計算もそこでする。池上さんはその場所からお店全体の状況に目を配っている。
でも、このお店をはじめるまで給仕の仕事はしたことがなかった。池上さんと田中さんは以前働いていたフレンチレストランで出会ったが、その店では池上さんも調理場に立って料理をつくっていた。
「自分たちのお店だから接客のスタイルもなにも決まってることがないし、誰が教えてくれるわけでもないし、接客するのは私しかいないから、毎日自分で考えて自分で決めていかないといけなかった。いまとなっては、よくやろうと思ったな、と思うけど。型がなかったのがかえってよかったのかもしれないね」と池上さんは言う。
ワインと、ワインに合わせる料理の店。黒板にその日ごと手書きで書かれるメニューにはフランス語が併記されている。知らないひとをこの店に誘うとしたら、「ビストロ」と説明するのがたぶんいちばん適当な呼び方だと思う。料理にも、食器にも、テーブルに置かれた紙ナプキンにも、料理やワインが提供される呼吸にも、きりりとした緊張が行き渡っている。けれども、料理を食べて時間を過ごすうちに、池上さんのサービスは「食堂」とか「酒場」という日本語で呼びたくなるような気安さもテーブルに与えてくれる。その絶妙な和やかさもこの店に足を運ぶひとたちにとっての魅力のひとつだと思う。その安心の塩梅は、どんなふうにつくりあげられたのか。
「毎日気がついたこととかをひとつずつ足したり引いたりしながら、だんだんできることが増えていって、そうやってちょっとずつ変わってきた、のかな。いまでもできないことはたくさんあるんだけど」
お店を始めてしばらくのあいだ、キッチンの田中さんはお客さんと全然話をしなかった。オープンキッチンだからお客さんから田中さんの姿はずっと見えているのだが、田中さんは料理に徹して余計なことは話さず、お客さんとのコミュニケーションはすべて池上さんに任せていたという。「だからはじめの頃は、これじゃオープンキッチンにした意味ないなあ、と思ってたの」と池上さんは笑う。
でも田中さんは別にお客さんと話したくなかったわけではなかった。「お客さんがいっぱいで、池上ひとりで手が回らないときとかは、俺も料理運んだりしてたんだけど」と田中さんがキッチンから話を挟む。「でもそれで料理運んだついでに俺がお客さんと話したりしてると、私の場を荒らさないで! って池上が思ってるのがわかるんだよね。だから、忙しいときは手伝うけど料理の皿だけ置いて余計なことしゃべらずに戻る、みたいな感じだったかな、最初の何年かは」
「そうなの!」と池上さんは少し苦い表情になった。「むかしはもっと高圧的だったっていうか、自分の思い通りにこのテーブルを進めたい、みたいな気持ちが強かったのね。だから田中さんが出てきたりすると、邪魔をしないで! みたいに思ってしまって」
それが、店を続けていくうちに、だんだんと変わっていった。どう変わっていったかを言うのは難しい、としながらも池上さんは「あー、でもこの1、2年でぐっと気持ちが楽になった」と言った。「ちょうど40になったあたりから。年を重ねたせいなのかな、わからないけど。肩の力が抜けたというか、前はあれもしたいこれもしたいって、したいことがたくさんあったんだけど、最近は、しないってことを意識するようになった。少し前までは、自分の理想みたいなものに沿ってこのお店を動かしたいと思ってたんだけど、最近は自分が自分がじゃなくて、お客さんが楽しく気持ちよく過ごすためになにをするかって考えるようになってきて、そしたら、なにをしないか、っていうふうに考えることが多くなった」
田中さんは、調理中はいまでも寡黙だが、作業がひと段落するとなじみのお客さんと気さくに会話を交わすようにもなった。
「あと、マリコね」と池上さんはふだん池上さんが立つ場所でパンを用意していたスタッフのマリコさんを見た。元々お客さんとしてこの店に来ていたマリコさんは、昨年から週に何日か店に立ってサジヤを手伝うようになった。「マリコが入ってくれたこともこの店にとってすごく大きい」
これまで店をやってきたなかで、池上さんも田中さんも、ひとをつかうことは一度も考えたことがなかったという。田中さんがホールに出てくることさえ池上さんが拒んでいたのだから、それも当然だったかもしれない。「でも、1年くらい前にふと、あ、誰かいてもいいな、って思ったんだよね。なんかすごく自然に」
それで池上さんがお店に来ていたマリコさんに「ここで働かない?」と声をかけた。
顔が似ているわけでもないのに、並んでいるとふたりはなんだか姉妹のようにも見える。まだまだ勉強中です、とマリコさんは笑い、池上さんは、マリコはマリコで考えて自分のやり方をつくっていってもらえれば、と話す。
足すことと引くこと、ぴんと張ったところと緩まるところ。そうやってだんだんこのお店がつくられてきたし、これからもきっと少しずつ変わっていく。サジヤのサジはお匙のサジ、匙加減のサジだそうだ。
ふたりは、お店を開くと決めてから1年以上かけて100件以上物件を見てまわった。ひと目で気に入った山型の窓が決め手だったが、ビルが古い建物だったこともこの場所を気に入った理由のひとつだった。「昼間に外からこの店を見ると、ああいいなあって結構気に入ってる。オンボロで」
ふたりよりも年上の、築50年くらいのビル。いまのサジヤの場所には、かつて喫茶店があったという。ふたつの窓は喫茶店時代からずっと変わらずにあるもので、大家さんからこの窓だけはいじらないで残してほしいと頼まれた。
「古いことは、きっかけになってくれる」と池上さんは言った。
あたりに古い建物もないではないが、その周辺ではサジヤの入った建物はひときわ古く、夜闇のなかではわかりにくいが、日中だとその古さがよくわかる。
「学生の頃、絵を描くときも、真っ白なキャンバスよりかは、なにかきっかけがある方が描きやすいっていうか、自分を出せるように思えたんだよね」
池上さんはもともと美大で油絵を描いていた。でも、大学で絵を描いているうちに、だんだん自分の描いたものが作品として残ってしまうことへの抵抗が大きくなった。描いているときは夢中になれるのに、描き終わってできあがった自分の絵を好きになれない。結局大学を退学して、自分の立つ場所を食の世界に変えた。「食べたり飲んだりってなにも残らないでしょ。それがいい。楽しく飲んで食事して、終わったらなにも残らないで楽しかった思い出だけが残る」
たしかに、どんなにおいしい料理も、お酒も、仕舞いには皿もグラスも空になって、なにも残らない。けれども、古い建物やその窓に愛着を示す池上さんは、形が残ることへの抵抗を感じると同時に、目に見えずに残るものへの強いこだわりが、実はとてもあるのではないか。
古さは形に残るわけではない。古い壁にペンキを塗ればその表面は新しくきれいになるけれど、そこにあった時間が完全に消し去られるわけではない。そこにあった時間は残る。人間の感覚はたいしたもので、いくら表面がきれいでも、そこにある曰く言いがたい蓄積を察知できるし、してしまう。
絵の話でも、お店の話でも、「きっかけ」を見つけて自分を表現する、という話を池上さんが繰り返していたのが印象的だった。その場にあるなにかをきっかけに、それに反応することで、自分のうちにあるものを表現することができる。
この建物の古さが、池上さんと田中さんがサジヤをスタートさせるために必要な「きっかけ」だった。けれどお店が時間を重ねていけば、そこにある古さは自分たち自身の時間にもなっていく。池上さんが自分の理想にこだわらなくなったり、マリコさんを店に迎えたりした変化は、サジヤという場所がこれからも「きっかけ」であるための変化だったように思える。
せっかくだから、と勧められて、池上さんと田中さんそれぞれがいつもいる場所に立たせてもらった。
池上さんの持ち場のキッチンと客席のあいだの通路に立つと、ふたつ並んだ左の窓がよく見えた。店の前の遊歩道を行き過ぎるひと、お店のなかをうかがって入ろうかどうか迷っているひと。お店に入ってくるひとは、だいたい窓越しに見た時点でわかる、と池上さんは言う。池上さんは店のドアが開くより先に、もう窓のこちらからお客さんを迎えているのだ。マリコさんが感心した声をあげた。「私はまだ、ドアが開いてはじめて、あ、お客さんだ、って思います」
次に、調理場に入れてもらって田中さんがいつもいるコンロの前に立ってみた。そこから見ると、さっきまで自分のいた店内の様子が全然違うものに見えた。調理場の田中さんの位置からは、ふたつ並んだうちの右の窓から外の様子がよく見える。「料理つくってるときに、歩いてくるひとと目が合うんだよ。知らないひとに会釈されたり」
立つ場所が違うと、見える景色は全然違う。池上さんの見ている窓からは、お店に向かって歩いてくるひとの姿が見えるけれど、田中さんの見ている窓からは店の前を通り過ぎるひとの顔がよく見える。あるいは通り過ぎていったひとの後ろ姿が、遊歩道のずっと先に隠れてしまうまで見える。
外から見ると隣り合って並ぶ同じ形の窓だけれど、ふたりのそれぞれの立ち位置から見ると、その窓からは全然違う景色が見える。同じ空間の少し違う位置から、それぞれに「きっかけ」を見つけては、足したり引いたりを続けている。
毎日の営業が終われば、お店にはなにも残らない。料理やお酒はお客さんのお腹のなかに消えて、楽しい晩餐の思い出とともにお客さんも帰っていってしまう。でも、そうやって繰り返される毎日の時間は、この場所に混ざっていき、残っていく。この建物にも、この街にも残る。それがまた誰かにとっての「きっかけ」になる。
滝口悠生/Yusho Takiguchi
1982年東京都生まれ。2011年「楽器」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2015年『愛と人生』で野間文芸新人賞、2016年「死んでいない者」で芥川賞を受賞。他の著書に『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』『高架線』『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』などがある。