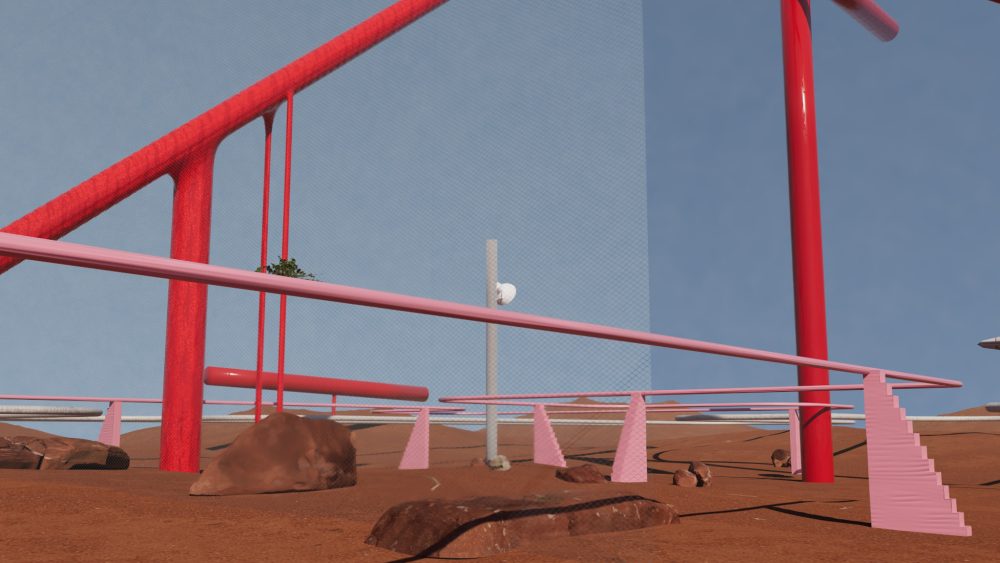旧館林市庁舎:
市政におけるコミュニケーションのあり方としての窓
20 Nov 2025
- Keywords
- Architecture
- Columns
- Essays
- Japan
菊竹清訓の著作『代謝建築論』で語られた理論「か・かた・かたち」の実践のひとつとして1963年に竣工した《旧館林市庁舎》(現・館林市民センター)。DOCOMOMO Japanの選定建築物にも2022年に選出されたこの建物は、グラフィックデザイナーの田中一光との協働もあり多様な特徴的な窓を持つ。DOCOMOMO Japanの玄田悠大氏が1960年代の時代背景を交え、目指された市政を建物と窓を通じて解説する。
1. 新たな市政の拠点
館林駅を降りて徒歩で約10分。駅前広場を過ぎて左に曲がり、少し歩くと、右手の仲町公園越しに一面ガラス張りで幾何学的な構成が特徴的な旧館林市庁舎が現れる。設計は菊竹清訓によるものである。
南の千眼寺、北の常光寺に挟まれたこの建築でまず目に飛び込んでくるのは、中空に浮かぶ三層分の連続窓である。透明性のある外観は、行政の姿勢を直感的に伝えている。菊竹自身、連続窓の四隅に立つ巨大な壁柱について「都市という広い空間に、場をつくろうとするための強さであろうとした」ものであり、「市庁舎を支えると同時に、都市に支えられるという表現でなければならない」「館林市の柱となる壁柱として独自の強さをもつことになった」と述べている。
館林市のほぼ中心に位置するこの場所には、以前から町役場が置かれていた。1954年、1町7村の合併により館林市が誕生。それから約10年後の1963年、新たな市政の拠点として、メタボリズム建築である旧館林市庁舎が竣工した。
2. 旧館林市庁舎が竣工した時代と菊竹清訓の建築的展開
1960年代は、メタボリズムが大きく展開した時期であり、昭和の大合併を背景に各地で公共建築が竣工した。DOCOMOMO Japan 選定建築物に限っても、坂倉準三の羽島市庁舎(1958年竣工)、丹下健三の香川県庁舎(1958年竣工)、佐藤武夫の旭川市庁舎(1958年竣工)、菊竹と安田臣の島根県庁周辺建築群(1958-1970年竣工)、坂倉準三の芦屋市民会館(1963年竣工)、上野市庁舎(1963年竣工)、佐藤武夫の岡山市民会館(1963年竣工)、坂倉準三の枚方市庁舎(1964年竣工)、大髙正人の全日本海員組合本部会館(1964年竣工)、川島甲士の津山文化センター(1965年竣工)、建設省近畿地方建設局・片山光生の奈良県庁舎(1965年竣工)、磯崎新の大分県立中央図書館(1966年竣工)、丹下健三の山梨文化会館(1966年竣工)、そして菊竹の都城市民会館(1966年竣工)など、全国各地に優れた公共施設が次々と建設された。
-

南東からの全景。写真左(南)に千眼寺、右奥(北)に常光寺が見える
菊竹はこのタイミングで、『代謝建築論』の「か・かた・かたち」の思想を実践し、スカイハウス(1958年竣工)、旧館林市庁舎(1963年竣工)、東光園(1964年竣工)と、構造によって空間を浮遊させる形式を発展させた。菊竹清訓建築設計事務所の所員であった内井昭蔵は、都市計画の重要な課題の一つとして「ここの人間を結びつけるにはいかなる場を提供すれば良いか」と問い、「都市の本質はコミュニケーション」であるとした。彼は「天降り式の役人対市民の対立関係」ではなく、人間相互の信頼が都市で新しく求められていると考え、市民対市民や市民対役人といった各々に対するスペースの〈かた〉を意識し、議場、業務部門、四方にのびたフラットスラブという、3つの支えるものと支えられるもの、そしてそれを結ぶものの有機的結合が、空間の機能の絶えざる流動性に対し、自由な、しかも秩序ある形態を表現することができるとしている。この空間のシステムこそ彼らが市庁舎の〈かた〉としてとらえたものであった。なお実現はしなかったが、建築を拡張する構想もあった。
3. 現代の「館林城」を彩る窓
竣工当時、現在駐車場や車路になっている場所には、主棟の周りに池と築山が設けられていた。来庁者は南側の正面入り口から入り、池に架けられた渡り廊下を通って主棟の1階と2階に至る。それぞれに一般事務カウンターが設けられていた。この空間の設計意図は「市民生活に密着し、親しみと、うるおいを与える『見とおし』のきく空間をつくる」ことであり、渡り廊下南面の大規模な縦格子窓はル・コルビュジエの造形表現を思わせながらも、日本的な連子窓も連想させる。
この主棟2階部分には、田中一光によってデザインされた五角形の窓が規則的に配置されている。書庫空間に用いられたこの造形は、城郭の鉄砲狭間を思わせる。館林は館林藩の城下町であり、その中心に館林城があった(この館林城跡に現在の館林市役所がある)。館林城は城沼に囲まれた大地に建っていたことを考えると、旧館林市庁舎は、まさに現代の城郭として構想されたと考えることができよう。
4. 窓を通じた近景との融和
主棟に入り階段室を上がると、踊り場に大窓が設けられている。そこから横目に連続窓の造形が覗かれ、城郭を思わせる細かな装飾が観察できる。また、連続窓越しに千眼寺の意匠が重なり合い、近景に近世、遠景に近代という対比が生まれている。階段室の扉は田中一光により塗り分けられており、空間に抑揚を生み出している。
-

踊り場の大窓から連続窓の造形(写真左)と千眼寺の意匠(写真奥)が見える
5. 窓が表す市政の姿
東西南北すべての面に設けられた連続窓からは、館林市全域が俯瞰できる。窓ガラスは竣工当時のものが多く、大切に使い続けられている。市庁舎時代には、職員がこの窓から市内を望み、地域の課題を議論していたであろう。まるで建築家が模型を囲んで議論するかのように、窓外の都市景観はリアルなジオラマであった。市民への透明性も表現するこの窓は、当時の市政が市民とどのようなコミュニケーションを取ろうとしていたかを如実に表している。
6. 都市の将来を方向づける議場の窓
内部空間のハイライトの一つは最上部に配置された議場であろう。上部から光を導く十字型の天窓と不規則な明かり取りが荘厳さを演出し、多様な都市課題を受け止める市の姿勢を象徴しているようである。
内井昭蔵によると、議場空間は「方向性よりも求心性が必要」であり、「市民全体が支えているという感じを出すために最上階に配置」し、それを4つのサービスシャフトで支え、市民の生活と結びつけるものとして業務部門の空間を持ってきたと述べる。菊竹は「全員の参加する審議にふさわしい空間は、そのポテンシャルを十分に包括するだけの空間容積をもって高められていなければならない」とし、「その高さは光の導入の仕方によって、強調もされるし弱められもするだろう」としていた。
また、議場空間の問題を「他と交換しあう空間条件と、個の内部に回帰する空間条件の二つの重なり」であるとし、その基本条件を「全体の合議と個人の決定という原則」におかれるものとした上で、「われわれの議場方式として、果たしてどうゆうものがふさわしいものか、これは今後ともわれわれの課題であって、よりふさわしいものへの努力をつくさねばならない」と述べている。こうして議場は「市制の明日を決定し、都市の将来を方向づける」場として位置付けられ、上部からの採光は、合議の象徴と理解できよう。
7. まとめ
旧館林市庁舎は、新しい時代における市政のコミュニケーションのあり方を表現した建築であった。それは菊竹清訓の建築思想を通じて現出した現代の城郭であり、「見とおし」と「見はらし」を通じて都市と結びつく建築であった。館林の風土や歴史へのまなざしを根底に、市政と市民の関係性を窓を通じて空間化した点が興味深い。
今日、この建築は役割を市民へと引き継ごうとしている。変容する空間内のコミュニケーションは、さらに新しい価値を空間に付与するだろう。窓の意匠性や透明性に象徴される建築の意図を今後どのように解釈していくか。それは、担い手である市民自身が探求し続ける課題であり、その行為自体がこれからの館林を築く城郭となることを期待したい。
玄田悠大/Yuta Genda
近代都市史・近代建築史研究者。東京大学大学院都市デザイン研究室学術専門職員。博士 (工学)。魅力的なまち、建築やコミュニティとのつながりを未来へ継承したいという思いから、田園都市や新教育などグローバルな視点を切り口に、地域研究やまちづくりに取り組む。DOCOMOMO Japan事務局長。独立行政法人職員。
論文に「玄田悠大, 米森公彦, 竹内雄一, 永野真義, 中島直人,文化財として未認知のモダニズム建築にみられる保全継承プロセスに関する一考察:―アントニン・レーモンド設計『旧赤星鉄馬邸』を対象として―, 日本建築学会計画系論文集 87(793), pp.668-679, 2022」など。