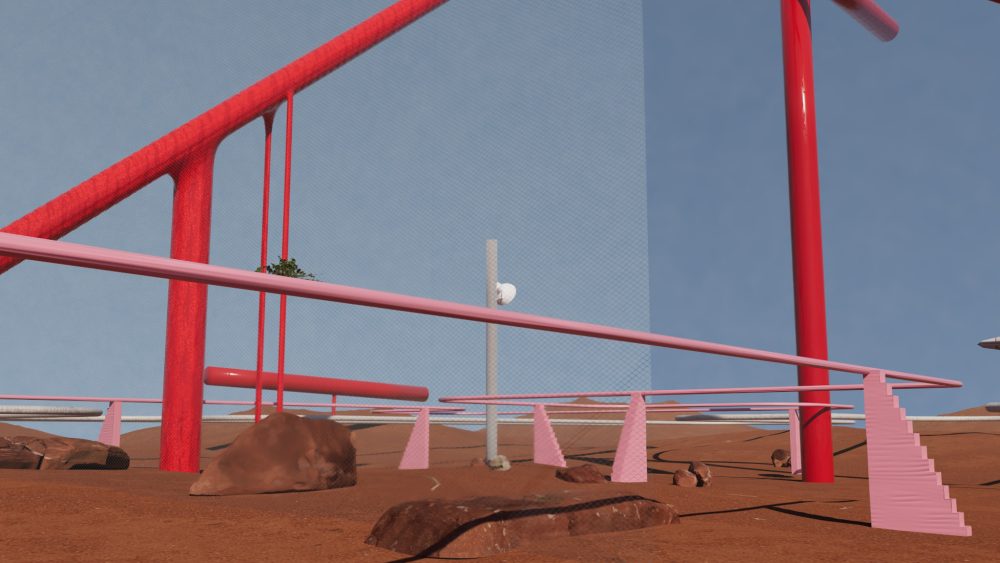山口蓬春と吉屋信子の終の棲家を訪ねて ─
吉田五十八、その設計の多様性を知る
25 Jul 2025
欄間の吹き抜きや建具の引き込みといった材や納まりを究極までそぎ落とす合理的なデザインを試行し、「新興数寄屋」と呼ばれる数寄屋造の近代化を成し遂げた建築家・吉田五十八。山口蓬春邸(山口蓬春記念館)と吉屋信子邸(吉屋信子記念館)という戦後に生み出された対照的な二つの住宅を建築史家が訪れ、そこに新たな眼差しを向ける。
山口蓬春邸と吉屋信子邸 ─ 戦後、ふたつの終の住まい
2025年1月に吉田五十八の手による戦後の作品をふたつ訪ねた。
ひとつは葉山の山口蓬春邸。日本画家・山口蓬春は、東京世田谷の祖師ヶ谷から山形に疎開、戦後葉山へ。1948年にここに移り、1971年に亡くなるまで暮らした。よく知られる画室(アトリエ)の竣工は1953年。1990年、山口家から土地建物と所蔵作品の寄贈を受けた財団法人JR東海生涯学習財団(現・公益財団法人JR東海文化財団)によって、1991年から山口蓬春記念館として公開。建築家大江匡による保存改修と改築が行われている(2023年、国の登録有形文化財に登録)。
-

山口蓬春邸(現・山口蓬春記念館)南側外観。右奥テラスのスチールフレームは大江匡の改築による
もうひとつは鎌倉は長谷の吉屋信子邸。作家の吉屋は1920年代に女学生の圧倒的人気を得てベストセラー作家となった。生涯貫いたおかっぱ頭がトレードマークで、少女小説、家庭小説、時代ものなどで女性をテーマにした大衆文学を書き続けた。戦前からの東京牛込の住宅を、戦後1950年代に出て麹町へ、ついで1962年に鎌倉に移る。1973年の他界までこの家に住んだ。翌1974年に鎌倉市に寄贈され、吉屋信子記念館として長年運営されてきた。
多くの芸術家や文化人の家をつくった吉田だが、わけてもふたりは掛け替えのないクライアントだった。山口の2邸、吉屋の3邸すべてに吉田は設計者として関わった。山口は1893年生まれで吉田と東京美術学校の同期。吉屋は1896年生まれで、吉田に好きに設計させた東京牛込の最初の家が、メディアで話題になり設計者の名を世に知らしめた。今回訪ねたのは、山口54歳、吉屋66歳からの終の棲家となった家で、後半生の創作の場でもあった。彼らは都心でも郊外住宅地でもない風光明媚な景勝の地を選んだ。吉屋は1939年に鎌倉に別荘をもうけ、戦時中はそこに疎開していたのだから、彼女にとって鎌倉はかつて避暑地であり避難地であった。東京は、敗戦後の廃墟の混乱から高度成長の混乱へと変貌しつづけ、たしかに心休まらぬ場所であったのだろう。
かようにふたつの家には共通点が多い。しかし訪ねてみると雰囲気はまるで違い、面食らってしまった。
山口蓬春の画室
山口蓬春邸のハイライトは画室だ。戦前の山口邸にももちろん画室があり、その規模は東西15尺(4.5メートル)、南北18尺(5.4メートル)で、15畳大であった。今回訪ねた二代目画室は、東西15尺、南北16尺と少し小さいが、かわりに南に4尺のベランダが足される。このサイズの広間で、天井高が10尺ほどもあるので、廊下を通って画室に入った瞬間、ちょっと立方体のようにも感じられる。大きな障子の面が正面にたちあがるが、和室の感覚ではない。
-

山口邸画室内観。障子から柔らかな光が差し込む
さらに特徴をあげていこう。従来日本画家は畳上で制作していたが、ここに畳はない。ヘリの線が目立つし、床に紙をひろげる際にはその凹凸も煩わしいからだ。かわりに床は寄木張としてカーペットを敷く。壁は木部を覆って大壁とし、リシンで明るめの褐色に仕上げる。画材の収納も壁紙を太鼓張りにした扉を閉じるとひとつの面になる。
開口部の枠は省略できないが、刃掛と呼ばれる納まりを徹底して見えがかりを消す。天井面と面一にしたアクリル板を通して蛍光灯の白い光が均質にひろがる。障子は桟の間隔を大きくして線を減らし、桟の見附も細く追い詰めている。また長押をなくし、ベランダ天井面と揃う高さまで、欄間を一体化した特大の建具とする。床から天井までピンと張った白い面。さらに障子・ガラス戸・網戸・雨戸のすべてを、壁と一体的につくられた戸袋に押し込めるので、開け放たれた開口部に建具が残ることはなく、部屋はぽっかり口を開け、さらにベランダの床が180ミリほど落としてあるのでガラス戸の下框は見えず、ゆえに画室はパーンと外へ開いてしまう。南下がりの庭、海の水平線、そして空……。
伝統から離れて
吉田五十八は新興数寄屋の生みの親として高名だ。吉田の青春時代は西欧で近代建築が確立してゆく時期だが、彼はそれを輸入する道を選ばなかった。かわりに彼は数寄屋にねらいを定めた。日本橋区呉服町に生まれた五十八の周囲にはたしかに色濃い江戸風が息づき、かつて伊藤ていじが指摘したように芸事とそこに連なる数寄の世界が切り開くモダニティもあった(文献3)。吉田は、近世的な技術文化の継承者たる大工や建具師たちからその伝統を学び、かつそこから逃れることで、近代的な感性にふさわしい意匠に至ろうとした(文献7)。ある意味で吉田は戦略家であったように思える。驚くべきことにその試みは数年の格闘により達成される。1935~36年頃のことだ。その造形と技法が、以後も洗練されこそすれほとんど変更されなかったとみるのは間違いでない。また彼の晩年、そして没後、吉田について論じる者はみな、いま和風と見えるもので吉田流新興数寄屋の影響がないと言えるものはじつはほとんどないのではないかと口を揃える。それほどに広い模倣の裾野を、吉田の意匠はつくり出したのである。
彼が目指し、獲得した新しい数寄屋の特徴は、日本建築をベースにしながら「面」で規定される空間ヴォリュームの感知を高めていくところにある。彼は柱・長押・枠・桟などの「線」が「うるさい」と考え、それを減らすことで、近代的な単純な明快さ、吉田の言葉でいえば「明朗性」の獲得に至ることを試みたのである。
-

障子戸を開けた画室。ベランダの開口部がL字型に回り込む
村野藤吾によるこんな吉田評がある。「氏は、氏一流の解釈と仕方で、歴史を容赦なく切り捨て、現代的に組み直した」(文献3)。吉田は歴史を正しく見る眼を持つと村野は言う。そのうえでなお吉田は歴史を「切り捨て」た、それも「容赦なく」、と言うのである。敬意と批判の両方を込めた言葉であったと思う。
蓬春画室は、「歴史を切り捨てた」空間の端的な例であろう。伝統の世界にあったものがそこにはほとんどない。たとえば折れ連なる床・縁。その上に対応する深い軒。それらが深い暗がりを室内につくり、そこに多数の柱と建具が垂直の線や面のリズムをつくる。先例の参照を前提としながら、含蓄ある自由闊達さによって生まれる意匠の楽しみ。それらはないのだ。トラックの箱型荷台の内側から外を見るような感じに、むしろ近いとさえ思える。
室によってあまりに違う
山口邸では、画室、主屋、庭のすみずみを巡ってみたが、それらすべてがひとつの明るく清浄な空気に満たされていた。素木の明るい色、白い障子紙、主張のない落ち着いたリシン仕上げの壁。おおらかな空間。明快さ。自然主義的な陰影と奥行きのある庭は、山とも海ともつながり、環境全体の一貫性を妨げることがない。
-

吉屋信子邸(長谷の家/現・吉屋信子記念館)南側外観。「奈良の尼寺のように」という吉屋からの要望を受け設計されたという
-

吉屋邸へのアプローチと玄関 -

寝室南面の窓
しかるに吉屋邸は別物であった。雁行はない。建物と庭の浸透関係は希薄。玄関と居間では黒く太い柱と梁がすべての壁に表現されているが、その梁は張り物と分かる。吉田作品で民家風の意匠が珍しいわけではない。初期の杵屋六左衛門別邸(1936)から鉄筋コンクリート造の玉堂美術館(1961)まで事例は少なくない。だが、ここ吉屋邸では、白い紙張りの薄板を網代風に貼った天井の目地がシルバーに鈍く光り、これと民家風の黒い木部との取り合わせはいくぶんキッチュにも思える。かと思えば隣の和室は艶のある整った数寄屋風の座敷である。
書斎はすべての壁面が白く、収納扉が格子状のパタンをなし、天井照明や窓障子の格子とあいまってバウハウス・デザインを見るかのよう。寝室は壁紙で覆われた洋室。台所は白くペイントされた木部とガラス棚が昔の病院のような几帳面な雰囲気。……要するにバラバラなのである。統合、洗練、一体感からはほど遠い。
〈広間の系列〉
吉屋邸でのこの戸惑いは、山口邸を見直すよいきっかけを与えてくれた。振り返ってみると、山口邸では澄み渡るような一体感のために、室による差異が見えにくかっただけだ。それに、山口邸主屋の茶の間と、吉屋邸の座敷は、木部が素木か黒いかの違いはあるが、それ以外はとてもよく似ている。作品をこえて座敷には座敷の意匠、寝室には寝室の意匠……、といったいくつかの系列のようなものがあって、個々の作品ではそれらが組み合わされている、という読み方が吉田作品の理解には必要らしい。
たとえば蓬春画室は、蓬春のふたつの家の画室だけでなく、他の画家たちのために吉田が設計した複数のアトリエとともに、ひとつの連作的な系列をなしている。アトリエといえば一般に安定した北側採光が好まれるが、吉田設計の画室はいつも南面に構える。画家は身体を西に向けて座し、右利きの画家の左から光を入れるようにしているのだが、光が強いときは障子を引く。天井に届くほどの大判で、鴨居もなく、枠も見えず、格子も大間なので、均質で少し温かみのある白い発光面ができる。障子だけでなく、室内の線は絵の制作を邪魔するので、他の部屋よりもはるかに思い切って線が消される。
-

画室で制作する蓬春。昭和29年(1954)頃 提供:山口蓬春記念館
-

山口邸画室障子戸の欄間を開く -

欄間を閉じる
そして、蓬春画室のような15~18畳くらいの、高さのある箱状の広間は、吉田作品では「居間」「応接間」などにも現れることに気づく。吉田の名を世に広めた東京牛込の吉屋信子邸(1936年竣工)の「応接間」がその例だし、吉田が自信作と称した熱海の岩波別邸(1940年竣工)は筆者も機会を得て2度訪れたことがあるが、その「居間」は葉山の蓬春画室と共通点が多い。
この系列では、窓は箱の南面だけでなく少し東側にも回り込んでL字とする場合が多い。南東角から二方向へ建具を開き、戸袋に押し込める。L字形があんぐりと口を空くように開く。吉田の住宅では、廊下が南へ西へと雁行しながら進み、その南側に主たる室群、北側にバックヤード的な室群が並ぶことが多いが、すると前者についてはどの室も南東隅が突出したかたちになるだろう。ここが開口になるのだが、とりわけ雁行の一番先、南西端の部屋がとくにおおらかな立方体のような部屋とされ、これが「居間」「応接間」あるいは「画室」となる。こうした室を、ここでは〈広間の系列〉と呼ぶことにしよう。
〈座敷の系列〉
次に座敷を見てみよう。吉屋邸の座敷と山口邸の茶の間はたいへんよく似ている。共通するのは、折れ曲がる天井と、宙に浮く軽やかな鴨居である。
天井面が途中で折れるものを船底天井というが、ここでは座敷部分を平天井とし、そこに差し掛けられた庇や下屋に相当する部分の斜め天井をつなげ、ひとつの面が途中で折れたように扱うかたちで、ここでは差掛け天井と呼んでおく。天井板は、ふつう竿縁と呼ばれる細い棒状の材にのせるが、吉田の座敷では見附9~10ミリ程度と極細の竿縁を採用する。あまつさえこれを面取りして猿頰面とし、残された2~3ミリ程度の下面に漆を塗る。シャープで、かつ艶やかな色気が出る。こうした繊細な線の走る水平面が、座敷から縁へと折れて連続する。別々の天井面として段差を設けたのでは決して得られない空間の一体性が生まれる。
さらに、折れの位置にある欄間障子のレールを天井と面一に納め、また吊り下ろされた細い鉄の棒で鴨居を宙に浮かせる。こうすれば天井面は折れても切れない。長さ2間におよぶ薄い鴨居を支えるにはふつう柱のような吊束が必要で、小壁や板欄間が入ることも多いが、それら一切を消すことで、文字通り天井が連続し、空間は一体化される。以上のような手法を、吉田は料亭座敷でも繰り返し採用している。これを〈座敷の系列〉と呼ぼう。
拡張的な窓のあり方
ここで窓に注目しよう。日本では、窓は一般に複数の建具の重なりとして構成される。内側から、障子戸・ガラス戸・網戸・雨戸、という順序だ。これらを組み合わせることで、光、風、熱、虫、暴風雨などの環境因子を制御する。蓬春画室ではベランダを設けてこの4層構成から障子戸を少し離す。この意味で縁側とは窓の拡張に他ならないのだが、これは両邸の座敷でも同様であり、考えてみれば上屋・下屋(母屋・庇)の構成を持つほとんどの農家や町家などに共通してもいる。しかし、これに関連する意匠が、吉田の〈広間〉と〈座敷〉では特殊な傾向を持つ。
〈広間の系列〉では、まず天井が高く、そのうえ長押が消去されている。そのうえで南面の間口いっぱい、あるいは東面に回り込んだL字形の開口全体、そして床から天井までの高さいっぱいにわたって建具を拡大し、そして開け放とうと思えば建具そのものがすべて消えてしまうようにする。
対して〈座敷の系列〉では、天井高はふつうで、空間の水平性を維持し、差掛け天井をつくることで座敷と縁側を一体の流れのうちに統合するが、鴨居はあえて消さずに残し、吊束や小壁・板欄間を消すことで、奥行き方向に走るシャープな竿縁を持つ天井面が、上屋・下屋の境界を突き抜けていくような感覚を強める。
こうして、いわば拡張的な窓のありようが、吉田のふたつの系列では明らかに異質であることが理解される。
新日本文化の創出を目指す人々の相互批評
吉田のクライアントは、古径、蓬春、玉堂、秀峰といった日本画家たちに加え、書、文芸、出版、政治など、さまざまなジャンルで新日本文化の創出を目指す者たちのサークルそのものだった。彼らは有言にせよ無言にせよ、互いの仕事を批評し、支えあう関係にあっただろう。そうした相互批評のなかで、おおらかで、明るく、外の環境ともつながった、近代人らしい自然主義的な安心と創造・創発性を約束する空間イメージが共有されていったのではないか。それが吉田五十八の〈広間の系列〉であったと考えてみたい。
ちょうどル・コルビュジエが盟友の画家オザンファンのために設計したアトリエ(1922年)の、あの大きな格子状のガラス面によって外部に開いた明るい立方体的空間が、シトロアンからユニテまでの彼のリビング空間と共通する空間性を持っていたことを彷彿させる。
リノベーション作家としての吉田五十八
他方、〈座敷の系列〉について考えるうちにひとつのことに思い至った。吉屋邸はその全部、山口邸は主屋の大部分が、既存建物の改修であったという事実である。山口邸の茶の間は既存建物に対する増築、つまりこの部分は新たにつくられたものだが、ほとんど同じ意匠が、改修の吉屋邸座敷でもつくり出されているのだ。うかつであった。帰宅して砂川幸雄による吉田の評伝を手に取り、改修、改修と唱えながらページをめくっていくと、彼が実に多くの改修設計を行っていたこと、そしてその多くが未発表であることを知った(文献5)。
-

吉屋邸応接間の窓
少なくとも戦後の高度成長期まで、家屋は人から人へと渡って使われるものだった。いや人が家屋から家屋へと移って、手を入れて住むのが当然だった。吉田は建築家として山口や吉屋の物件探しを手伝ってもいた。吉田にしてみれば、施主が入手した建物の上屋・下屋をまたぐ関係を改変すれば〈座敷の系列〉の空間をつくり出せることが分かっていたはずだし、逆に〈広間の系列〉のおおらかな箱状の空間は新築でないと難しいとの判断もあっただろう。
論じ尽くされたかに見える吉田五十八の住宅設計について、まだ考えてみるべき視点がいくつかありそうなことが見えてきた。まずは吉田五十八をリノベーションの建築家として見直す作業を始めてみようかと思う。彼は伝統を学びそれを切り捨てたかもしれないが、他方では実在の建物をリノベしていたのである。
参考文献
1 『吉田五十八建築作品集』(吉田五十八著、目黒書店、1949)
2 『現代日本建築家全集 3 吉田五十八』(粟田勇監修、建築思潮研究所編、三一書房、1974)
3 『吉田五十八作品集 改訂版』(吉田五十八作品集編集委員会、新建築社、1980)村野藤吾「温故知新」、伊藤ていじ「吉田五十八」ほか所収
4 『住宅建築別冊17 数寄屋造りの詳細 吉田五十八研究」(野村加根夫監修、建築思潮研究所編、建築資料研究社、1985)鈴木博之「創業のひと 吉田五十八論」所収
5 『建築家吉田五十八』(砂川幸雄著、晶文社、1991)
6 『吉田五十八建築展』(東京藝術大学藝術資料館、吉田五十八建築展実行委員会編、藝術研究振興財団、1993)
7 『数寄屋の森 ―― 和風空間の見方・考え方』(中川武監修、中谷礼仁構成、丸善、1995)
8 『住宅建築』256号 1996年7月号 「時代を越えた住まい 1930~60年代 第4回 吉田五十八邸」(建築思潮研究所編、建築資料研究社)
9 『山口蓬春記念館 研究紀要』第二号(山口蓬春記念館、2004)
10 『建築家による「日本」のディテール:モダニズムによる伝統構法の解釈と再現』(青柳憲昌著、彰国社、2023)葉山の山口蓬春画室の詳細図を所収
山口蓬春記念館
住所:〒240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色2320
電話: 046-875-6094/Fax:046-875-6192/Web
吉屋信子記念館
住所:〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷一丁目3番6号/Web
青井哲人
1995年京都大学大学院工学研究科建築学専攻博士課程中退。神戸芸術工科大学助手、人間環境大学准教授などを経て、2008年より明治大学准教授、2017年より同教授。博士(工学)。
単著=『ヨコとタテの建築論──モダン・ヒューマンとしての私たちと建築をめぐる10講』(慶應義塾大学出版会、2023)、『彰化一九〇六 ── 一座城市被烙傷,而後自體再生的故事』(大家出版、台湾、2013)、『彰化一九〇六──市区改正が都市を動かす』(アセテート、2006)、『植民地神社と帝国日本』(吉川弘文館、2005)。共著=『戦後空間史──都市・建築・人間』(筑摩選書、2023)、『沖縄と琉球の建築|Timeless Landscapes 3』(millegraph、2022)、『地域文脈デザイン』(鹿島出版会、2022)、『世界建築史15講』(彰国社、2019)、『津波のあいだ、生きられた村』(鹿島出版会、2019/2021年度日本建築学会著作賞受賞)、『日本都市史・建築史事典』(丸善、 2018)ほか多数。