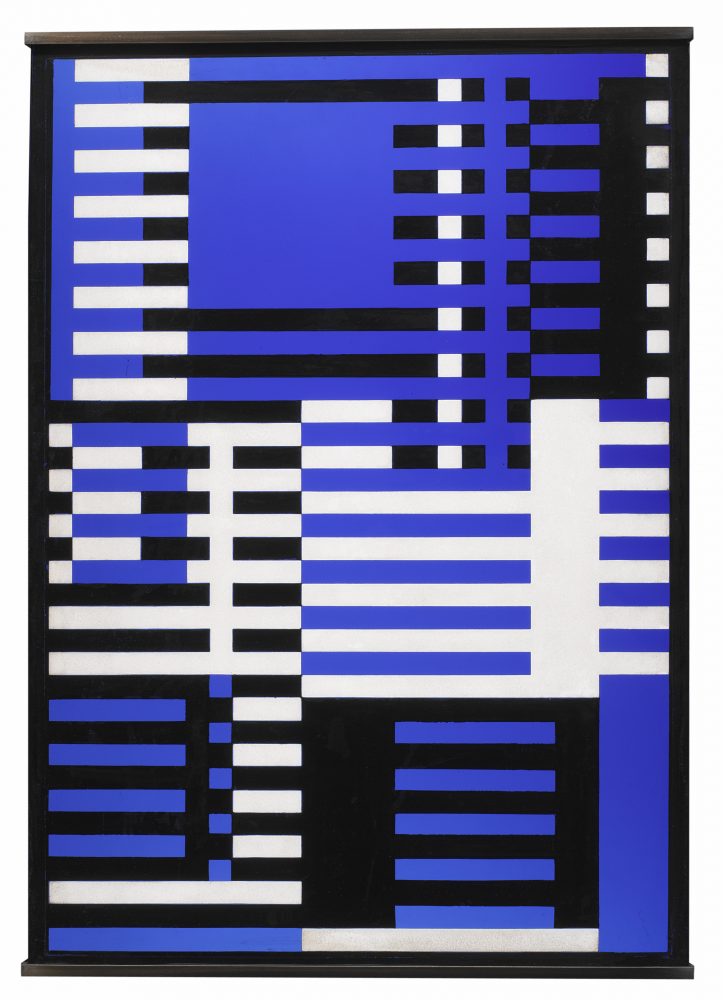作家・堀江敏幸 夢想の枠としての窓
19 Jul 2016
- Keywords
- Interview
- Literature
本を開いたときの感触は、自分の家の窓を開けたときのそれに似ている──多様な”窓”のすがたを切り取ったエッセイ集『戸惑う窓』の著者である作家・フランス文学者の堀江敏幸氏。幼少時代の窓にまつわる記憶の数々から、フランス留学時代の窓まで、その背景にある窓への思いを伺った。
──『戸惑う窓』を執筆された経緯や背景、思いについてお聞きします。文学作品だけではなく、絵画や写真、映画、建築、そして有窓性と呼ばれる細胞に関する用語など、かなり幅広く書かれていることにとても驚きました。
きっかけは、高級時計を扱う『クロノス』という雑誌からの、連載依頼でした。基本的に題材は自由だったのですが、いちおうこの雑誌の読者を想定に入れてということだったので、最初は、時計だから時間についてなにか書けばいいと、安易に考えていたんです。しかし、これはじつにありふれた、しかも奥深いテーマです。哲学的な話題になるのは避けたかった。
そのとき、ふと、自分がしていた腕時計に目をやったんです。どこにでもあるような安物ですが、3時と4時の間に日付の小さな窓がある。つまり、時計の中の窓です。これならなんとかなるかもしれない。リュウズやネジなど、時計の部品に光を当てたメカニックな話題でも楽しかったでしょうけれど、日付の窓をいわゆる窓に数えるなら、なにか書けるかもしれない。そこで、「窓をテーマにします」と先方に伝えたんですね。具体的に何をどう書くかは決めていませんでした。ただ、話の中に、なにか窓という言葉が登場してくれればいい。縛りはそれだけです。
──窓というテーマで書こうと思ったときに、なにか調べたことはありましたか。
事前に調べることはしませんでした。調べようがないんです。書き始めないと、自分でも何が出てくるのかわかりませんから。書いているうちに、「こういう話があったな」と、まずは記憶を頼りに書く。その途中で、あるいは後で調べることもありますが、それは確認作業にすぎません。記述に大きなまちがいがないかどうか、校閲みたいなものですね。幸い、全篇書き直しになるほどの思いちがいはありませんでしたが、そうではない部分での細かい修正はつねにありました。
たとえば引用文。使用するのは手持ちの版です。校閲の方が参照した本と、細部が異なっていることが何度かありました。同じ本でも、版を重ねる際、明らかな誤記や表記の手直しが行われている場合があるんです。書き手としては、訂正後の版を定本としたい。けれど、ひとりの読者としては、自分が身体に染み込ませた版の日本語を大事にしたい。読み手はだれしも、最初に読んだ本に対する思い入れがあるものです。アルミサッシに替えた後の窓より、昔の木枠の窓が好きだったのと同じように。本を開いたときの感触は、自分の家の窓を開けたときのそれに似ています。これはわがままですが、自由にさせていただきました。でも、題材に苦労することはありませんでした。窓という言葉は、文学では至るところに出てくる。詩でも小説でも、様々な場面で使われています。
──次に何を書こうかという場合、窓というキーワードで連想されていくわけですね。その幅が、とても広いと感じました。
そうですか(笑)。振れ幅が大きいから、博覧強記みたいに誤解されることがあるんですが、それはまちがいです。ピンポイントでしか物事を見ないから、逆に幅が広く見えるんでしょう。まずは好きな絵なり写真なりがあって、そこにたまたま窓がある、という順序です。作家の作品全体において窓がどのような位置を占めているかについては、書き始めてから考えることです。学問的に突きつめるとか、論文を書こうというわけではありませんから。
──それらの窓は、どのようなきっかけで先生の記憶に残っているのですか。
そのときの天気、時間、体調、周囲の人の数、あらゆることが景色の見方を変えてくれる。その変化の度合いが、身体に影響を与えるんです。よく言われるように、記憶と記録は異なります。記録にはない部分が、後から思い出すという作業を経て記憶になる。本に書いたのは、ある程度思い起こすことができた範囲内でのことです。
ぼくは昭和の生まれで、田舎で育ちましたから、鉄筋コンクリートのビルのカッチリした窓より、ふつうの日本家屋の窓に親しみがあるんです。雨戸を開けて、引き戸を開ける。平屋の一階なら、障子の張られた採光窓や箒の掃き出し口など、開口部がたくさんありました。そういう中で、いちばん心に残っているのは、小学校の教室の窓なんです。古い建物でしたから、窓枠はもちろん木で、立て付けが悪く、すきま風が入ってがたがた音を立てる。ガラスは少しいびつな、向こう側の景色がちょっとだけ歪むような年代ものが入っていました。授業中は、この窓から外ばかり見ていましたね。いま、自分が教師みたいなことをしていて学生と面と向きあって話をしていますが、まっすぐこちらを見ている人より、ボーッと外を見ている人の方が健全な気がするのはそのせいです (笑) 。
実際、小中学校の9年間で、授業の内容や先生の表情はあまり覚えていない。そのかわり、午後の気候の変化や、同じ窓から見える景色の揺れの方が内的な体験として身体に馴染んでいます。部分的に改装された教室の、新しい窓は好きではありませんでした。光の通り方が均一なんです。一枚の大ガラスではなく、格子窓の一つをフレームにして、その区切られたところから外をボーッと眺める。6つぐらいに仕切られている窓に太陽の光が当たると、時間とともに少しずつ陰影がずれていく。季節によっても、ちがいがあります。だから、窓と言われたときに想い浮かべるのは、素の空間というか、外から建物を見上げたときの窓ではなく、内側から外をまなざしている自分と、そういう自分を許容してくれる空間なんです。
──フランスで生活されていたと伺いました。異なる地域では、窓の扱い方など、文化がちがうと思います。実際に生活をして、影響を受けたもの、印象に残っていることはありますか。
若い頃に、3年間ほどパリに住んでいました。窓を開ける方向のちがいが印象に残っていますね。1970年代以後に建てられた近代建築はべつとして、フランスの窓はたいてい内側に引くかたちで開けます。それは映画を通して知っていたことではありますが、引き戸以外の窓は外側へ押し開けるイメージが頭の中に定着していたので、びっくりしたんです。それから、窓の造りが雑なことですね。おまけに規格サイズは一つもない。建物の壁の高さと幅にあわせて窓をつくるので、同一規格の窓を大量に発注するなんていうことがない。同じ部屋に窓が二つあると、左右で大きさがちがう。それを職人が、ひとつひとつ測定してつくるんです。
それから、ガラスがとても厚い。通りに面したところでも、窓を閉めるとシーンと音が消える。放送局のスタジオのドアを閉めたような静けさでした。音の消え方に、なんとも言えない特徴があるんです。石造りの建物で、密閉度が高いことも関係しているでしょう。沈黙じたいが石の音として聞こえてくる。窓の記憶が、目ではなく耳に残ります。手前に引いて開けていた窓を、ギューっと前に押しながら閉めて、完全に閉まった瞬間に音が消える。このとき、外の景色が内側に入って、同時に、窓が目ではなく耳に返還される。曖昧な言い方ですが、昼間なのに目が消えて耳だけになるという感じです。それに慣れてくると、今度は落ち着いて外が見られるようになる。
──連載を始める前後で、窓に対する印象が変わった、思うことが増えた、などエピソードがあれば教えてください。
とくに気をつけているわけではありませんが、「そういえばこういう窓もあったな」と、後で思い出すことはありました。いまも、雑多な読書の中で窓という言葉に出会うと、連載中の、締め切り前のことが蘇ります。これで補遺が書けるかなとよけいなことを考えたり。でも、そう考えた瞬間につまらなくなる。「素材に使えるな」と思ってストックしておくのは、好ましくない。むしろ、一旦忘れた方がいい。あらためて思い出せたら使えばいいし、忘れたらそのままでいいんです。
──「小学生の頃の学校の窓が印象に残っている」というお話がありましたが、記憶されていることの中で、思い返して嬉しかったこと、ご自身にとってプラスになったことを教えてください。
小学校の窓の経験はプラスになっていると思いますね。毎日通って、一番長く見ていた窓ですから。その同じ窓を、クラスの仲間たちもおそらく眺めていたでしょう。それでいて、みな、ちがう景色を、ちがう窓を見ていたはずなんです。窓は夢想の枠であり、手段なんですね。それは建築的な要素を超えた側面です。
──先生の窓に関する好きな文章、言葉はありますか。
特定の文章が好きということは、ありません。作品の中で、その一文が、言葉がどのように機能しているのかを見るしかありませんから。窓は内と外で、まったくべつものになります。とても美しい建築の、外側から見て美しい窓が、内側から見てもよいかといえば、必ずしもそうではない。
窓は単体ではなく、総合的に見るべきものでもある。実際の建築でも、それから自分の体の中でも。内側から見た景色を大事にしたい反面、外側から見ないとわからないこともあります。建物の一部というか、顔というか、構造そのものになっている場合もある。住んでいる人が中から見る窓は、訪ねて来た人が外から見た窓と一致していない。
どうしてここにつけたのか、不思議に思う窓もありますね。先ほどの普請中の話と重なりますが、建物は単体で建っているわけではないので、窓の魅力も、周囲の環境によって変化します。設計上すばらしい窓が、歩行者にとってもそうであるとはかぎらない。少し離れた通りから高い建物の窓を見上げたとき、季節によってはちょうどそこに強い夕陽が当たって、周囲の景色を消してしまうことがあります。惜しいと思いますね。設計者はたぶん、周辺を歩いていないんだと思います。
にもかかわらず、それは同じ窓なんです。窓は、一致しない二つの視点に耐えなければなりません。固定化されているようで固定化されていない。逆に言えば、「この窓」という、限定はありえないことになる。同じ一つの窓というものは、存在しないんです。この瞬間の、この時間の窓はあるけれど、翌日の窓の外は微妙に光が変わっているわけですから、同じ景色ではない。「行く川の流れは絶えずして」、ではありませんが窓は刻々と変化している。
最初に、有窓性という話も出ましたが、窓は建物という身体における皮膚呼吸の穴と同じです。そこを潰してしまうと病気になる。細心の注意が必要です。建築のことはまるでわかりませんが、建物の内部の、窓からの光の記憶は、ほとんど身体感覚なんですよ。村野藤吾設計の早稲田大学戸山キャンパスに、ぼくは卒業後20数年経って、戻って来ました。そのあいだ、一度も中に入っていないのに、足を踏み入れて、長い回廊に注ぐ窓からの光を見た瞬間、かつての動きのすべてを思い出したんです。あそこを右に曲がると自動販売機があり、その前にお手洗いがあるとか、直角型につながった建物のつなぎの部分に少し段差があるとか、そういうことが窓からの光量と影の塩梅 (あんばい) でスーッと思い出されてきた。「ああ、建物ってこういうものだ」とそのとき実感しました。身体の記憶と不可分なんです。この建物が取り壊されたら、窓だけでなく、身体の記憶が、過去が消える。そのような付き合い方をしていた窓は、やはり特権的なものかもしれません。
──とても記憶を大切にしていらして、今回はそれらを思い起こしながらのお話だったと思います。先に設定をなさらないというお話を最初にいただいたので、お聞きします。これから出会いたい窓はありますか。
「そのときに出会った窓」が、出会いたい窓になりますね。製作サイドからみれば、「こういう窓が欲しいと思ってつくりました」と言えるでしょうけれど、それはどうでもいいんです。これまで出会った窓と、窓をめぐる記憶をより豊かにしてくれるような窓であればいい。「この窓一つがあればいい」という窓ではなく、「この窓があるから他の窓も思い出せた」、そういう窓であれば。
震災の後、東北の復興を考える建築業界のシンポジウムのような場所に、招かれたことがあります。驚いたのは、建物をつくる側と道路をつくる側に、設計段階での接点がなにもないということでした。統一的な視点がないのです。役所の管轄もべつです。これが不思議でなりませんでした。既に街があって、その中の小さな区画でなにかをする際にも必要なのですから、ランドスケープ的な視点は不可欠なはずです。全体の中にどのような建物があり、どのように見えるか、どのような道路をひくかは、あわせて考えなければならない。「このような身体にしたいから、ここに血管を通そう」という順番ではなく、道路は道路で勝手にひいて、その後に造成工事が来る。それでは上手くいくはずはない。
すばらしい窓のある建物を造りたいと言っても、将来的に、その前に大きな建物ができてしまったら、元も子もなくなる。この一つの窓を活かすために、街全体を設計する。そういうことも大切でしょう。
ぼくはあまり長い作品を書きませんが、長編小説を中心に仕事をしている作家は、この場面のこの窓を活かすためには、他の場面を整えなければならないと考えて書き進めていると思います。あるいは、途中でその窓が危険にさらされそうになったら、全体を変化させる方向に持っていく。こうした配慮は、現実の世界でも必要だと思います。過程が大切なんです。建築においても。普請中のフェンスによって変容、変化する景観も、建築のうちですから。フェンスに花柄の絵のシールを貼ったり、過去の街の様子の写真を貼ったりして、その部分だけごまかすのは、どうかと思いますね。
──子どもの絵などもありますね。
色をもう少し周りの環境にあわせて塗り直すだけでも、印象はちがうはずです。
──先生は、お話されるとき、その背景もすべて含めた一つのことを話されています。統合感といいますか、それをつねに失わないようにしようという印象を受けます。
有名なお寺に行くとき、参道に馴染めないことがありますね。そうなると、あまり面白くない。たどり着くまでの気持ちの準備となる、アプローチにも気を遣って欲しいんです。読書でもそうです。全体を読み返したときに、前後の仕事、前後の文脈をあわせて、ある部分が、なぜ輝くのか、それを考えさせるような読みをしていきたい。細部はそのためにあるんですから。
──建築家が新しい作品をつくると発表する月刊などの専門雑誌があります。先生が、建築を訪ねていくと、どのような文章が出てくるのだろう、一読者としてぜひ読んでみたいと思いました。
書く、書かないはべつにして、楽しいでしょうね。写真を見るのは好きです。ただ、何通りかあります。でき上がったばかりの建物の建築写真はからっぽで、ちり一つ落ちていない。たしかに美しい。でも、窓は、家は、人が住み始めてから生きるんです。でき上がってすぐではなく、ある程度時間が経って、窓は窓になる。雑誌の建築写真の窓はピントが合い過ぎて、どうも苦手ですね。
──名建築と呼ばれる作品の窓や、建築家が力を入れてつくった住宅の窓を、先生がどのように書かれるか、とても興味があります。それは、建築家が自作を語るものとも、住んでいる人が語る感想ともきっとちがうものが出てくるのだろうと思います。
建物の周辺の変化を、建築家は拒むことはできません。建てた状況で、こういう景色だったからつくった窓というものが、周りの人の無理解によりどんどん潰されていく。30年経って、窓そのものの内化と言いますか、自分の中に入ってくるようにとても良い感じに古びたとしても、そこから見る景色があまりにもおぞましい場合、べつの諦めになってしまいます。
美しい建物、表から見れば美しい窓が並んでいますが、裏はぐちゃぐちゃということがあります。表の顔と裏の顔がまるでちがう。設備的な側面、排水、配管などが関係しているのでしょうけれど、映画のセットではありませんから、見えない裏の窓を粗雑にしていると、なにか全体もいいかげんな感じがしてしまうのです。裏から見たときの姿をも、大切にしたい。後ろ姿は、過程の重視につながります。「どうせ見えないところだから」という工事の仕方をしていると、隣の建物が壊されて剥き出しになったとき、壊される以上の幻滅を周囲に与える。背後にあった申し訳程度の窓は、このとき突然変化した光量にとまどう。窓にも、正しい呼吸をさせてあげたいと思いますね。
『戸惑う窓』
著者:堀江敏幸、 初版刊行日:2014年1月10日、サイズ:判型A5判、ページ数:216頁、出版社:中央公論新社、価格:2200円 (税別)
堀江 敏幸/Toshiyuki Horie
作家、フランス文学者。早稲田大学第一文学部フランス文学専修卒業後、東京大学大学院人文科学研究科フランス文学専攻博士課程単位取得退学。その間にパリ第3大学博士課程留学。1994年フランス留学経験を随筆風に綴った『郊外へ』が白水社の雑誌『ふらんす』に連載。1995年には単行本化され作家デビュー。2001年『熊の敷石』にて、第124回芥川龍之介賞受賞。2004年より明治大学理工学部教授、2007年早稲田大学文学学術院教授就任。2009年早稲田大学短歌会会長就任。