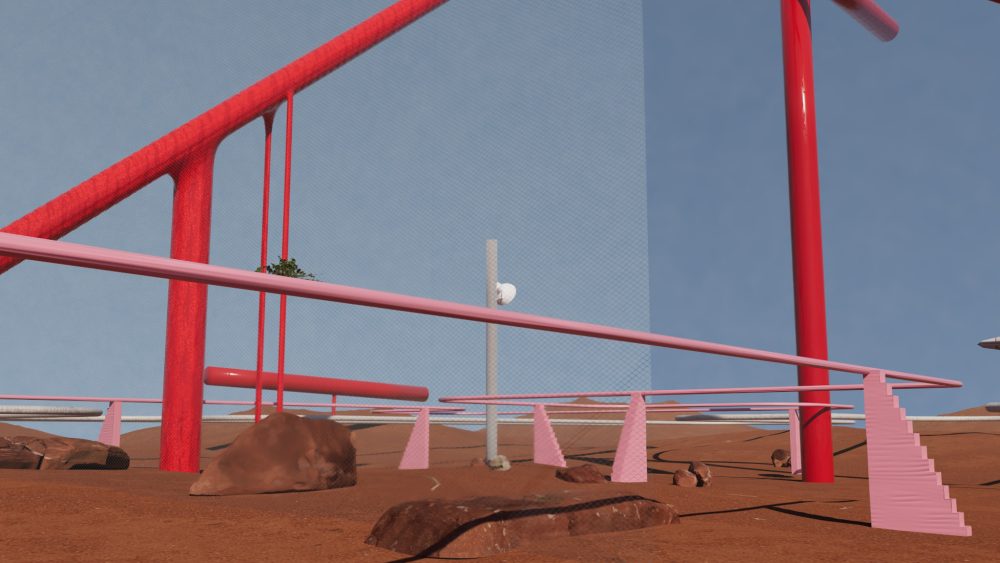自邸に宿る、建築家の精神性─
吉田研介《チキンハウス》の窓
08 May 2025
- Keywords
- Architecture
- Columns
- Essays
《チキンハウス》は、1975年に建てられた建築家・吉田研介氏の自邸だ。謙虚さを表す鶏小屋が名前の由来になっている。「工場より安く、教会のように爽やかに」というキャッチフレーズを掲げて事務所を構えていた吉田氏の自邸は、外壁にはスレート、屋根には三晃式折板を用いるなど安価な材料を駆使しつつ、安くとも爽やかな空間を実現する工夫を随所に凝らして設計された。独立初期のローコストハウスの実践は、以降、吉田氏に来る依頼の方向性を決定付け、その後も低予算の住宅を数多く手掛けることとなった。翻って現代、若手の建築家が手掛ける建築プロジェクトは低予算が当然となっている。その状況下でも設計の工夫で良い建築をつくろうと独自の活動を展開するIshimura + Neichiの2人が、《チキンハウス》に隠されたローコストハウスの精神に迫る。
ローコストハウスの合理と非合理
石村大輔(以下:石村) 東京都足立区で職人と事務所をシェアしながら設計事務所を構えているIshimura + Neichiの石村と申します。足立区には職人がたくさんいることから、設計と施工の距離を近づけるといった取り組みも行っています。私たち若手の建築家が今取り組んでいる仕事は、どれも予算が限られたなかでつくることが前提になっています。コストを極限まで下げないと新築を建てられない状況のなかで、それでもどうにか良い建築をつくりたいと思い、建物のつくり方から考え直していこうと、1945年以降のいわゆる戦後住宅をトレースしています。高い材料は使えないけれども手間を掛けて工夫することで、費用を抑えながらも良い建築にすることができるという考え方が、その頃からすでにあったことに驚かされ、今この時代の建築にも通じるアイデアが沢山眠っていることをトレースを通じて学んでいます。吉村順三さんや山口文象さんの住宅も参考にしているのですが、吉田さんが設計する住宅にもそうした工夫が詰まっていますよね。
-

正面外観。外壁には後にガルバリウム鋼板が張られた
吉田研介(以下:吉田) 僕もローコストハウスの精神は山口さんに教わりました。山口さんが設計された住宅を見学した際、「吉田くん、ローコストというのは鉛筆の削り方から節約しなきゃいけないぞ」と仰られたのをよく覚えています。山口さんが以前、太い梁に鴨居の溝を彫ってしまって、木の収縮で寸法が狂ってしまった経験から、ただ安くすればいいというものでもない、セオリーがあるものはなぜそうなっているのかをよく知っておかないといけないということも教訓として語っておられました。ただ、《チキンハウス》は正統なローコスト論に則ってつくられたものではなく、本当は違う選択をしたいのだけれど資金がないからこうせざるを得ないという、結果的にローコストになった住宅なんです。
たとえばリビングの窓は大きなフィックスガラスにするために、木の架構とは切り離して鉄骨で支えていますが、木枠との接合部には本来コーキングをしなくてはいけないところ、そのお金がありませんでした。竣工時にはそのままにしておいたので、隙間から外が見えていたんです。東海大学の設備の先生に、「夏はヒマワリが枯れて、冬はペンギンが風邪をひく家だ」なんて言われましたね。何年か経ってからようやく塞ぐことができたのですが、ローコストにするための工夫を凝らしたというわけではないんです。お金があればしなくてもいいはずの我慢もたくさん経験してきました。
根市拓(以下:根市) ただ、その我慢をしてでも実現したい空間があるわけですよね。
吉田 ええ。僕は性能を高めることにはあまり興味がないんです。一度吉田五十八さんの現場を見せていただいた際、養生のために普通は紙を使うところにベニヤを使っていて、養生にこんなに費用を掛けているのかと驚きました。美しく仕上げるために費用を掛けているわけだけれど、僕はそこには興味がもてないなと思いました。
根市 今のお話を聞いて、すごく納得ができました。吉田さんが設計された《清水邸》(1984)を書籍で拝見して、吉田さんのなかに2人の分裂した人格を感じたんです。中庭を囲むように建つ住宅ですが、屋根を折板でつくられていますよね。素材としてはローコストで、折板屋根はそれほど勾配を付ける必要もないので一見安くつくられているように見えるのだけど、実はとんでもないことをされている。中庭の中心に向かって、角度を変えて建つ各棟の折板屋根に勾配を付けた上で継いでいるから、折板の継ぎ目がすごく複雑になりますよね。
吉田 仰る通り、あれは無理をしていますね。ギザギザの形状を斜めに切ってしまったら、継ぐだけでは雨水の処理がうまくいくはずがないので、継ぎ目の下に雨樋を入れています。そういうことに対する手間は惜しまずにやってきました。
根市 その選択が吉田さんの建築をつくり上げているように思うんです。安くつくることが目的なのではなくて、空間的な質をきちんとつくり上げていますよね。安いだけでは終わらせない、必ずひと手間加えて意志のあるものに昇華しているなと感じます。
吉田 建築家にはその人それぞれの好みというか、やりたいことがあるわけじゃないですか。それが合理的か非合理的かと言えば、全く合理的ではない部分もある。でもそれが、建築をつくる意味であり、そういう合理性を超えたところに建築の質が生まれるように思います。その感性は、人に説明できるようなものではないのでしょうね。
根市 今の時代だと、コストも抑え性能も上げることが当たり前に求められるようになっています。たとえば窓でいえば、高断熱・高気密にするために自ずと既製品のサッシを使うことになり、そうするとカタログから製品を選ぶため、ある程度窓の開き方も限られてしまう。そのなかで、私たちとしては建物のつくり方から見直していくことで、選択肢を増やしていきたいと考えています。設計・施工が近い距離で協働して仕事をしていく進め方も、その試みの一環です。
吉田 僕が建築をはじめた頃は、建築家が設計も施工も受けるのはご法度という時代で、僕も竹中工務店に入社してから会社のやり方に違和感を覚えた部分もあって独立しました。その考えでずっと建築をつくってきましたが、最近になって設計・施工一体で建てられた住宅を拝見して考えを改めました。施工まで建築家が責任をもつことで、施主に説明できる範囲が増えるメリットはありますよね。ところでアルミサッシというのは1960年前後にビル用、住宅用と商品化が進みました。それまでは木サッシが当たり前で、スチールのサッシもありましたがあまり性能は良くありませんでした。
石村 吉田さんのデビューは1968年ですよね、アルミサッシが出てきてからしばらく経っていますが、サッシの選択についてはどのように考えていらっしゃったんでしょうか。
吉田 僕たち世代の建築家の基本姿勢は、既製品に頼らないことでした。その最たる例が石山修武ですね。当時、建材メーカーがどんどん新しい材料を出していて、世間はそちらに流れていくわけです。その方が便利なのは間違いないので。ただそれを使うのは嫌だった。良い悪いではなく、建築家はメーカーがつくったものに従ってはいけない、そういう時代精神がありました。山登りが趣味の人も、良い景色を見たければヘリコプターで山頂まで行けばいいのに、苦労をしてでも断崖を登りたいわけで、建築もその苦労にこそ醍醐味があるのだと思います。
三者三様の論理で選ばれた、《チキンハウス》の窓
根市 《チキンハウス》の窓は、3階はアルミサッシでつくられている一方で、1階と2階はリビングの大開口も、キッチンや個室のパタパタ窓もいずれも造作ですよね。それぞれの役割はどのように考えていたのでしょうか。
吉田 3階は両親の住居です。年齢のこともありとにかく性能が第一だということで、1、2階とは全く違う考え方でできています。とても木サッシなどは使えなくて、アルミサッシにせざるを得なかったため、下の階とは切り分けて上に載せ、外からも目立たないようにセットバックさせています。プランについても両親と大喧嘩をした末、渋々和室もつくりました。だからメディアにも発表当時は3階のプランは出しませんでした。
根市 立面をセットバックさせてはいるものの、帯状の構成にはきちんと沿うように気を使って立面をデザインされていますよね。1、2階で採用したパタパタ窓は、《チキンハウス》で初めて使用して、その後も度々使われていますが、どのような経緯で生まれたものなのでしょうか。
吉田 これはファサードの構成からきています。リビング側の窓を大きく見せるには、その隣はグリッドしかないという考えですね。当時いろいろなサッシが出てきていましたが、正方形の製品はないし、グリッドのプロポーションを考えると枠も5cmは必要だなというように、外観から決めていきました。また開閉させるためにはこの形式しかないので、パタパタ窓にしました。
根市 ルイス・カーンやフランク・ロイド・ライトは開き戸をデザインしていますが、吉田さんの場合は雨の多い日本の気候に対応できるように、庇としても機能するこの形にしたのかなと思っていました。
吉田 なるほど、確かにそれはあるのかもしれませんね。当時考えていたことを正確には思い出せないのですが。
根市 すりガラスはどのような考えで使われたのでしょうか。
吉田 キッチンや寝室に使うにあたって、透明なガラスにはしたくないからほかになにかないかというのが出発点です。模様の入った型ガラスが新しくできた頃で、流行っていたのですが、その流れに抵抗したいというのが1つ。それから、
根市 ミース・ファン・デル・ローエの《トゥーゲントハット邸》(1930)のエントランスには乳白色のガラスが使われていて、まるで光る壁のような存在感が印象的でした。《チキンハウス》の、このグリッドに嵌められたすりガラスは窓でもあり光の壁でもあるような、両義性を感じられて新鮮な印象を受けます。
吉田 ミースは僕の勝手な解釈では、頭のなかに空間やデザインのイメージがあって、それに合う材料を探してくる人なんじゃないかと思うんです。僕の場合はかなり理性的に、なぜこの材料を使うのかという理由を考えて選んでいるところがあります。安いからとか、メーカーがつくったものではないからとか、こんな使い方は今までなかっただろうとか、そういうことを優先していると思いますね。パタパタ窓には今では木が腐らないように鉄板を張ったり、窓枠に水切りを付けたりしていますが、当初はそれもできなかったんですよ。だから性能の面では悪い見本ですよ。
石村 ただ、悪い見本と言っても竣工から50年経った今でもきれいに残っていますし、なによりこの空間に入った瞬間の気持ちよさは、吉田さんが信じていた精神が間違っていなかったことを示しているように感じます。ご著書のなかで、メンテナンスについての言及も度々あったので、ご自身で施工された部分もあるのかなと思って見ていました。私はいま、マンションの一室をリノベーションして住んでいます。壁の石灰クリーム仕上げを、近所に住んでいた職人さんに教わりながら自分たちで行いました。素人の手癖が味わいになって、気に入っています。日々の生活はもちろん、犬を飼っていて壁が汚れることも多いので、自分で修復できることの良さを感じています。
吉田 仕上げを自分でやるのはすごいですね。建築家が自分で手を動かすこと自体はあり得る選択肢だと思いますが、僕の技量では到底考えられません。《チキンハウス》ではせいぜい2階へ上がる階段の手すりを後付けした際に自分でビス止めをした程度で、基本的なメンテナンスは職人さんにお願いしています。
石村 私も特別技術があるというわけではなく、コスト削減のためにできることをした結果としての自主施工ではあるのですが。《チキンハウス》は竣工後に少しずつ性能が上がっていったような住宅ですが、メンテナンスをするのは楽しいですか。
吉田 お金があれば楽しいですね。ようやく窓の隙間をコーキングで塞ぐことができたとか、モルタルで仕上げたままにしていた風呂場にタイルを張れたとか、だんだん完成に近づいていく喜びはありますよ。今も僕の部屋の構造用合板を張り替えたいなとか、まだまだやりたいことは残っています。
吉田研介/Kensuke Yoshida
1938年東京生まれ。建築家。東海大学名誉教授。1962年に早稲田大学理工学部建築学科を卒業後、竹中工務店設計部に入社。1964年に同社を退社後、早稲田大学大学院建設工学科修士課程に進み、1966年、同大学院修士課程修了。1968年より、吉田研介建築設計室(後に吉田設計室に改称)を開設、主宰する。1965年より、多摩美術大学非常勤講師に就任、1967年に東海大学建築学科専任講師に就任し、1986年より、同大学教授。2004年に退任後は同大学名誉教授。この間、早稲田大学建築学科非常勤講師としても教鞭をとる。主な作品に《ヴィラ・クーペ》(1971)、《チキンハウス(自邸)》(1975)、《M氏邸》(1987)、《シルバーグレイ》(1989)、《伊豆の別荘》(1996)、《都電脇の家》(2006)等。主な著書に『建築家への道』(TOTO出版、1997)、『建築設計課題のプレゼンテーションテクニック』(彰国社、新訂版:2003)、『住宅の仕事 白の数寄屋 吉田研介40年40作』(バナナブックス、2009)、『住宅半世紀/半生記/反省記』(アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、2011)等。
石村大輔/Daisuke Ishimura
1988年、東京都生まれ。2007-09年、測量会社勤務。2014年、東京理科大学工学部第二部建築学科卒業。2014-19年、駒田建築設計事務所勤務。2017年、Ishimura + Neichi 設立。日本工業大学、東京理科大学非常勤講師。
根市拓/Taku Neichi
1991年、神奈川県生まれ。2014年、東京都市大学工学部建築学科卒業。2015-16年、ミラー & マランタ 勤務。2017年、メンドリジオ建築アカデミー修了。同年、Ishimura + Neichi 設立。東京都市大学教育講師。