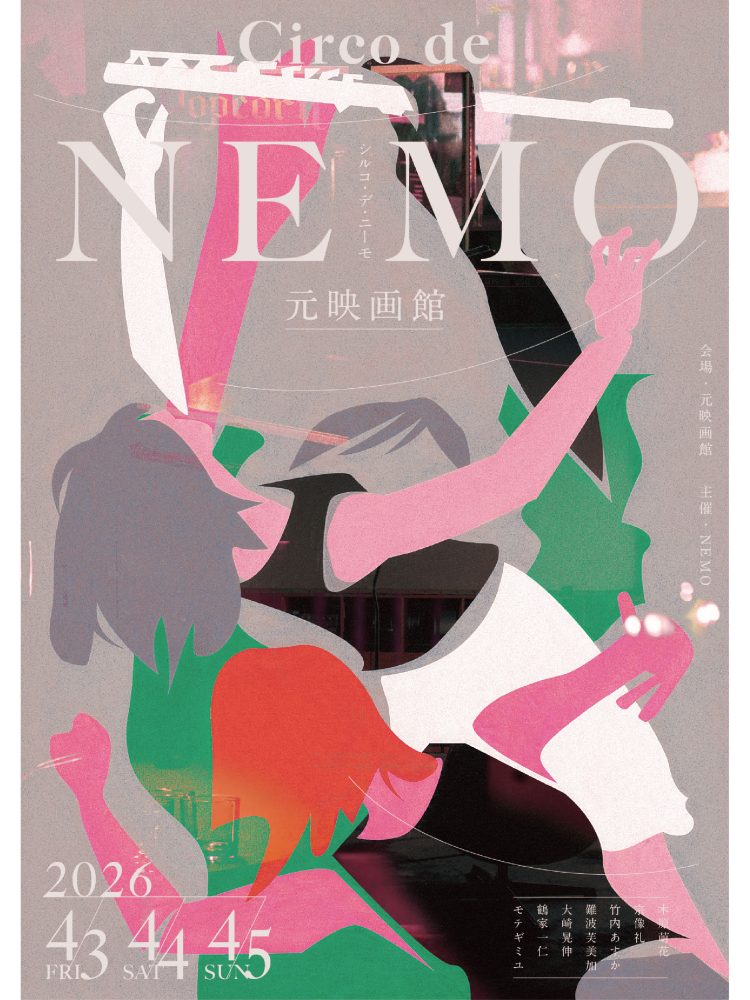クリスト&ガンテンバイン
31 Mar 2022
スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ)を卒業後、エマヌエル・クリストとクリストフ・ガンテンバインの二人によって結成された、クリスト&ガンテンバイン。1998年の設立以来《スイス国立博物館 改修・増築》や《バーゼル市立美術館 増築》、現在進行中の《チューリッヒ大学病院》まで多岐にわたるプロジェクトを手がける。さらにこうした実践と並行し、世界各地の都市における建築のタイポロジーを継続的に調査している。
初期作品《ガーデン・パビリオン》が佇むバーゼル近郊の緑豊かな庭園の一角で、貝島桃代氏、シモーナ・フェラーリ氏(ETHZ 建築のふるまい学研究室)が二人に話を聞いた。
──本日は窓とタイポロジーの関係から、お話を伺っていきたいと思います。タイポロジーの概念は、お二人の研究の中心であり、建築設計における重要なテーマのようですね。例えばチューリッヒの《スイス国立博物館》や《バーゼル市立美術館》では、増築というコンテクストのなかで、既存のタイポロジーと向き合う必要があったと思います。このような歴史の変遷による形態の変化は、私たちが窓の研究を進める上でも興味があります。多くの点で、窓の形態は技術の発展と密接に結びついており、時代とともにより大きなガラス面が実現可能になりました。しかし、窓は単なる技術の表現であるだけでなく、社会をあらわすものでもあります──タイポロジーも広く捉えればそうであるように。
スイス国立博物館のような事例では、ミュージアムのタイポロジーが今日の社会にとってどのような意味を持つのかという問題を扱ってこられましたが、お二人はその後、さらに大きなスケール、ほとんどインフラストラクチャーと言えるようなスケールにおいて、建築を探求されはじめている。その点で、キャリアの転機を迎えているようにも感じます。
クリストフ・ガンテンバイン(以下:ガンテンバイン) 私たちにとって、建築は必ず過去の建築から生まれます。先例との対比によって、歴史的視点で読み解くことができるものです。しかし建築は、新しい建物が既存の建物といかに関係するかという文脈とも関わっています。それは建物のボリュームや素材、施工方法といった、さまざまなレベルで関係していますが、根本的にはタイポロジーの問題です。建物をどのように構成するか、その基礎となる原則は何か、そしてその原則は周囲の環境とどのように関係しているか、ということです。
その意味では、スイス国立博物館とバーゼル市立美術館は、既存の建物と直接タイポロジカルに相関しているといってもよいでしょう。どちらのプロジェクトでも問題となったのは、施設での活動のための入れものとして機能させるため、新しい部分と古い部分をどのように構成するかでした。
バーゼル市立美術館の場合には、増築された新館はその内部のロジックや空間構成の点で、通りを隔て向こう側にある本館と類似(アナロジー)の関係にあります。地上階の入口、窓を介して都市空間と対話する2階の展示スペース、そしてより外部に対して閉じた性質を持ち、トップライトを設えた3階のスペースです。これら二つの建物は、ある意味で同じ「ファミリー」に属しているのです。
-

バーゼル市立美術館増築。新館は右奥に見える本館から道路を挟んで立つ
Kunstmuseum Basel, Basel, Switzerland, 2010-16 : ©︎Walter Mair
エマヌエル・クリスト(以下:クリスト) 増築と既存の間にこうした類似的関係があるのと並行して、そこには差別化または区別化のプロセスも働いています。新旧二つのプロジェクトの間には、常に交渉があるのです。スイス国立博物館では二つの幾何学形態がぶつかり合い、空間構成が非常に豊かになっています。基本的なタイポロジーの秩序はアンフィラードですが、同時に一種のコラージュとも言え、既存部分の多分に偶発的なコンビネーションによって、迷宮的な性質ももたらされている。ミュージアムの増築は、こうしたコラージュに付加するものですが、明らかに新たな空間のタイプを生み出してもいます。
-

改修されたスイス国立博物館既存部分内観
Swiss National Museum Renovation, Zurich, Switzerland, 2002-20 : ©︎Roman Keller -

先ほど「インフラストラクチャー的なスケール」とおっしゃったのは、興味深いですね。というのは、スイス国立博物館の窓をつくるときのシナリオは、まさにそういったものであったからです。スイスには、山中や地下に驚くべき工学技術による空間があります。私たちは増築部をほとんどインフラの一部のようにみなすことで、従来のギャラリーをはるかに超える、空間のダイナミクスとスケールにアプローチする方法が生まれました。ここでの窓は発電所のそれのように、むしろ技術的な開口部であり、非常に明確に内部と外部を接続している。しかし内部では、窓の高さなどはヒューマンスケールに設定されており、より打ち解けた雰囲気をもたらす空間になっています。
-

Swiss National Museum Extension, Zurich, Switzerland, 2000-16 : ©︎Walter Mair
──インフラという概念に言及したのは、それが特定の[空間的な]ニーズを満たす、誠実で直接的な手段のように感じたからでもあります。ミュージアムもずいぶん進化してきましたが、お二人は前例にとらわれず、現代社会がミュージアムの建物に求めているものを、躊躇することなくダイレクトに表現されている。ある意味で、タイポロジーは人と建築とのつながりの表明でもあると思うのです。
クリスト タイプとは一般的に受容されていて、さらには集団的に生み出されたソリューションですから、当然、社会に関係しています。この観点において、それは個人的な行為とは対極にあるようです。しかしあらゆるデザインは、たとえそれが特異なものであったにせよ、そのタイプの一つの解釈または反復として、一定のレベルの普遍性に到達しているとも言えるのです。
例えば、[19世紀に建てられた]既存のスイス国立博物館の窓は、単に外光を採り込むために存在していました。何かしらのものを展示するのがミュージアムの役目ですから。しかし、こうした窓は現代──20世紀後半の様式ということですが──のミュージアムのあり方には反しています。なぜなら、現代のミュージアムの窓は展示物を照らすのではなく、しばしばパノラマの屋上空間や大きなエントランス・ホワイエを付加することによって、来訪者のためにミュージアムの内と外の関係性を構築する役割を担っているからです。ギャラリー自体は閉ざされた箱であり、アートの体験は外の環境から完全に遮断されたものだというのが現代の考え方です。こうした20世紀後半から現在に至るミュージアムのタイプは、デンマークのルイジアナ現代美術館のように、壁を完全に取り除いて展示室を開放しようとする、後期モダニズムのモデルからの根本的なパラダイムシフトをも体現していると言えます。
-

Swiss National Museum Extension, Zurich, Switzerland, 2000-16 : ©︎Walter Mair
ガンテンバイン ミュージアム界隈では、窓はしばしば展示への集中を損なうもので、展示にまつわるナラティブから注意をそらし、問題を引き起こすと考えられています。しかし建築家としての私たちの見方は違います。ミュージアムの立地には大きな意味があるのです。スイス国立博物館──あるいはルーヴル美術館でも大英博物館でも構いませんが──を実際に訪れるのは重要で、ウェブサイトでの閲覧とはまったく違った感覚で展示物を見ることができる。展示物がその場所にどのように持ち込まれるかということもまた、物語の一部を構成するのです。
-

Swiss National Museum Extension, Zurich, Switzerland, 2000-16 : ©︎Walter Mair
クリスト ですから、作品の知覚が場所の知覚(作品を鑑賞する具体的な空間条件)と結びついているのが理想的です。これもまた先ほどの窓の問題と、窓とヒューマンスケールの扱い方、そして身体と空間の関係性の問題に帰結します。
──設計のプロセスにおいて、異なる窓のサイズやプロポーションについては、どのように調査されるのでしょうか?
クリスト スイス国立博物館では、窓を技術的な開放装置として、一部を主に空調のためのものと理解していました。そのため、壁をドリルでくりぬいて窓をつくろうと決めました。それが最も合理的で正確な方法だと思ったからです。窓の直径はドリルを使って実現可能な最大径、110 cmです。
-

Swiss National Museum Extension, Zurich, Switzerland, 2000-16 : ©︎Roman Keller
一方、バーゼル市立美術館では異なります。そこでは窓のプロポーションが問題でした。内と外が一緒になって少しずつ混ざり合っていくような瞬間を生み出したいと考えたのです。実際の経験をシミュレーションするために、 1/1 のモックアップをつくり、自らの身体を使って計測しました。
-

Kunstmuseum Basel, Basel, Switzerland, 2010-16 : ©︎Stefano Graziani
-

Kunstmuseum Basel, Basel, Switzerland, 2010-16 : ©︎Walter Mair
ガンテンバイン 窓は単独ではデザインできません。まず、プランのタイポロジーとは結びついていますから、空間や天井、床、ドアなど内部の他の要素との関係を考える必要がある。他方、窓のプロポーションは都市空間とも関係し、外から見た建物の表情を決定づけるものでもあります。
──通常、窓のデザインにはある程度技術的な側面が伴いますが、バーゼル市立美術館の空間を体験すると、窓とその技術的な要素が消えていくような印象を受けます。開口部が非常に直接的に外へと導かれるように認識されるのです……。
-

Kunstmuseum Basel, Basel, Switzerland, 2010-16 : ©︎Stefano Graziani
クリスト 面白い発想ですね。おそらくそれは「廃墟」という概念──ほとんど匿名的な、混じり気のない空間構造──につながっているのだと思います。今クリストフが言ったように、窓は建物の相貌を決定づける「目」のようなものです。しかし私たちの建築において、主要な存在は壁です。窓という建築的要素は非常に縮少され、廃墟のようにほとんど存在しないのです。
ガンテンバイン 私たちには、窓の技術が建物の表情に与える影響に対する敬意(畏れさえも)があります。窓の造りは建築の極めて重要な部分だからです。オスマンのパリ改造や19世紀ドイツの街区の窓など、窓の細部を見ればその街の相貌がわかるでしょう。予算が控えめの小さなプロジェクトであれば、技術的な制約のなかでも美しい窓をつくることは可能ですが、大きなスケールの仕事になると、高い経済的制約のもとで技術的な側面がコントロールできなくなり、建物の表情を支配されてしまう危険性があるのです。
クリスト ですから私たちの作品において、窓は根源的な存在であると同時に、不在であるという読み方もできるでしょう。この設計戦略は、私たちのごく初期のプロジェクトである、《アーレスハイムの住宅増築(ガーデン・エクステンション)》から始まりました。これはスイス国立博物館増築の小規模の予行演習と捉えられるかもしれません。ここではボリュームの物理的な存在感は非常に洗練されていますが、窓はそこから切り取られた単なる開口部です。ここから、ガーデン・パビリオン/廃墟という大きなアイデアが漠然と生まれてきたのです。
-

アーレスハイムの住宅増築(ガーデン・エクステンション)外観。増築部は既存の1920年代のヴィラから、広大な庭園の内部へとアクセスする通路(ガーデン・ルーム)として設計された
Garden Extension Arlesheim, Arlesheim, Switzerland, 2001-02 : ©︎Roman Keller
-

内装には植物模様の壁紙が使用されている
Garden Extension Arlesheim, Arlesheim, Switzerland, 2001-02 : ©︎Roman Keller
さて、これが抽象化のための戦略か否かを議論してみるのも面白いでしょう──最終的にはアカデミックな議論になってくるかもしれませんが。というのも私たちは、窓の抽象化という観点からは考えていないからです。例えば、スイス国立博物館増築のケースでは、そこに高度な具体性と物体性があります。壁の切り抜かれた開口部からはテラゾーの切り口や、それがどのようにして磨かれたかがわかりますし、真鍮のフレームを持つ窓もあります。古代の建築のように、素材の存在感を讃えているのです。
バーゼル市立美術館の場合には、窓枠が目立たないかわりに、シャッターがあります。シャッターが物理的な存在感を持ち、開けるとファサードから突き出したシャッターの影が落ちる。このアイデアをとても気に入っています。もちろん、シャッターを壁の中に組み込んで隠すこともできますが、そうはしませんでした。私たちにとって重要なのは、抽象性を追求するのではなく、建築の基本的な形態に要素を落とし込むことなのです。
-

Kunstmuseum Basel, Basel, Switzerland, 2010-16 : ©︎Stefano Graziani
ガンテンバイン 特に窓のデザインは、壁の物体性の問題に関わります。露わになる断面によって、窓は建物の造りや素材の実体について教えてくれる。何も隠すことはできないのです。
──最後に、現在進行中の《チューリッヒ大学病院》新館の設計についてお伺いします。今日の病院の設計には技術的要素が非常に大きく、これもまたある種のインフラストラクチャーを構成していますが、しかし同時にヒューマンスケールへの配慮も必要です。病院は社会的な文脈と密接に結びついた施設でもあるため、ここでもタイポロジーの問題が非常に重要な意味を持ってくる。例えば、病院はかつての多くの患者を収容する大部屋から、個室を中心とした施設というあり方へと移行しています。
クリスト 確かにこのプロジェクトの課題は、この巨大なテクノロジーの機械をどのように管理し、人間と都市の両方のスケールに関係させつつ、都市の一部にするかです。この点において、チューリッヒ大学病院は、特殊なケースです。他のヨーロッパ諸国では医療費が高騰しており、都市部の病院ではなく郊外の大規模な病院施設へと移行しつつありますが、一方、チューリッヒでは病院というものが依然として、都市の再生に何らかの役割を果たせるだろうと考えられているからです。
ガンテンバイン ここでは患者の個室がプログラムの中心的な要素であり(集中治療用の2フロアを含め)合計5階分の構造を占めています。しかし、窓は個室という一つの空間タイプに特化して関係を持つものではありません。窓は救命救急室から医務室など、大きく異なる種類の空間を包む、実にさまざまなプログラムと関わることになります。
フロアプランは、オフィスビルと同じように、間仕切り壁を自由に移動させられます。フレキシビリティーを重視した結果ですが、これはある意味ではタイポロジーに反するものです。ここでの窓は、建物の技術的な皮膚(スキン)の一部としてつくられており、[流動的な性格を持つ内部空間とは結びつきが弱いため]より独立した要素になっています。都市の一部としての建物と内部空間、それら両方の様相に対応するものとして窓を考えるとき、この建物において後者の側面は副次的なレベルでしか現れません。
-

Zurich University Hospital USZ, Zurich, Switzerland, 2019-28 : ©︎Christ & Gantenbein
──写真を見ると、ファサードにグリーンが使われているようです。これは先ほどお話しにあったような、過剰な技術的表現を目立たなくするための手段なのでしょうか?
クリスト まず、このファサードのグリーンは建築的要素を隠すものではありません。空間的な奥行きを持たせ、複雑さや豊かさを感じさせようとするものです。ちょうど今この窓から見えるように、一部が植物で囲まれた部屋に座ってみると、空間の感じ方にただちに影響があることに気づくでしょう。外部に対して、まったく異なる知覚をもたらすのです。これは、先ほどのヒューマンスケールの問題にも通じるところがあります。
もう一つ、癒しの環境という考え方があります。植物の存在が人間の健康に寄与することは、よく知られていますね。植物は日よけにもなりますし、理想的な微気候をつくり出すこともできる。かつての病院では、建物が庭に囲まれていたため、こうした要素を取り入れるのは難しくありませんでしたが、現在の大規模な病院では、そう簡単ではありません。
-

インタビューはガーデン・パヴィリオンの建つヴィラの敷地にて行われた
©︎ Chair of Architectural Behaviorology
さらに、既存のコンテクストとプロジェクトの関係性をどう定義するかという問題もあります。ミュージアムではないにせよ、今回のプロジェクトも結局のところ増築だからです。1940年代後半に建てられたチューリッヒ大学病院では、植物を育てるといった自然のエレメントが組み合わされ、バルコニーやロッジアなどによる外部とのつながりがありました。現在では安全上の理由からバルコニーは認められていませんが、私たちはこうした自然のエレメントの存在を改めて強調したいと考えています。 すべての部屋がこのように外とつながり、自然とふれあい、日々のリズムや季節の移り変わりを感じられるようにしたいのです。
どのように建築が先例を参考にするか、という冒頭のクリストフの言葉に戻りますが、これは病院の設計にも当てはまります。私たちは、サナトリウムやベランダ、さらには内部のロッジアなどの要素を、テクノロジーを駆使したハイエンドな複合ビルのコンテクストに取り入れたいと考えています。これは抽象化に対するステートメントとも言えるかもしれません。私たちは、密閉され、効率に優れた、単なる箱以上の何かをつくりたいのです。
──グリーンがあることで、病院建築にさまざまなスケールやレイヤーを持ち込むことができる。それはインフラとも言えるし、庭とも言えるでしょう。
クリスト 「庭」とおっしゃったのは、まさにその通りです。私たちは、植物の成長を組み込むことができる金属による構造システムをつくろうとしています。コントロールせず、自然に任せて成長させるものではありませんが、とはいえロマンティックな部分はあるでしょう。ここで重要なのは、窓のある本体と、柱や梁などの構造システムをレイヤリングさせるというロジックです。ここでは自然が建築の要素を覆い隠しているのではなく、自然が[建築の一要素として]その上に層を成すことで形態が生み出されているのです。これは非常に美しいことです。ある意味で、先ほどの廃墟の概念にもつながってきます。例えば、ミラノには典型的なノヴェチェント様式の住宅がありますが、そこでは建築の大部分がほとんど完全に植物に覆われていながらも、この《ガーデン・パビリオン》のように、窓が独自の存在感を放っています。形態は建築によって定義され、自由に成長する自然によって定義されるのではない。それが建築と自然、それぞれの形態による興味深く多義的な対話を生み出すのです。
-

Garden Pavilion, Basel, Switzerland, 2011-12 : ©︎Walter Mair
-

Garden Pavilion, Basel, Switzerland, 2011-12 : ©︎Walter Mair
──窓の要素をほとんど廃墟のような形態にまで還元していくのが、お二人のデザインに多くみられるテーマです。これは窓の技術的な表現に対する抵抗のようでもあります。しかしなぜ、このようなアプローチが昨今重要であるとお考えですか? つまり、現代社会にとって廃墟の価値とは何でしょうか?
ガンテンバイン 未来にありうる建物というアイデア──つまり建築の一時性を主題化することよりも、私たちが廃墟に興味を惹かれるのは、それが建築をそのタイポロジカルな性質、すなわち空間構造にまで還元していく点です。その空間構造によって、建物がどのように構成されるか、都市的な文脈にどう位置づけられるか、どういった用途に用いられるかが決まります。そのような点で、内と外を関係づける窓は、決定的に重要な役割を果たします。ですから私たちのプロジェクトにおいて、窓は一つの事象として重要であり、その造り──例えば素材や窓割り──は、厄介なものとして捉えられるのです。それらが開口部の持つ本質的な事象の邪魔をし、弱めてしまう恐れがあるからです。ですから私たちにとって、家を廃墟、すなわち混じり気のない空間構造として捉えることは、ほとんど匿名で、個人的な特徴のない、ひっそりと目立たない建築、そして純粋かつ完全な状態という概念へと結びついているのです。
-

©Lukas Wassmann
エマニュエル・クリスト/Emanuel Christ
1970年生まれ。スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ)、スイス連邦工科大学ローザンヌ校、およびベルリン芸術大学で建築を学ぶ。クリストフ・ガンテンバインとともに、1998年にバーゼルでクリスト&ガンテンバインを立ち上げ、世界各地で数多くの賞を受賞。主な作品にスイス国立博物館、バーゼル市立美術館 改修・増築(ともに2016年)がある。バーゼル造形芸術専門学校(2002年–2003年)、スイス連邦工科大学バーゼルスタジオ(2000年–2005年)、ロバートゴードン大学アバディーン校(2005年)、オスロ建築デザイン大学(2008年)、メンドリジオ建築アカデミー(2006年、2009年)、ETHZ(2010年–2015年)、およびハーバード大学デザイン大学院(2015年–2017年)で教鞭を執る。2018年にはETHZにて建築学およびデザインの正教授、2021年にはハーバード大学デザイン大学院にて、丹下健三記念デザイン批評家(Kenzo Tange Design Critic)に任命されている。
クリストフ・ガンテンバイン/Christoph Gantenbein
1971年生まれ。スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ)で建築を学ぶ。エマニュエル・クリストとともに、1998年にバーゼルでクリスト&ガンテンバインを立ち上げる。主な作品にスイス国立博物館、バーゼル市立美術館 改修・増築(ともに2016年)がある。バーゼル造形芸術専門学校(2002年–2003年)、メンドリジオ建築アカデミー(2004年、2006年、2009年)、オスロ建築デザイン大学(2008年)、ETHZ(2010年–2015年)、およびハーバード大学デザイン大学院(2015年–2017年)で教鞭を執る。2008年から2017年まで、スイスエンジニア・建築家協会バーゼル支部(SIA Basel)の管理取締役会のメンバーを務める。2018年にはETHZにて建築学およびデザインの正教授、2021年にはハーバード大学デザイン大学院にて、丹下健三記念デザイン批評家(Kenzo Tange Design Critic)に任命されている。
貝島桃代/Momoyo Kaijima
2017年よりスイス連邦工科大学チューリッヒ校「建築のふるまい学」教授。日本女子大学卒業後、1992年に塚本由晴とアトリエ・ワンを設立し、2000年に東京工業大学大学院博士課程満期退学。2001年より筑波大学講師、2009年より筑波大学准教授。ハーヴァード大学デザイン大学院(GSD)(2003、2016)、ライス大学(2014-15)、デルフト工科大学(2015-16)、コロンビア大学(2017)にて教鞭を執る。住宅、公共建築、駅前広場の設計に携わるかたわら、精力的に都市調査を進め、著書『メイド・イン・トーキョー』、『ペット・アーキテクチャー・ガイドブック』にまとめる。第16回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館キュレーター。
シモーナ・フェラーリ/Simona Ferrari
建築家・アーティスト。2017年よりスイス連邦工科大学チューリッヒ校「建築のふるまい学」研究助手として指導にあたる。ミラノ工科大学、ウィーン工科大学、東京工業大学(外国人特別研究員)にて建築を学ぶ。2014年から17年までアトリエ・ワンの国外プロジェクトを担当。チューリッヒ芸術大学美術学修士課程在学。「ユーロパン 15」(2019)コンペ勝利にともない、現在は伊ヴェルバニアのアセターティ社工場跡にてプロジェクト(メタクシア・マルカキと共同)を進行中。
Top image: Swiss National Museum Extension, Zurich, Switzerland, 2000-16 : ©︎Walter Mair