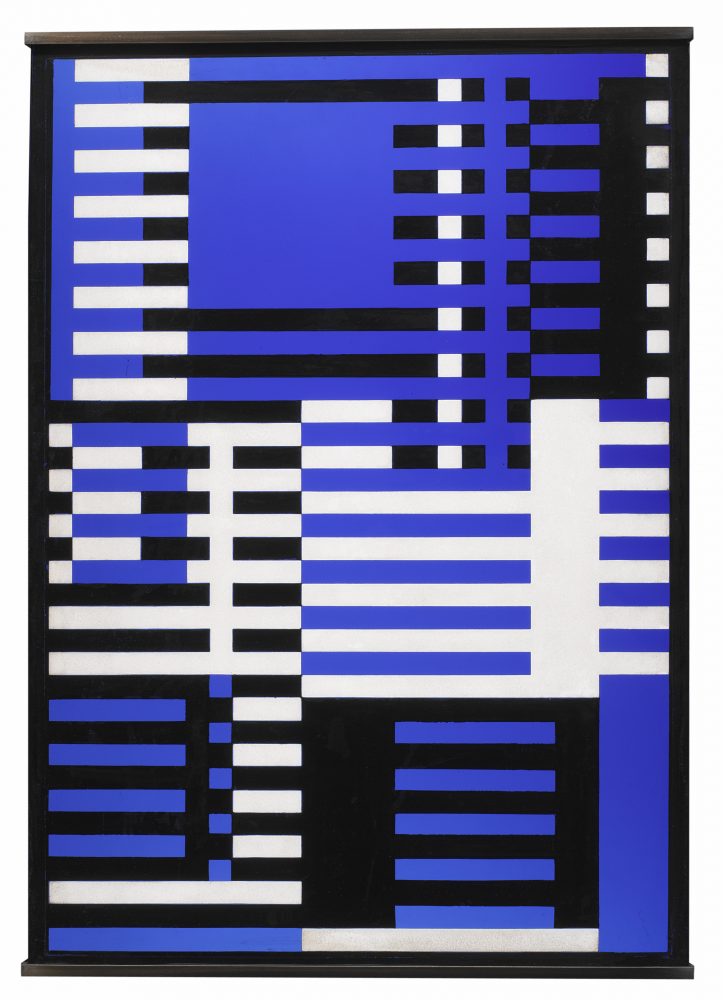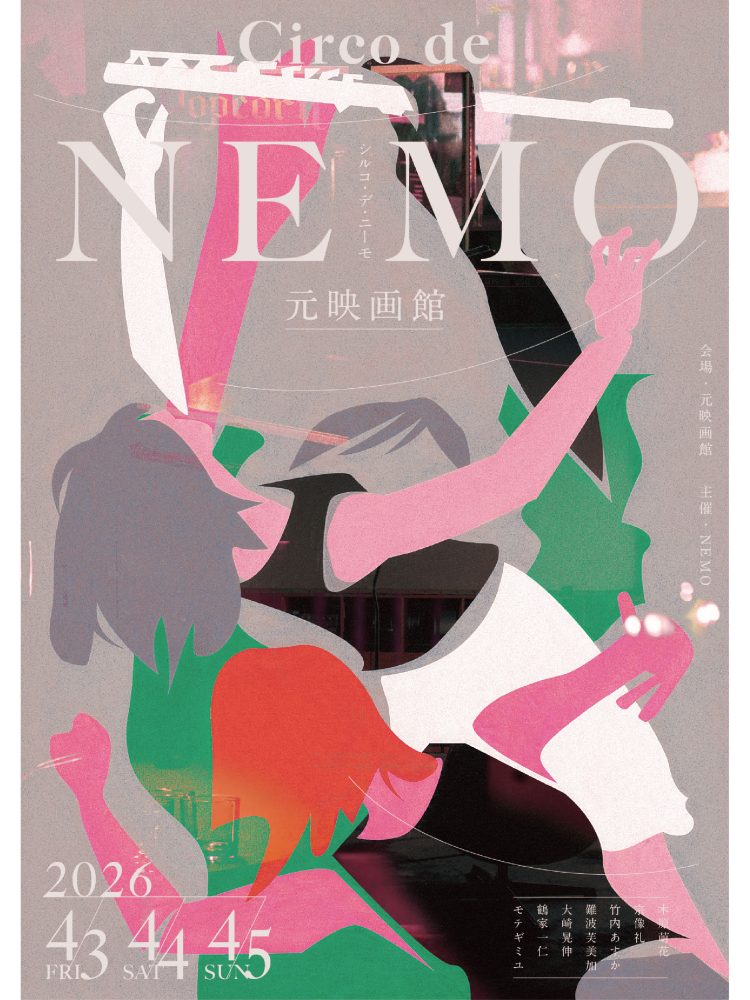安藤桃子 窓を描く監督
22 Jun 2018
- Keywords
- Interview
2009年に『カケラ』で監督デビューを果たし、その5年後に公開された『0.5ミリ』では第18回上海国際映画祭アジア新人賞など、数々の賞を受賞し、国内外で高い評価を得た安藤桃子監督。映画作りでは常にリアリティを追求してきたという彼女の作品には、驚くほど多くの「窓による人物描写」が登場する。
今回のインタビューでは、映画『ウタモノガタリ』(6月22日より全国ロードショー)のために4年ぶりにメガホンを取った安藤監督に、映画における窓、そしてフレーミングの重要性を語っていただいた。
──これまでに安藤監督は、小説を書いたり、リトグラフ展を開催するなど、映画の他にも幅広い分野で活躍されて来ましたが、いつ頃からこうした活動を始めたのですか。
安藤桃子(以下:安藤) 3歳~4歳の頃から、父(俳優・奥田瑛二)と一緒に絵を描いていたこともあり、「絵を描く人になりたい」と思ったのが始まりでした。その後、大学でペインティングを学び、今では映画を作っていますが、映画も1秒24コマのフィルムで撮影された「絵」が連なって構成されているものなので、制作の感覚は絵を描いていた頃からあまり変わっていません。それに、脚本を書くときや撮影に入るときは、映像作品よりも、写真集や写真展からインスピレーションを得ることが多いです。
──映画製作の道に進もうと決めたきっかけについて教えてください。
安藤 2001年に父が『少女』(2001)という作品で初監督を務めたときのことです。当時芸大の准教授だった日比野克彦さん(現東京藝術大学美術学部先端芸術表現科教授)が美術を担当していた影響から、大勢の美大生が制作に参加していて、美大に入学した直後だった私も、休暇を利用して撮影に関わらせていただくことになりました。私自身、映画が身近な家庭環境で育ってはいましたが、制作に携わるのは初めてでした。
1人で地道に絵を描くのとは違って、映画の現場では大の大人が一丸となって、命がけで1つの作品を作り上げます。その職人気質と大変な制作過程に、雷に打たれたかのような衝撃を受けました。特に映画監督という仕事には、多くの決断が求められます。例えば天気やロケーションなど、誰にもコントロールできない問題が撮影の障壁となってくるので、腹をくくるタイミングが重要になります。それなのに映画では、実在しない人々や世界があたかも存在しているかのように見せなくてはならないので、1本作るのは死に物狂いです。
──様々な障壁があるなかで、ロケハンやセット作りは、どのように進めているのですか。
安藤 セットは組んでおらず、全てロケで撮影しています。空き家だったり、人が住んでいる家をロケハンで見つけて借りて、美術部と一緒に考えながら作り込んでいきます。ロケハンの一番面白い部分は、自分が想像していた場所と、現実の世界が出会うことで、自分の頭の世界観が広がっていくことです。そこに役者さんやスタッフが入っていくことで、自分のなかに収まっていた世界が無限大に広がっていきます。「刑事は足で稼ぐ」と言いますが、映画監督も足が大切です。私は、誰も行かないような裏道にも率先して入ってロケハンをするので、地元の人より土地に詳しくなることもあります。
──実在の建造物を使用しているせいか、安藤監督の空間描写からは圧倒的なリアリティを感じます。なかには窓が特徴的に描かれているカットも数多く登場しますが、こうしたカットは意識的に取り入れているものなのでしょうか。
安藤 『カケラ』(2009)の公開後に、「この監督は窓を描く監督だ」という批評をいただいたことがあります。それまではあまり意識していなかったのですが、その時にはじめて自分が窓に深い思い入れを持っていることに気づきました。
例えば、窓が絵の中にあるだけで、内と外が表現できますよね。西洋哲学では、まず外側があり、そのなかに内側(自己)が存在する、という考え方が一般的ですが、仏教思想では内側に全てが存在するという考え方をすることがあります。日本人である私にとって、室内の窓を一つ切り取るということは、登場人物の内面を一度に表現するということに繋がるんだと思います。
──『カケラ』は、主人公・北川はるが部屋の窓を全開にして掃除をしているシーンで幕を閉じます。やはりここでも、意識的に窓を構図に取り込んでいるのでしょうか。
安藤 はるの部屋の窓の開け閉めに関しては、全て厳密に決めていました。「このシーンは窓を閉め切る。ラストシーンは全開。最後に窓の外から彼女の顔を映す」、というようなこだわりがあったので、カーテンの幅を毎回美術部に伝えて、漏れなく脚本に書き出しました。「これは全部閉める。これは3分の1」という具合に。ラストでは、全体にすがすがしさを持たせるために窓を全て開けました。
-

映画「カケラ」(2009)のラストシーンで部屋の窓を全開にして掃除をするハル(満島ひかり演)
──『0.5ミリ』では、ホームヘルパーの職を失った主人公・山岸サワが町で出会うワケあり老人の家を転々としていく姿が描かれていますが、そのなかでも窓が印象的なシーンがいくつか見受けられました。特に頑固者のお年寄り、真壁義男の自宅で展開されるシーンでは、障子から洋風のものまで色々な種類の窓が用いられていますね。
安藤 そうなんです。例えば、妻・静江の部屋では、西洋の窓とレースや花柄のカーテンを組み合わせることで、教会のような明かりが差す空間を演出しています。窓は完全に閉めていますが、外から差すやわらかな光によって静江の尊さを表現しようとしています。そして、そんな彼女の姿を窓の外から義男が見つめるカットでは、「内と外」、つまりは義男と静江の心の距離感を表そうとしています。
-

静江(草笛光子演)の枕元は、窓から差すやさしい光で照らされている
-

窓の向こう側から静江を見つめる義男(津川雅彦演)
また、義男とサワの別れのカットでは、『カケラ』のラストシーンと同様に窓を全開にしました。これは義男が戦時中の体験をサワに明かすカットでもあり、彼とサワの開いた心のコミュニケーションを表現したかったんです。
-

サワに戦時中の体験を語る義男
──他にも、『0.5ミリ』のなかで窓の映し方に思い入れがあるシーンがあれば教えてください。
安藤 私の中では、サワが街で出会ったワケあり老人・茂のために、朝から台所に立ち、味噌汁を作っているカットがとても重要でした。ここでは、窓を少し開けて空気を入れ替えて、味噌汁の匂いと湯気が部屋にこもらないようにするサワの心遣いを表しています。
蒸気や湯気が漏れてる家って、すごく幸せじゃないですか。住宅街を歩いてても、家のなかにいるような気持ちになるというか。なのでこのシーンでは窓を少しだけ開けて、味噌汁の匂いを画面に映りもしない外に向けて、逃がすことにしたんです。そうすることで生活感を出すだけでなく、一人暮らしのおじいさんの家に、火を使って料理をする女性が現れた温かな変化の瞬間というものを描こうとしました。
-

茂のために朝食を作る、おしかけホームヘルパーの山岸サワ(安藤サクラ演)
──窓がほんの少し開いているだけなのに、そこから主人公の人間らしさがにじみ出てきます。
安藤 きちんとしている人なら、朝起きて料理をしようと思ったら、冬でもまず窓を少し開けて、空気を入れ替えてからキッチンに立ちますよね。
やはり、窓を開けるか、閉めるか、というのは常に気にしています。開けるか、閉めるかで、ひとつのシーンに登場する主人公や登場人物の心の内が非常に異なって表現されます。もしかすると窓を意識してない映画監督はいないかもしれないですね。私にとって、窓とカーテンは意識的に意味を持せなくてもよいほど、当たり前の存在です。
そして当然のことですが、窓は明かり取りですよね。映画の中で光と影ということにおいて、窓をどう扱うかは絵としてとても重要なことです。部屋に窓がなかったら、ただの箱になってしまいます。
──安藤監督が制作に携わっている、映画『ウタモノガタリ-CINEMA FIGHTERS project』(2018)について教えていただけますか。
安藤 6人の監督が6本の短編を撮るという内容で、私はこのなかで『アエイオウ』という作品を監督しました。今回の作品は、私が『0.5ミリ』で出会ってから生活の拠点にしている高知で撮影しました。撮影現場となったのは高知県南西部の土佐清水という黒潮のぶつかる場所で、世界で一番、魚の種類が多い場所とも言われるような自然豊かな場所です。土佐清水にたどり着く魚たちは、荒波を生き抜いているのでとんでもない筋力を付けているし、それを食べて生活している人たちも活気に満ち溢れています。他にも、木のうねり方が変わっていたり、人工物がほとんどない浜が続いていたり、まるで自然の原点のような場所なんです。
今回の作品では、第三次世界大戦が勃発する中、特命任務に抜擢された若い日本人陸上自衛隊・安住ひかるがこの浜に出向く姿を描いています。この若者がひたすら海を監視し続けていると、かつての恋人の姿や、昔の思い出が浮かんでは消えるという、過去と現在の交差の物語です。
前に、九州大学の教授が学生に「君たちは将来の日本を、トトロ型の国家にしたいのか?アトム型の国家かにしたいのか」という質問をしたら、過半数が「トトロ型」と答えたという話を聞いて、面白いなと思ったことがあります。だって、アトムは未来を描いているけど、トトロは過去を描いていますよね。実際われわれ人が望むのは、利便化・効率化された未来ではなくって、ものすごく不便な、人が人としてそのまま生きている、自然の世界なのかもしれない。そんな思いから今回の映画を撮影しました。
──『アエイオウ』でも、窓が特徴的に描かれているシーンはありますか?
安藤 今回の作品でどうやって窓を作ったかというと、これです。新しい窓枠です。
海しかないでしょう。辺り一面自然なのに、「窓」があるんです。もとは見張り台で、これが気に入って今回のロケ地をここに決めました。木で組まれていて、窓枠みたいになっていて本当に美しい。
映画というフレームのなかにこのフレームがあり、空青が切り取られています。海の青。波の白。窓ガラスが張られていない、野外の窓です。
──窓枠がフレーミングの役割を果たしているのですね。
安藤 フレーミングは映画の基本ですよね。特に私は写真をやっていたので、「絵を切り取る」という感覚が強いのかもしれません。日常生活でも、無意識に頭の中でカシャカシャと写真を撮っていることがあります。それに、例えば室内にいるとき、辺りに直線になっている箇所がたくさんあれば、その直線をこの直線のフレームの中にどう置くか、ということばかり考えてしまいます。そうすることで距離感が取れたり、物の大きさを測れて、安心できるんです。それに、切り取った瞬間に、「終わる」感じが気持ちいい。点が線になり、「今」が「過去」になる感覚です。フレーミングしていくことで、時間や物事の整理が付きますし、物事をまた未来への視点から見ることができるのだと思います。
昔、異常な癖があったんです。5歳ぐらいのときにオートマのカメラを渡されて、それでテレビの画面をずっと撮り続けていました。それが何千枚にもなってしまい、現像代がかかるから奪い取られてしまいましたが(笑)テレビ番組欄を全て覚えていて、自分が見たいテレビ番組になったら、ほとんどアニメでしたが、ここだと思ったシーンを切り取っていました。カメラを持ち、ずっとテレビの前で集中して見ていました。「テープは摩耗していつか見れなくなる」と思っていたので、ビデオの録画では駄目だったんです。自分で撮影することで、その瞬間を切り取れた喜びがありました。実は、出産の様子も写真と音声で残していて、分娩台から「カメラ準備!」と指示出ししていました(笑)。今も写真は自分の手で撮ることにこだわっています。
──最後に、今後、映画やご自身の活動を通して伝えて行きたいことがあれば教えてください。
安藤 私は、周囲から「3本撮るまでは映画監督とはいえない」と言われて育ちました。そして今回、短編ですが3本目の映画を撮りましたが、やはり何度撮っても、毎回異なった恐怖心があるし、その分、楽しさや発見もあります。
私が最終的に表現のツールとして選んだものは映画でしたが、世の中の人々それぞれ異なる表現方法を持っていると思います。会社員だったり、八百屋さんだったり、料理人だったり、取り組んでいることはみんな違いますし、それぞれが目指すところも別々ですが、自分の信念を疑わずに、いろんな形で自らを表現していけたら、あたたかな未来になると思うんです。
作品情報
作品名:ウタモノガタリ-CINEMA FIGHTERS project-
監督: 『カナリア』松永大司/『ファンキー』石井裕也
『アエイオウ』安藤桃子/『Kuu』平林勇/『Our Birthday』Yuki Saito
『幻光の果て』岸本司
主演:『カナリア』TAKAHIRO、夏帆、塚本晋也
『ファンキー』岩田剛典、池松壮亮、麻生久美子
『アエイオウ』白濱亜嵐、木下あかり、奥田瑛二
『Kuu』石井杏奈、山口乃々華、坂東希
『Our Birthday』青柳翔、佐津川愛美、芦名星
『幻光の果て』山下健二郎、中村映里子、加藤雅也
公開日:2018年6月22(金)~
製作年:2018年
製作国:日本
配給:LDH PICTURES
上映時間:98分
公式サイト:http://utamonogatari.jp/
安藤桃子/Momoko Ando
1982 年東京生まれ。高校時代よりイギリスに留学し、ロンドン⼤学芸術学部を次席で卒業。 その後、ニューヨークで映画作りを学び、助監督を経て2010 年『カケラ』で監督·脚本デビュー。2011 年、初の⻑編⼩説『0.5 ミリ』(幻冬舎)を出版。同作を⾃ら監督、脚本した映画『0.5 ミリ』が2014 年公開。第39 回報知映画賞作品賞、第69 回毎日映画コンクール脚本賞、第18 回上海国際映画祭最優秀監督賞などその他多数の賞を受賞。2017年高知市内に映画館「ウィークエンドキネマM」を開館。同10月ギャラリー「& Gallery」をオープン。現在、高知県に移住。一児の母。