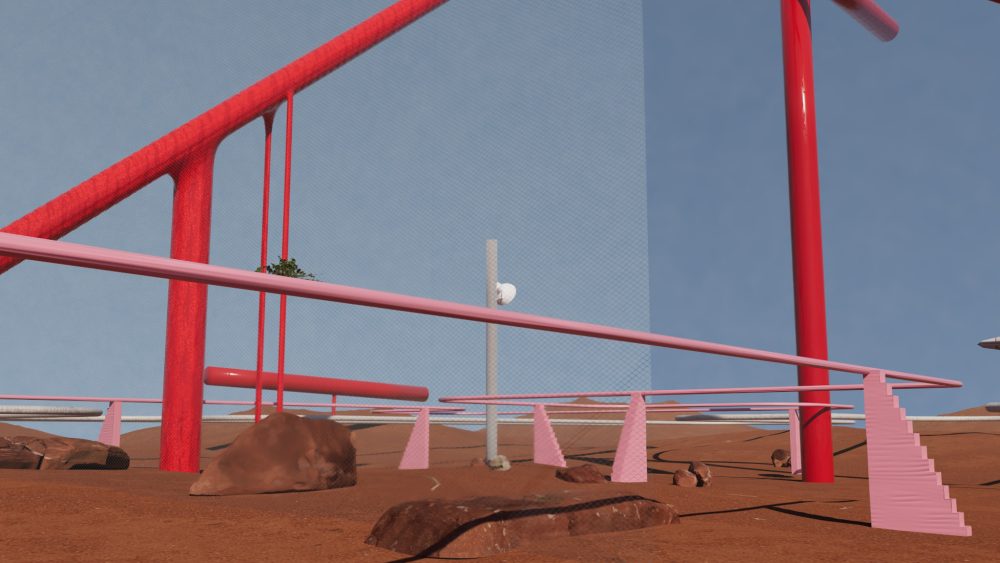ノーマン・フォスターはなぜ建物に光を注ぎ込むのか ─ スタンステッド空港からドイツ連邦議会新議事堂まで
24 May 2024
- Keywords
- Architecture
- Columns
- Norman Foster
「建築は芸術と科学の融合」を持論に、オフィスビル、美術館、行政庁舎、空港、地下鉄など、多数の作品を手がけ、20世紀後半以降の建築シーンを牽引してきたノーマン・フォスター。ハイテクながらも環境配慮を欠かさないそのデザインが国際的な評価を得て、プリツカー賞など数々の賞を受賞。1999年には、エリザベス女王より貴族爵位を受爵した。そんなフォスターが長らく情熱を傾けてきたという建築における自然光の扱い方を、照明設計の専門家であるトマス・シェルケ氏が解説する。
建築家の多くが室内を明るくするために窓を用いるなか、ノーマン・フォスターは天井から自然光を取り入れることに関心を寄せてきた。フォスターはイギリスを代表する建築家であり、ルイス・カーンやアルヴァ・アアルトの太陽光に対するアプローチを高く評価してきた。なかでも大規模な公共建築物を心地よい空間にした屋根の扱い方に影響を受けており、陸上空港や高層オフィスビルなどの巨大建造物は、天井から日が差すように設計すべきだと考えてきた。そして天井から注ぎ込む光を「人間的で詩的なだけでなく、エネルギー消費にも関わるもの」としてとらえ、そこに美しさ以上の価値を見出してきた。
-

スタンステッド・ロンドン第3空港ターミナルビル(1981-91)
Norman Foster + Partners, Image © Norman Foster + Partners
-

スタンステッド・ロンドン第3空港ターミナルビル(1981-91)のトップライト
Norman Foster + Partners, Image © Dennis Gilbert
フォスターが《スタンステッド空港》の設計に携わっていた当時、主流の空港はおもに屋根ダクト、吊り天井、屋根用空調設備、蛍光灯照明で構成されており、率直に言うと、構造的にも機能的にも無駄が多く、たくさんの自然光を取り入れるような仕様にはなっていなかった。それに比べると、《スタンステッド空港》の屋根は斬新である。建築家の説明によると、この屋根は「自然光にささげられたものであり、外装の一部がガラス張りで、太陽光を取り入れられるようになっている。そして夜になると、人工光によって同じ効果が得られる」という。
この屋根を実現するために、フォスターは従来のターミナルの形式をひっくり返し、すべての設備をメイン・コンコースの下に配置した。そして「その結果、大幅なエネルギーが節約できただけでなく、はるかに詩的な空間体験が実現」した。その後もフォスターは、《香港新国際空港》や《北京首都国際空港》などのターミナルで繰り返し同じ手法を用いた。そのいずれにおいてもトップライトは、重要な役割を果たしたのだった。
エネルギーハーベスティング用のパネルを備えたNASAのスカイラブ衛星に触発されたフォスターは、高度な技術を組み込んだ《香港上海銀行本社ビル》のために、一層の技術的挑戦を試みた。太陽光をたくさん取り込むためにアトリウムの底部に太陽光をすくい取り、高く奥行きのある建物に配された複数の鏡に反射させる計画を考案したのである。鏡があることで、プラザの半透明のガラス床を通じて、地上に太陽光が反射する。しかし「夜になると、下から差し込む光によって状況は逆転し、プラザの床そのものがクリスタルや宝石のような輝き」を放ち出す。日が沈むと、コンセプトが反転するのである。
-

香港上海銀行本社ビル(1979-86)
Norman Foster + Partners, Image © Nigel Young
-

香港上海銀行本社ビル(1979-86)
Norman Foster + Partners, Image © Ian Lambot
1975年に竣工したイギリス・イプスウィッチの《ウィリス・フェイバー・デュマス本社ビル》のように、オフィスビルに天井から太陽光を取り入れた例は多数ある。フランクフルトの《コメルツ銀行タワー》など、その後のオフィスビルでフォスターは、大規模で迫力満点のデイライトシステムに頼らずにアトリウムを設計することができるようになった。
-

ウィリス・ファーバー・アンド・デュマ本社(1970-1975)
Norman Foster + Partners, Image © Tim Street-Porter
-

ウィリス・ファーバー・アンド・デュマ本社(1970-1975)
Norman Foster + Partners, Image © Tim Street-Porter
フォスターは、この手法を追求して自然な雰囲気を作るべく、地下鉄にも目を向け、さらなる太陽光を注ぐ機会をうかがった。メトロ・ビルバオや《カナリー・ワーフ駅》のガラス張りのエントランスは、コンコースの奥深くにまで太陽光を取り込むことができる。人々を歩道から地下へと誘い込むガラスで囲いのエスカレーターからすでに、建築家のコンセプトが始まっているのだ。電車から通勤客が降りてくると、光のプールが出口へと導いてくれるので、大量の案内板は必要ない。
-

カナリー・ワーフ駅(1999)
Norman Foster + Partners, Image © Nigel Young
-

カナリー・ワーフ駅(1999)
Canary Wharf Underground Station, Norman Foster + Partners, Image © Dennis Gilbert
ベルリンの《旧帝国議会》(現・連邦議会新議事堂)には、議場の下に太陽光を採り入れるためにもともとドームが設けられていたが、フォスターの改修を経て、それがさらに多様な機能を備えるようになった。見学者のための螺旋状の通路は、その一例に過ぎない。改修時に追加された鏡は、議場全体の照明を和らげる役割を担っており、真っ直ぐに差し込んでくる光を下方空間に向けて跳ね返すように個別に調整されている。しかし太陽光の量が増えると今度は、まぶしくなりすぎなように制御することが大きな課題となる。ドームに設置された大型の日よけは、政治家やテレビ放送に必要とされる視覚的な快適さをもたらした。この日よけが太陽の軌道に沿って動き、厳しい直射日光を遮ってくれる。そしてそれとは対照的に、夜になるとキューポラの鏡が光の道標を作り出し、街の標識となる。さらに天井に円を描くようにしてスポットライトが配置されることで、光が一点に集中しないようになるなど、あらゆるシーンや時間に対応するインフラが整備された。
-

ドイツ連邦議会新議事堂(1999)
Norman Foster + Partners, Image © Reinhard Gorner
-

ドイツ連邦議会新議事堂(1999)
Norman Foster + Partners, Image © Nigel Young
-

ドイツ連邦議会新議事堂(1999)
Norman Foster + Partners, Image © Nigel Young
-

ドイツ連邦議会新議事堂(1999)
Reichstag New German Parliament, Norman Foster + Partners, Image © Dennis Gilbert
フォスターが手がけた初期と最近の作品を比較すると興味深いのは、前者がおもに個人の主観に頼って設計されていたのに対して、後者は具体的な数字やデータで評価できるように設計されている点である。脳内の特定の位置を流れる血流の増加パターンを読み解くことで、自然光による視覚刺激のある環境への生理学的な反応を測定することができる。長期的なパフォーマンスの向上を証明できるようになったことで、フォスターは幅広いハイエンドプロジェクトにおいて、高い投資コストの必要性を正当化できるようになった。光を質的な資産としてだけでなく、量的な資源としても捉えるようになったことで、彼の事務所のアプローチは劇的に変化した。フォスターにとって、「建物が最終的にどう“呼吸”して自然と交わるかは、人間的で詩的で精神的な次元と切り離して考えられる問題ではない」のである。
参考文献
Norman Foster, David Jenkins: Norman Foster – Talking and Writing. Norman Foster Foundation, Madrid. 2017
Top image: © Tim Street-Porter
本コラムは2019年2月9日にArchDailyに掲載された記事を再編集し、翻訳したものです。オリジナルの記事は“Why Norman Foster Scoops Daylight into his Buildings”で読むことが出来ます。
トマス・シェルケ/Thomas Schielke
ダルムシュタット工科大学で建築学を学んだ後、同大学で工学の博士号(Dr-Ing)を取得。現在は、ライティングメーカーERCOのライティングデザイントレーナーを務め、建築用照明に関する幅広いオンラインガイドを設計し、ライティングの指導に従事。おもな出版物に、「Light Perspectives – between culture and technology」(2009年)や「SuperLux – Smart Light Art, Design & Architecture for Cities」(2015年)など。おもな講演先に、ハーバード大学デザイン大学院、マサチューセッツ工科大学、コロンビア大学GSAPP、スイス連邦工科大学チューリッヒなど。オンラインメディア『ArchDaily』で連載中のコラム「Light Matters」では、様々な側面から建築用照明について発信している。