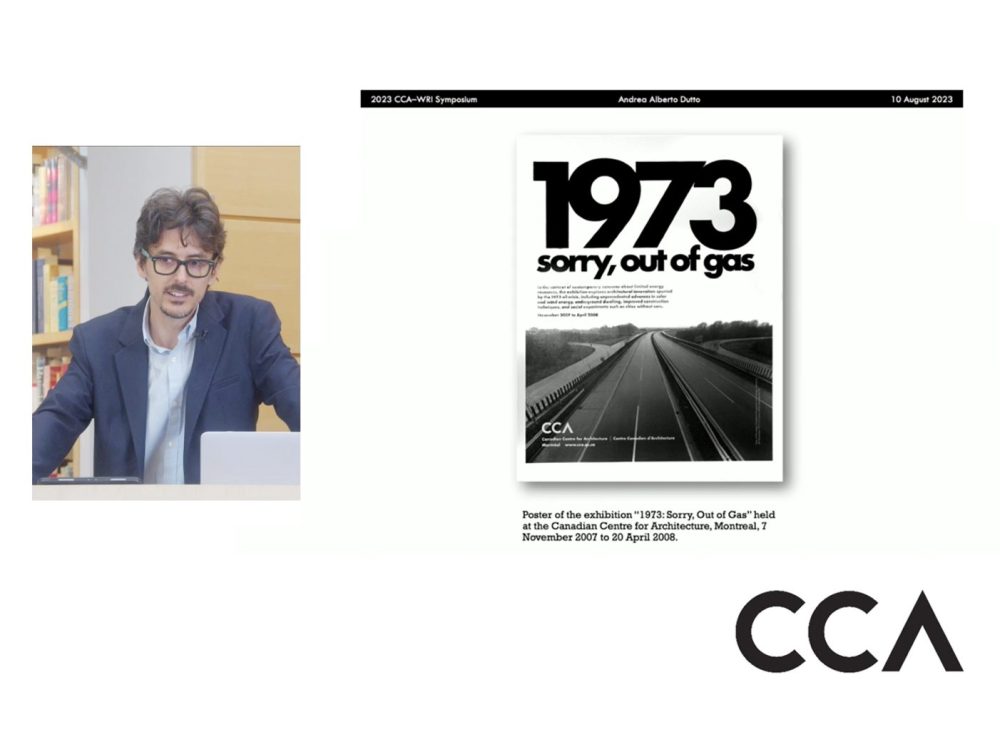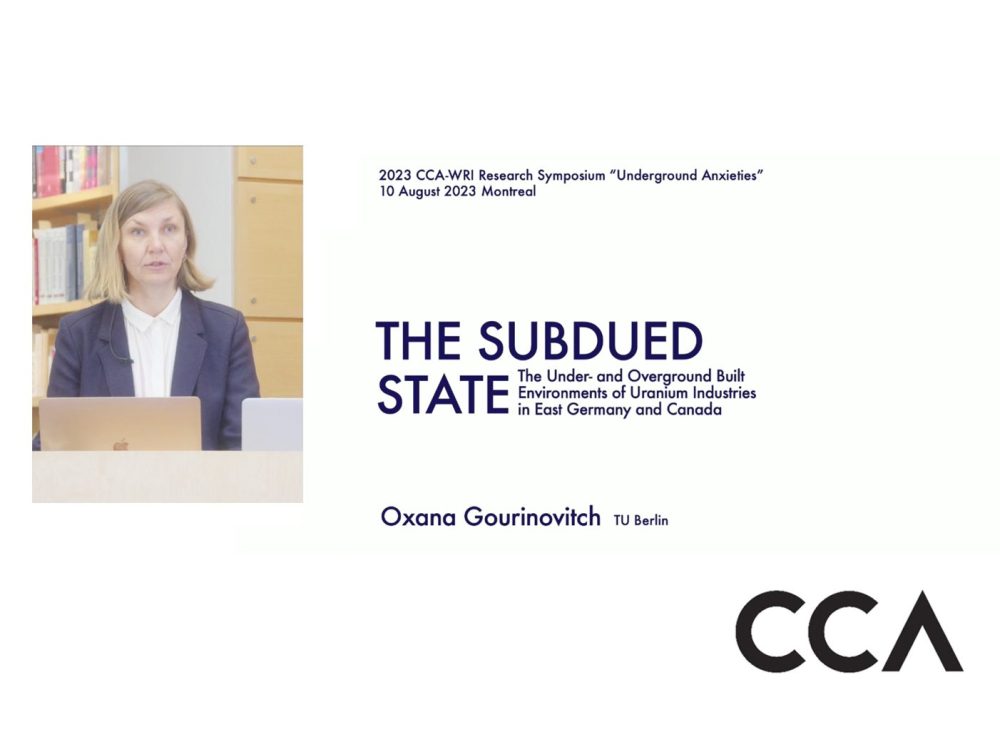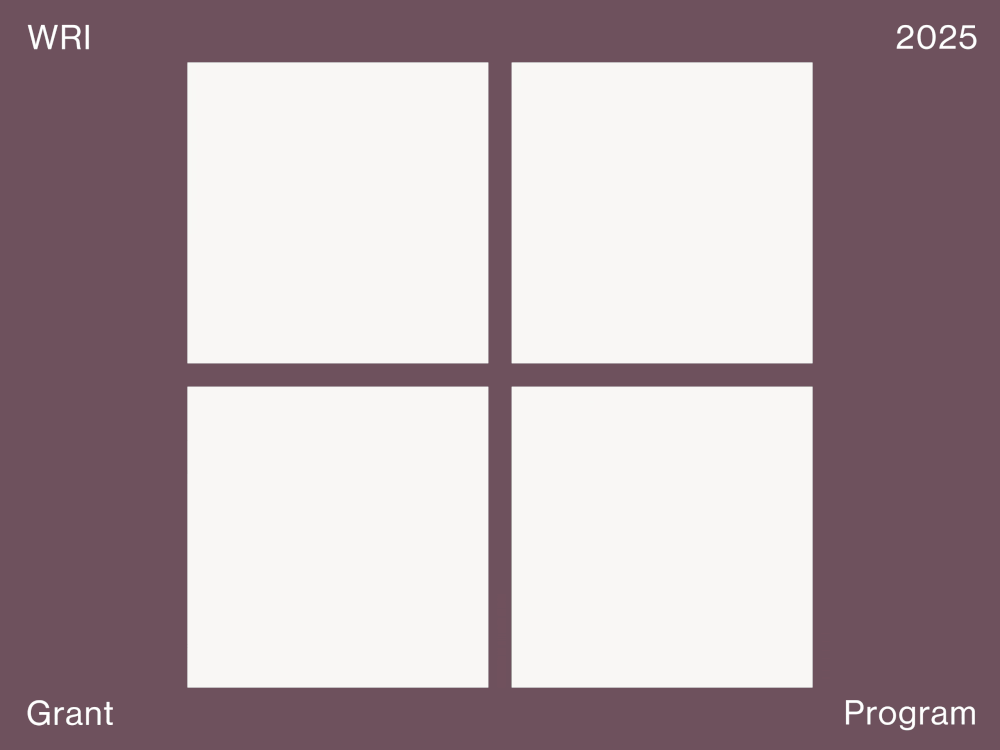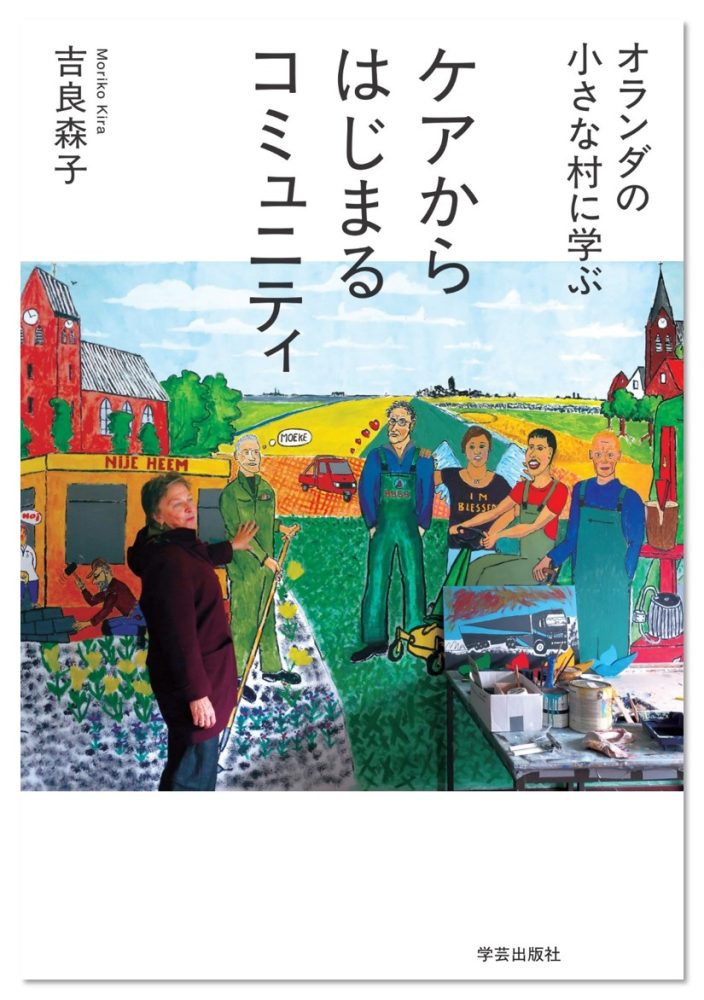Grant Results 2023年度 採択テーマ CCA-WRI Research Fellowship
Visual Function in Earth shelters from the viewpoint of emergency sustainability
視環境と持続性――地下シェルターにおける光の評価
31 Mar 2025
- Keywords
- Architecture
- CCA-WRI
公益財団法人 窓研究所は、カナダ建築センター(Canadian Centre for Architecture)と共同でフェローシップ・プログラム「CCA-WRI Research Fellowship」を実施しています。本記事は、2023年度リサーチフェローのひとりである宮田智美氏の研究テーマを紹介するものです。
研究テーマ概要
本研究では、アースシェルターにおける視覚的機能について、二つのアプローチから検討を行った。一つは、ヘッドマウントディスプレイ型バーチャルリアリティ(HMD-VR)を用いた視覚実験による定量的かつ心理的アプローチであり、もう一つは、人々および社会の嗜好に着目したフィールド調査およびアーカイブ調査である。前者は視環境の最適化に有用であり、後者は文化的嗜好を視覚環境デザインに反映させる上で意義があると考える。
視覚環境デザインの最適化に向けた定量的実験
– 光および空間の測定
– VRを用いた主観評価実験
社会的嗜好を読み解くフィールド調査およびアーカイブ調査
– オフィス内装の図面・写真
– アーカイブ資料および現地調査(核シェルターの訪問)
– CCAのスタッフおよびリサーチフェローへのインタビュー
1. オフィス空間の光色測定とVR実験
CCA館内にある21室の部屋において、全天周の光色測定を行い、そのうち10室を仮想空間に再現した。空間への慣れが光の変化に対する反応に与える影響を検証するため、CCAスタッフ8名および外部研究者7名を対象に、各自のオフィス空間に対し14~20種類の光環境での評価を実施した(利用可能な照明の種類に応じてパターン数は異なる)。外部研究者については、主にCCAアーカイブやコレクションの閲覧に使用していた図書館空間について評価を行った。
均一な光変化の影響:明るさの増加によりスタッフの快適性が低下
光量が変化しても輝度分布が均一な場合、外部研究者は明るい環境ほど作業効率および快適性が高まり、暗い環境ではそれらが低下する傾向を示した。一方で、スタッフにおいては通常使用しているオフィスの照明が最も快適かつ効率的であるという結果が得られた。
不均一な光変化の影響:自然光の変化に伴う輝度分布の変動
自然光のみが変化する状況(すなわち輝度分布が変化する場合)では、スタッフの読書、筆記、PC作業における作業効率は、自然光が元の20%まで減少した場合や、3倍に増加した場合でも大きな変化は見られなかった。これに対し、外部研究者の評価は、自然光が元の60%未満、あるいは150%以上になると変化する傾向が確認された。
2. アースシェルターに関する現地調査
滞在期間中、以下の2つの地下施設を訪問した。
ベルリン・ウンターウェルテン(Berliner Unterwelten)
第一次世界大戦および冷戦期の地上および地下核シェルターを保存・公開するベルリンの団体である。
ディーフェンバンカー(Diefenbunker)
カナダに所在する、窓のない4階建ての政府用地下核シェルターであり、現在は冷戦博物館として運営されている。
これらの空間では、光環境や窓の有無だけでは「地下空間であること」を明確に視覚的に判断することは難しかった。しかし、狭い廊下のような空間、冷たい室温、空気の質などがわずかな違和感として作用し、来訪者に「ここは地下空間である」という感覚的な認識を促す手がかりとなっていた。
3. 考察と学び
照明の変化に対する反応は、スタッフと外部来訪者とで異なる傾向が見られた。特に、空間に慣れているスタッフは輝度分布の変化に対してより敏感であることが確認された。空間への適応度が高い者ほど、視環境の変化に対して柔軟に対応できる可能性が示唆された。
地下シェルターは窓がないことが多く、光環境の変化は人工的に設計される必要がある。短期滞在を前提としたシェルターにおいては、輝度の変化が作業効率や快適性の低下を引き起こす可能性がある。一方で、長期滞在を想定したシェルターにおいては、輝度分布の変化を伴う光の変化が、居住者にとっての快適性や作業効率の維持に貢献する可能性がある。
『Underground Anxieties: 2023 CCA-WRI Research Symposium』(2023年8月10日、モントリオール)記録映像より
佐野智美(旧・宮田智美)/Tomomi M. Sano (former, Tomomi Miyata)
1989年東京生まれ。幼少期をカナダとイギリスで過ごし、文化的ルーツを再確認するために帰国。東京工業大学(現・東京科学大学)で建築学修士号を取得後、照明設計や視環境解析ソフトウェアの開発企業に勤務。その後、同大学博士課程に進学し、2011年の東日本大震災後の計画停電の経験をきっかけに、HMD-VRを用いた緊急時のオフィス視環境と事業継続に関する研究で博士号を取得(2022年)。2023年より建築研究所にて、建築のエネルギー性能評価と社会実装に取り組む。同年6月から9月にかけて、WRI-CCAリサーチ・フェローとしてCCAに滞在し、建築デザインにおける歴史・文化の影響を調査。現在は、視環境に対する人びとの文化的・身体的適応の影響に関する研究を進めている。