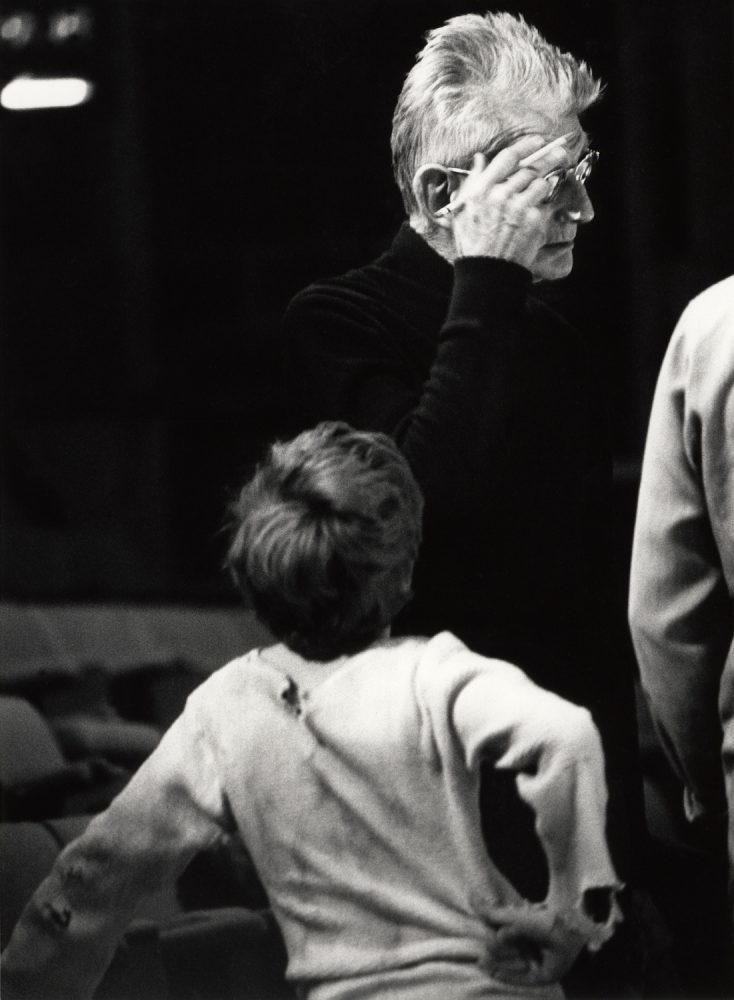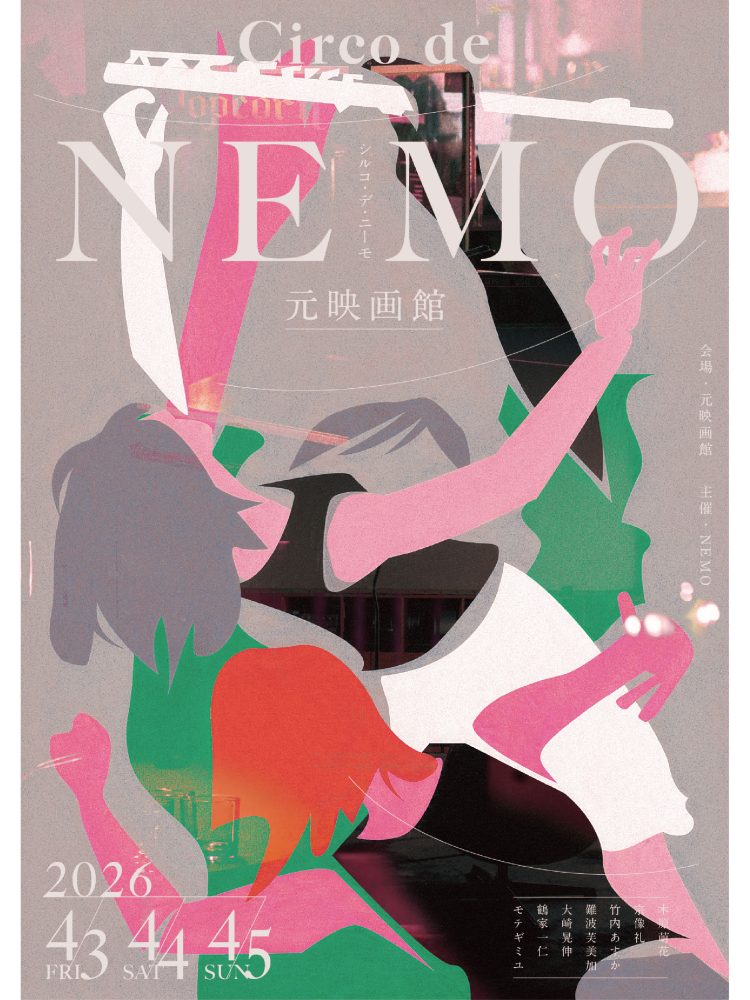堀江敏幸|気泡に封じ込められた微笑──夏目漱石『硝子戸の中』から
23 Dec 2020
- Keywords
- Columns
- Essays
- History
- Literature
夏目漱石の晩年の作、『硝子戸の中』。「私」は部屋の中から、うつろう日々を見つめつつ、過去の記憶にも思いをめぐらせます。そんな趣深い小品を読み解くのは、作家・フランス文学者の堀江敏幸さん。漱石を愛読し、また自身も『戸惑う窓』というエッセイ集を手がけた堀江さんが“漱石と窓”を考える、魅惑のテクストです。
中学か高校の、国語の教科書と併用する便覧でだったろうか、はじめて夏目漱石の書斎の写真を目にした。早稲田南町時代の、いわゆる漱石山房の一室である。白黒だったから細部の色はわからないのだが、中央手前に原稿用紙と筆箱と辞書が載るくらいの小さな文机が置かれ、その向こう側にチェック地の座布団が、書き手から見て右側には鋳物らしいどっしりした薬罐の載った大きな火鉢がある。私はまず、床に整然と積まれた本の山脈に目を奪われた。いま使っている本、これから使いそうな本、読み返したい本たちが、小口を見せない控えめな知の柱廊をなし、そのまた背後の壁にならぶ書棚の横置きされた書籍とも連動して、美しい律動を感じさせる。明窓浄机とはおそらくこういう空間を言うのだろう。
漱石がこの書斎のある家に移り住んだのは明治40年9月、小説を書く記者という奇妙な肩書きで朝日新聞に入社してから半年ほど経って、『虞美人草』を完成させた頃である。大正5年、『明暗』連載のさなかに49歳で亡くなるまで、漱石は胃痛に悩まされながらこの書斎でひたすら書きつづけた。書斎の隣りにあった居間は、毎週木曜日に来客を迎え入れる文芸サロンの役割も果たしていたので、この二室は読者にとってまぎれもない聖域なのだが、居間は和室のようだったし、文机に火鉢、和服の作家の結びつきから、書斎も当然和室だと思い込んでいた。
ところが、大学に入ってから安価で購入した袖珍版全集の、別冊に収録されている「文士の生活」と題された談話(大正3年3月22日、大阪朝日新聞)を読んで、とんでもない勘違いに気づかされた。実際には板敷きの洋間だったのである。「此家は七間ばかりあるが、私は二間使つて居るし、子供が六人もあるから狭い。家賃は三十五圓である」。もとは医者が住んでいたという、手すりのある回廊に囲まれたかなり広い屋敷で、文机の左側にある上げ下げ式の西洋窓とあいまって、どこか南洋諸島ふうのコロニアルな雰囲気さえ漂っている。窓掛けが下がっていて写真では判別しづらいのだが、文机の背後の壁にも腰高の細長い窓がふたつあるので、かなりの陽が入るのではないかという前向きな想像もあっさり否定された。
「私はもつと明るい家が好きだ。もつと奇麗な家にも住みたい。私の書斎の壁は落ちてるし、天井は雨洩りのシミがあつて、随分穢いが、別に天井を見て行つて呉れる人もないから、此儘にして置く。何しろ畳の無い板敷である。板の間から風が吹き込んで冬などは堪らぬ。光線の工合も悪い。此上に坐つて読んだり書いたりするのは辛いが、気にし出すと切りが無いから、關はずに置く。此間或る人が來て、天井を張る紙を上げませうと云つて呉れたが、御免を蒙つた。別に私がこんな家が好きで、こんな暗い、穢い家に住んで居るのではない。餘儀なくされて居るまでである」
親友の正岡子規が病臥していた根岸の家には、横になったままの状態で庭の景色が見える、当時はまだ珍しい硝子戸があった。明治32年12月、高浜虚子から贈られたものである。ほどなく子規は漱石に宛てて、病室の南側の窓が「ガラス障子」になり、寒気も防げるし昼間は日光が入ってあたたかいと伝えている。この子規庵の写真も記憶に刷り込まれていたせいか、漱石の書斎はあくまで畳敷きで、気泡入りの古い硝子が嵌まっている戸に囲まれた、藺草の香りが漂う明るい和室だという絵が頭のなかにできあがってしまったのである。ロンドン留学時代の下宿のような洋窓が嵌められているなどとは考えもしなかった。
「硝子戸の中から外を見渡すと、霜除をした芭蕉だの、赤い実の結つた梅もどきの枝だの、無遠慮に直立した電信柱だのがすぐ眼に着くが、其他に是と云つて数え立てるほどのものは殆ど視線に入つて來ない。書斎にゐる私の眼界は極めて単調でさうして又極めて狭いのである」
大正4年、つまり1915年1月13日から2月23日まで、39回にわたって朝日新聞に連載された『硝子戸の中』は、そんなふうにはじまる。視界が限られているうえに年の暮れから風邪を引いてずっと硝子戸の中にいるので、「世間の様子はちつとも分らない。心持が悪いから読書もあまりしない」という。たしかに健康状態はよくなかった。前年の夏、『こころ』を書き上げた直後の9月に四度目の胃潰瘍になって、10月末まで調子が悪かった。にもかかわらず、新聞社から給料を貰う職業作家である以上、こんな小品の連載もこなさなければならない。先走って言えば、翌年3月には五度目の胃潰瘍に見舞われながら、6月から9月まで『道草』を連載している。身体は着実に蝕まれていった。残されている命は、あと一年と少々しかない。
そんな予感があったからか、『硝子戸の中』の語り手は心を硝子張りにし、日中でもマグネシウムを焚かなければならないほどの暗さのなか、胸の内をレントゲン写真さながら他者に披瀝して、記憶の奥深くへ降りて行くために死者の力を借りる。というより、みずからその死者になりかわり、向こう側の目でこちらを見ようとする。天井のシミを隠すのではなく、それを凝視することが求められているのだ。
いま「私」は、透明の硝子のゲージのなかでうずくまっている。猫のように、いや、貰われてきた子犬のように。第三章から第五章までひとつづきで語られる愛犬ヘクトーの逸話は、表に出るべくして出てきた、語り手における存在のシミにほかならない。風呂敷に包まれて山房にやってきたヘクトーを、「私」はその夜、藁を敷いて温かくした裏の物置きに寝かせた。ところが子犬は宵の口から激しく鳴き出し、戸をひっかいて外に出ようとした。「彼は暗い所にたつた獨り寝るのが淋しかつたのだらう、翌る朝迄まんじりともしない様子であつた」。物置の戸はただの木戸だから中は見えない。主人は硝子戸のこちら側にいて、内部の闇と子犬の孤独に心の波長を合わせている。
漱石はかなり遅くにできた子だった。懐妊を恥じた母親は、他の兄姉と歳の離れた末子を生後すぐ里子に出した。出された先は、夏目家の女中の姉の嫁ぎ先だった四谷の古道具屋と源兵衛村の八百屋の二説あり、どちらの場合も商売のあいだ鉢か籠に入れられて地べたに置かれていたことになっているのだが、「私」は第二十九章で前者の説を踏襲してこう書いている。
「私は其道具屋の我楽多と一所に、小さい笊の中に入れられて、毎晩四谷の大通りの夜店に曝されてゐたのである。それを或晩私の姉が何かの序に其所を通り掛つた時見付けて、可哀想とでも思つたのだらう、懐へ入れて宅へ連れて来たが、私は其夜どうしても寝付かずに、とう〳〵一晩中泣き続けに泣いたとかいふので、姉は大いに父から叱られたさうである」
硝子戸の中の「私」は、記憶のない幼児のときの自分と貰われてきた子犬を同一視している。夜中にまんじりともしなかったのはヘクトーであり、眠れない状態を共有している「私」自身でもある。里子に出され、連れ戻され、再度里子に出されたものの新しい養家に問題が生じて、そこに籍を置いたまま九歳のとき夏目家にまた引き取られた金之助。夏目家に復籍したのはようやく明治21年、21歳のときである。意識の底から湧きあがるさみしさと孤独が、ヘクトーとの出会いと別れに重ねあわされる。ある日、ヘクトーは姿を消す。一週間ほどして、「一二丁隔つたある人の家」の庭の池に浮いているのが見つかった。その家の下女が知らせに来てくれたのである。あちらで埋めておきましょうかという申出を断って「私」は車夫を雇い、愛犬を筵に包んで持って来させると、庭に埋めて、白木の墓標に「秋風の聞えぬ土に埋めてやりぬ」と記した。庭にはすでに、猫の墓もあった。
「私の書斎の、寒い日の照らない北側の縁に出て、硝子戸のうちから、霜に荒された裏庭を覗くと、二つとも能く見える」
二つの墓は、いずれ自分にも訪れる死を暗示している。硝子戸の中に沈潜し、内から外を眺めなければ生まれえなかった感懐でもあるだろう。つまらない日常の些事と重い記憶をない交ぜにして、「私」は自分を見つめ直す。己を映す手段は鏡だけではない。写真の手を借りることもできる。
某雑誌の記者が写真を撮りに来たときの顛末が、第二章に語られている。電話で撮影取材の申し込みがあり、「私」が「あなたの雑誌へ出すために撮る写真は笑はなくつては不可いのでせう」と確認すると、そんなことはないと言う。「当り前の顔」でよければとの条件で受けたものの、当日の撮影では、どうか笑って下さいと頼んでくる。「私」はとりあわない。しかし後に送られて来た写真を見たら、たしかに少しばかり笑みを浮かべていた。これはおかしい。写真に細工をして笑っているように見せたのだと考え、家族の見解を乞うと、果たして同意見であった。なんとなく滑稽な逸話ではあるのだが、ここには笑おうとしない自分を見てさみしく笑っているもうひとりの自分の目が働いている。少しくらい許してもいい他者に対する笑みを、あたかも天井のシミのようにしか見做せない自己凝視の淋しさに読者は打たれる。
冒頭からずっと坐っていた「私」は、最終章で立ち上がり、硝子戸を開け、庭を見渡す。自身の内部を見るだけではない。驚くべきことに、「一般の人類をひろく見渡しながら微笑してゐる」。人に頼まれても絶対に見せないその微笑を、自分から「一般の人類」に向けているのだ。
「今迄詰らない事を書いた自分をも、同じ眼で見渡して、恰もそれが他人であつたかの感を抱きつゝ、矢張り微笑してゐるのである」
冬がいつのまにか春になる。不機嫌な顔につくりものではない笑みが浮かぶ。しかしこのやわらぎは束の間のものにすぎない。ヘクトーも「私」も、哀しみと孤独のなかで声を上げた。そのとき意識に刻まれた傷はいつまでも消えない。
「所詮我々は自分で夢の間に製造した爆裂弾を、思ひ〳〵に抱きながら、一人残らず、死といふ遠い所へ、談笑しつゝ歩いて行くのではなからうか」
『硝子戸の中』は、第30章で語られているとおり、大日本帝国も加わった大戦が「継続中」の状況で書かれている。人類一般という書斎からあまりにもかけ離れた大仰な言葉は、いつ本格的に漏るのかわからない屋根と天井の傷を、あるいはいつ破裂するのかわからない心の爆弾のありかをごまかさずに示すことで、はじめて意味を持つだろう。この散文集を囲む硝子戸の気泡には、すぐそこに自身の死が迫っていることを意識した者だけに許された微笑が封じ込められている。「私」とかぎりなく近い漱石は、その気泡のありかを知りながら、ついに取り出すことなく息絶えた。
堀江 敏幸/Toshiyuki Horie
作家、フランス⽂学者。早稲⽥⼤学第⼀⽂学部仏文科卒。東京⼤学⼤学院博士課程中退。フランス政府給費生としてパリ第3⼤学に留学。1995年フランス留学経験を随筆⾵に綴った『郊外へ』(白水社)でデビュー。2001年『熊の敷⽯』で、第124回芥川賞受賞。現在、早稲⽥⼤学文学学術院教授。主な著書として、『その姿の消し方』(新潮社)、『傍らにいた人』(日本経済新聞社)、『曇天記』(都市出版社)、『オールドレンズの神のもとに』(文藝春秋社)等がある。