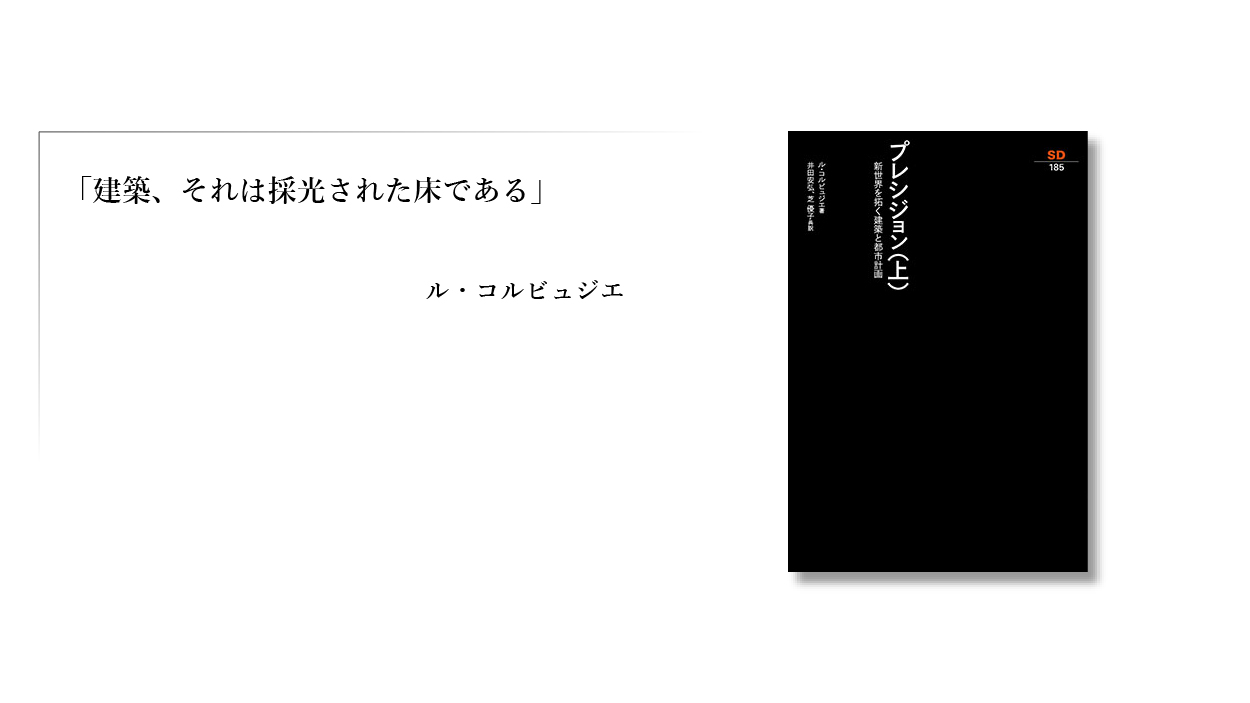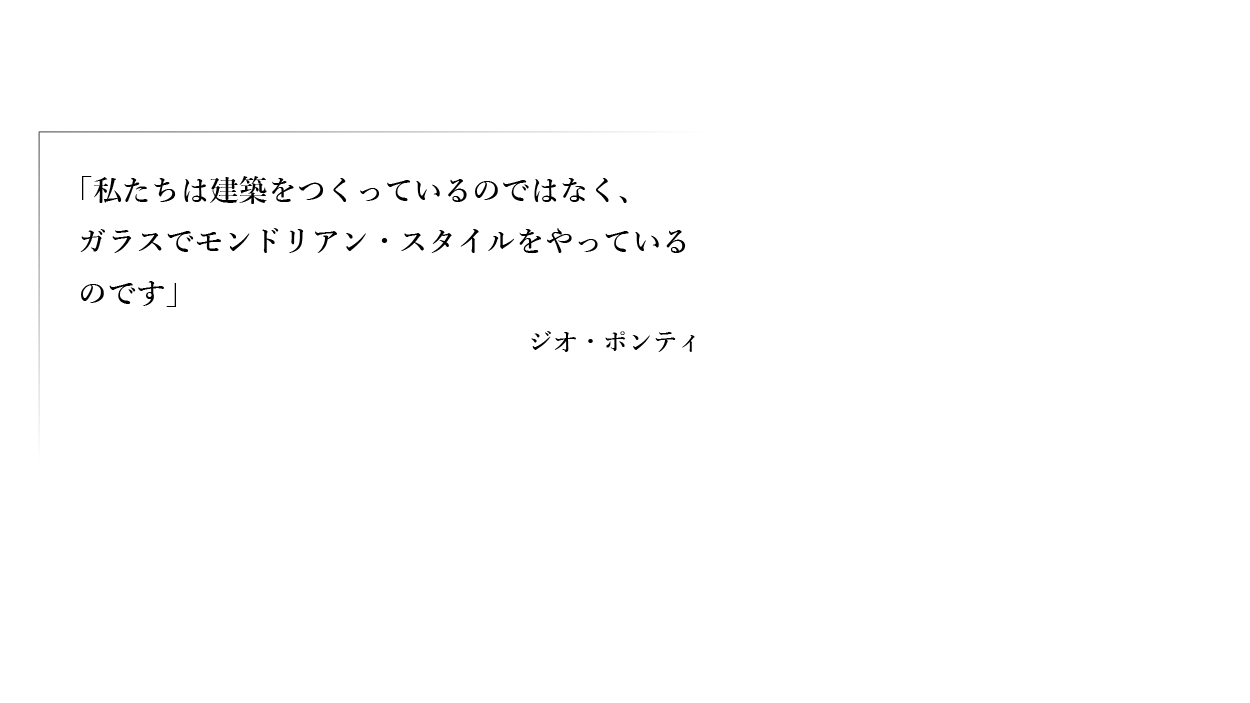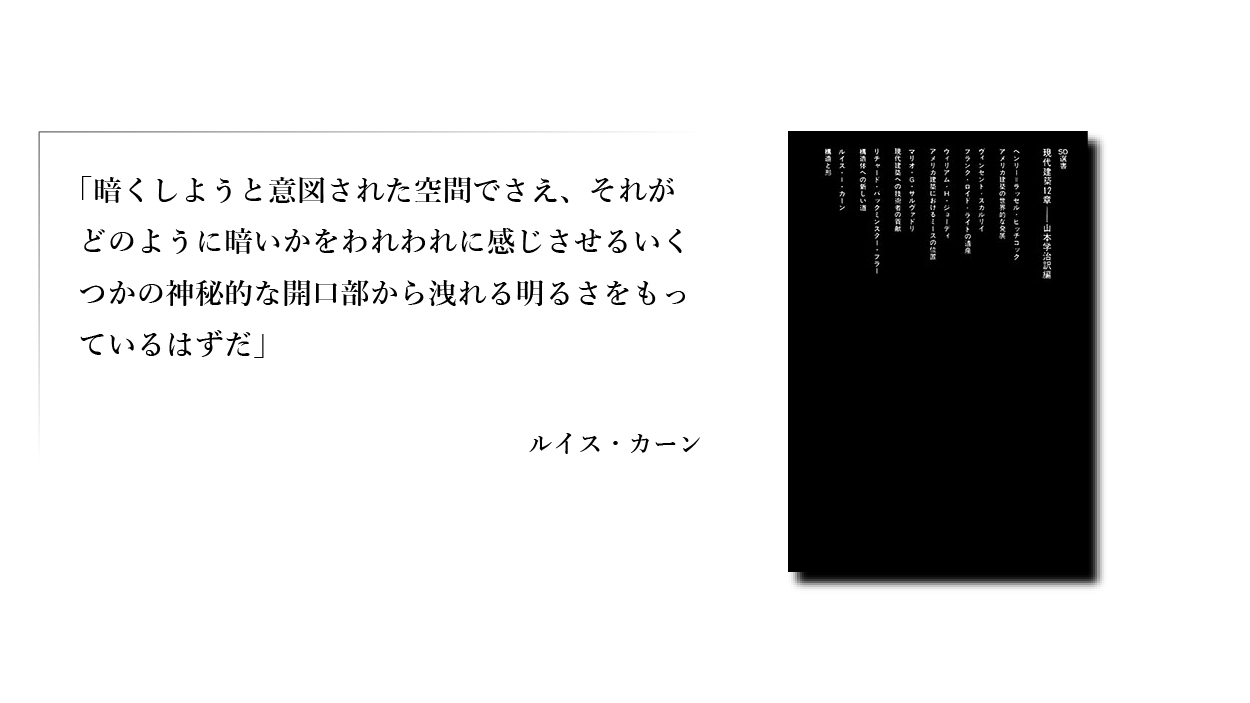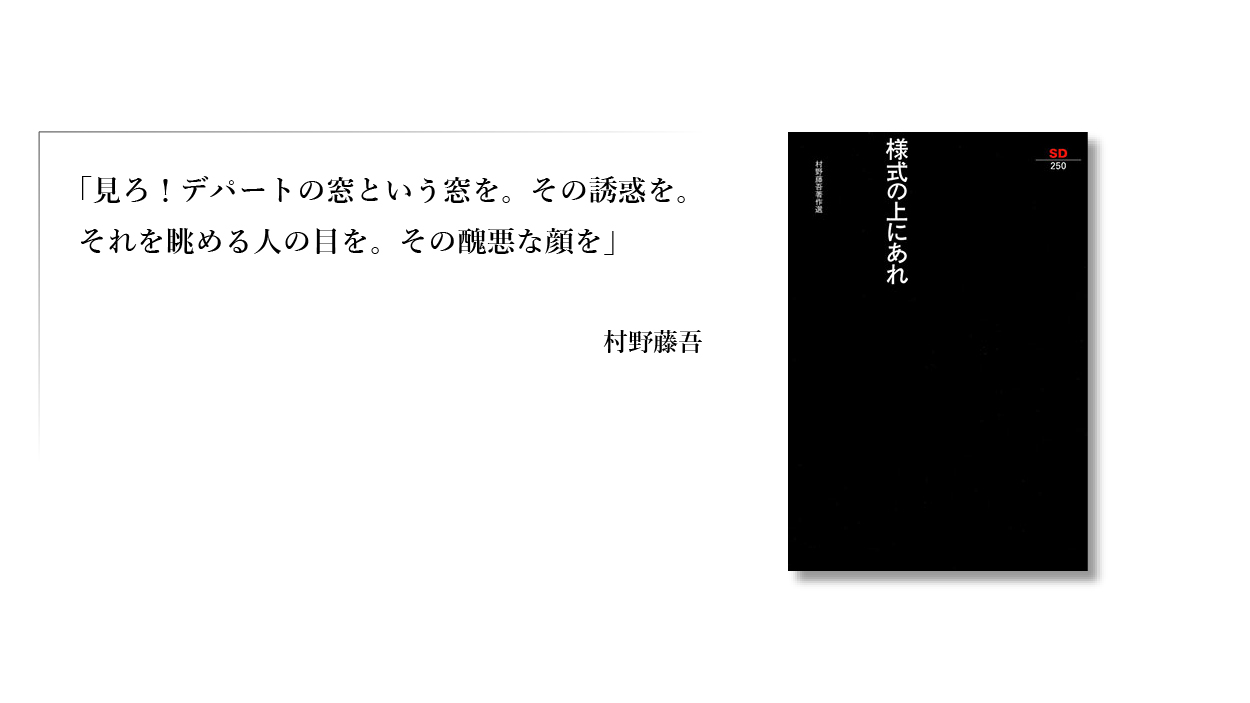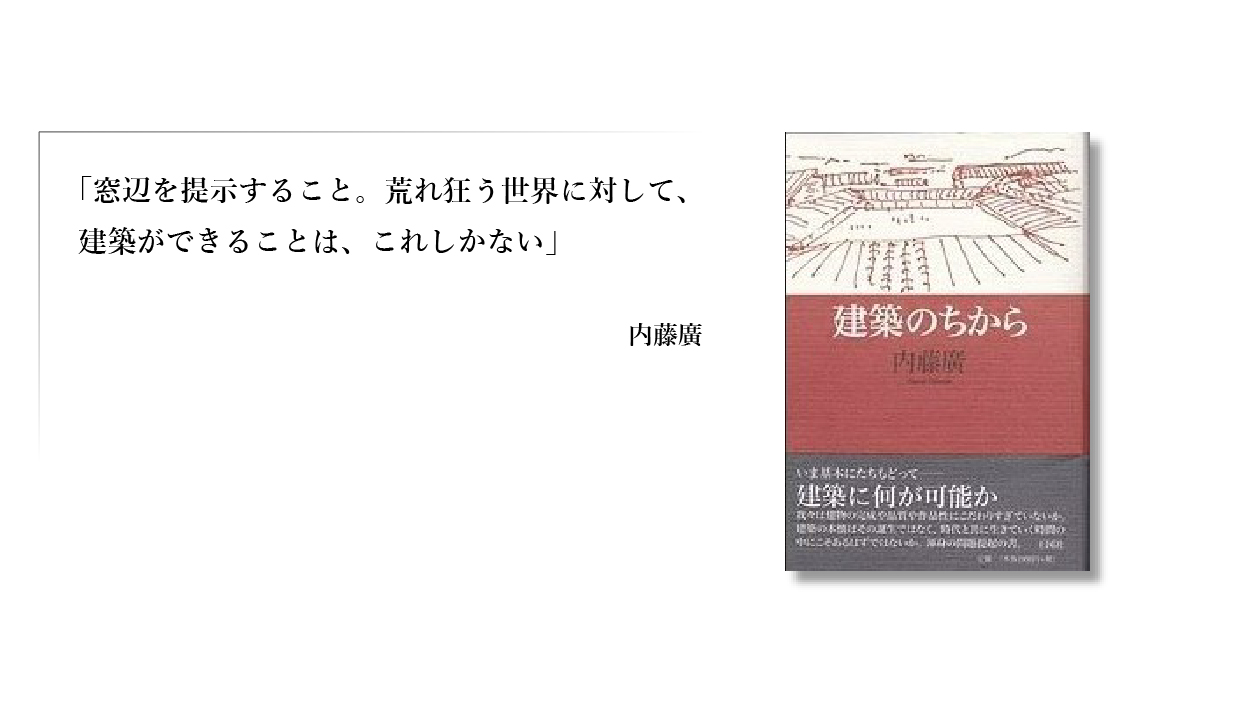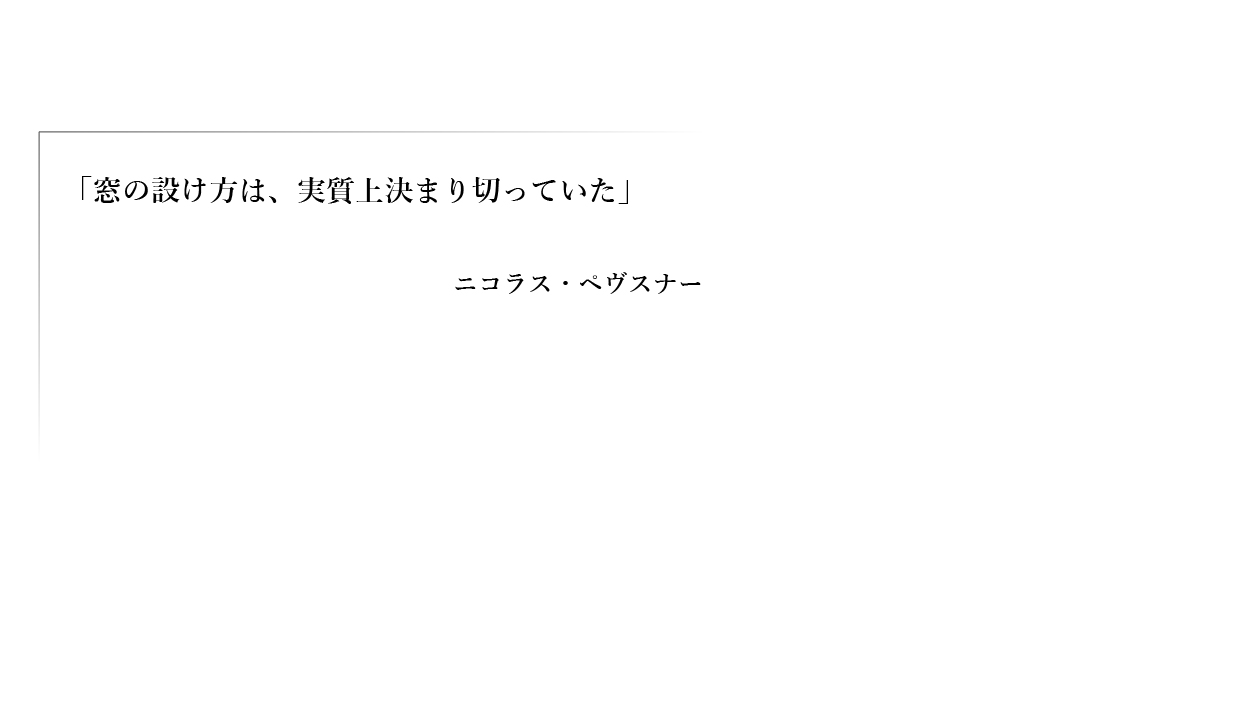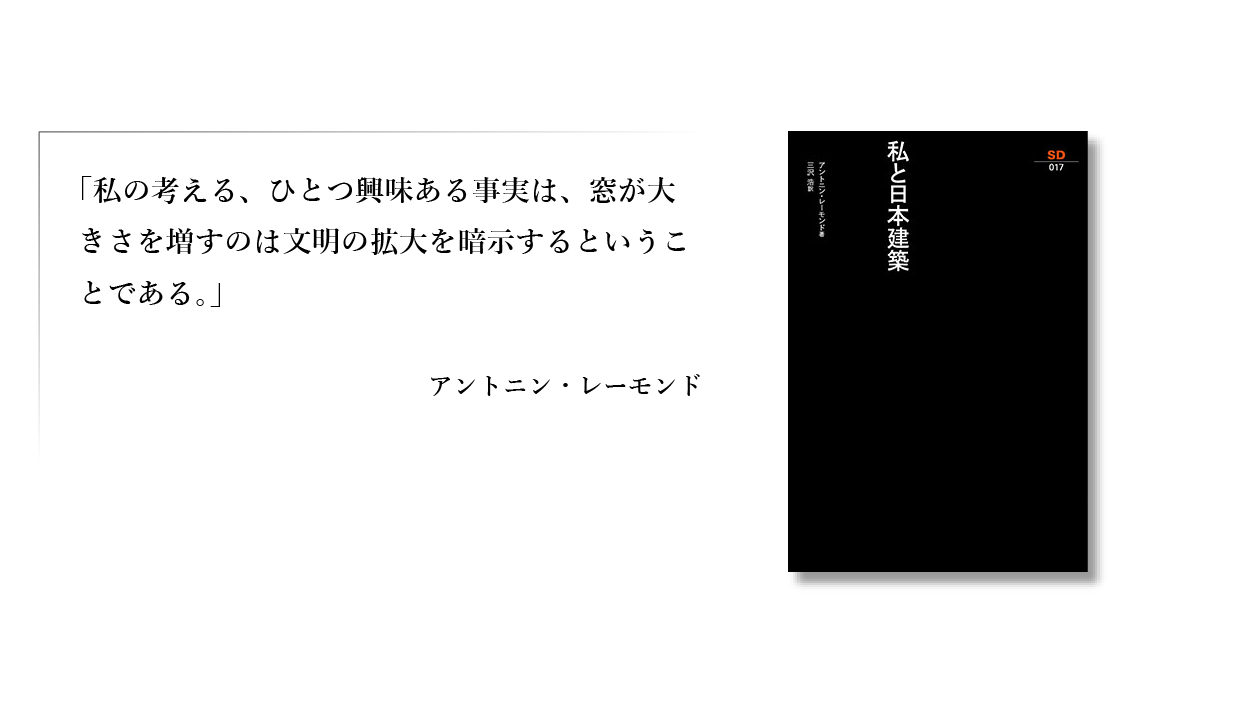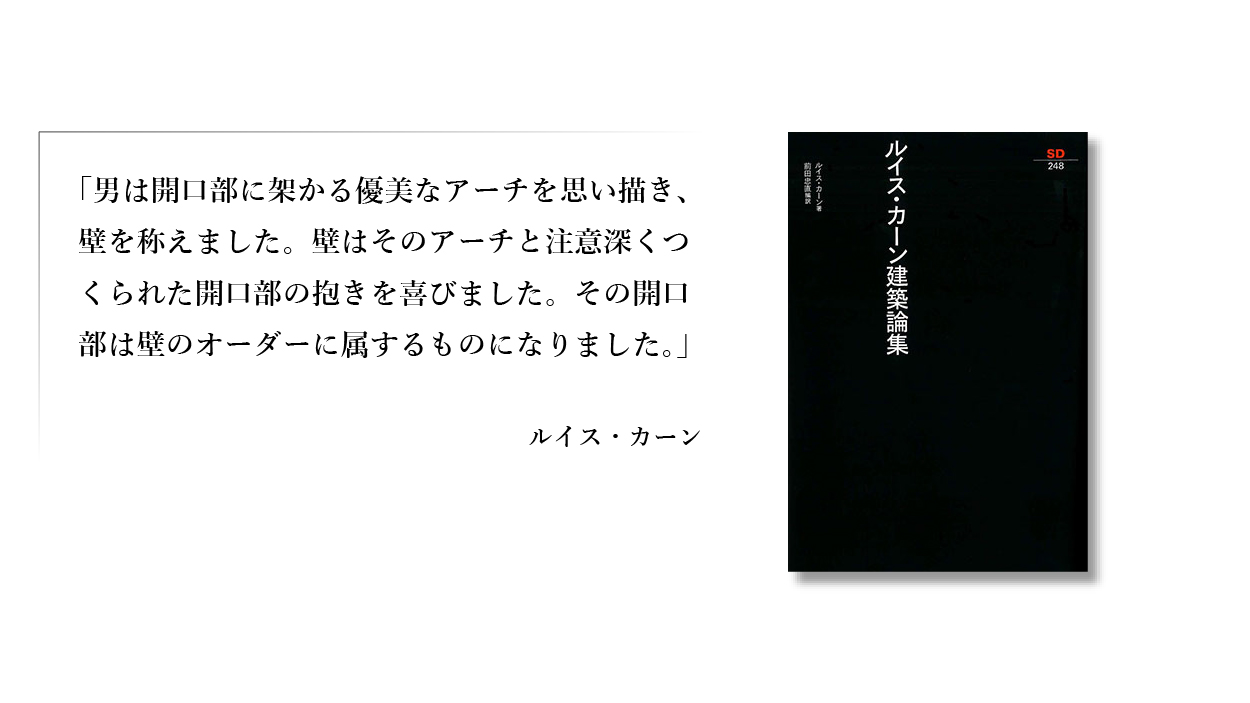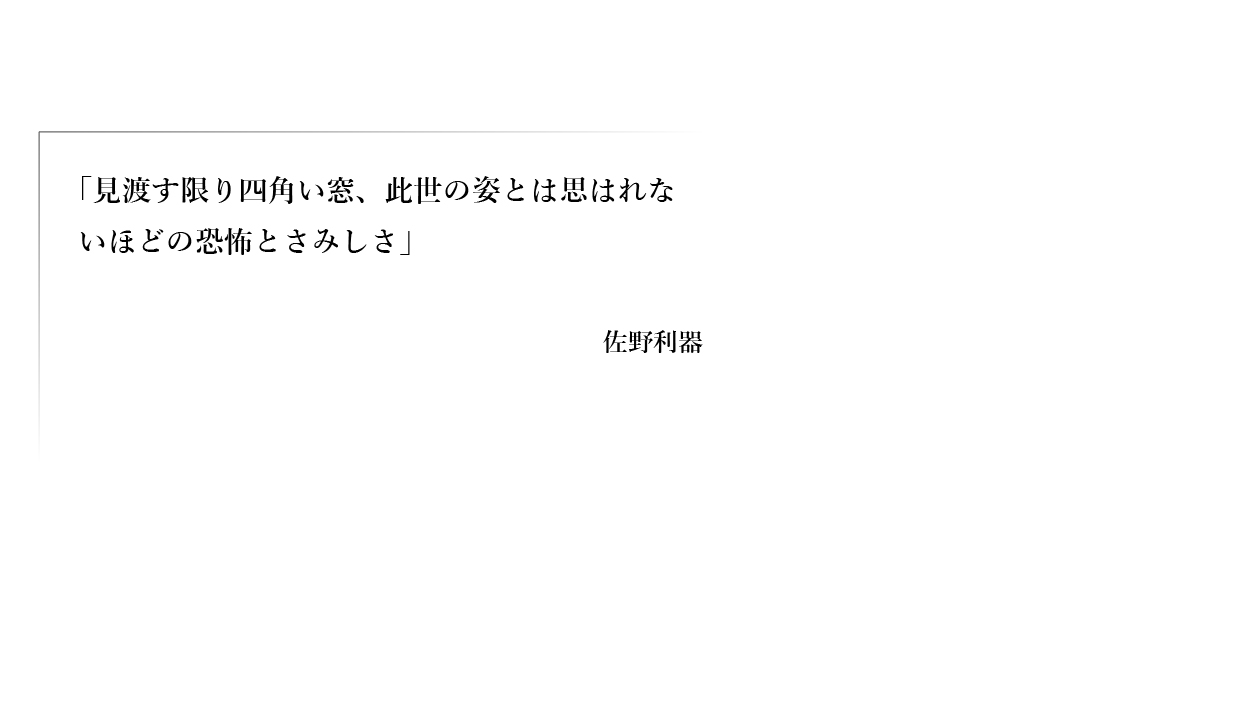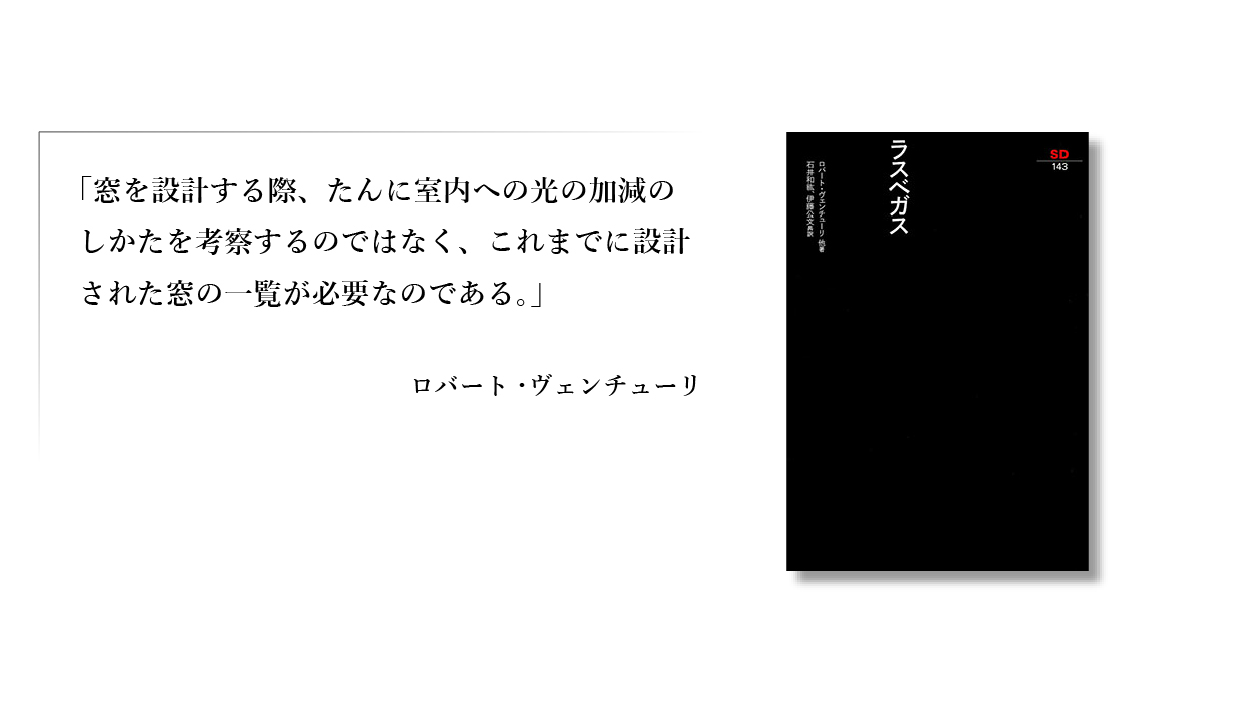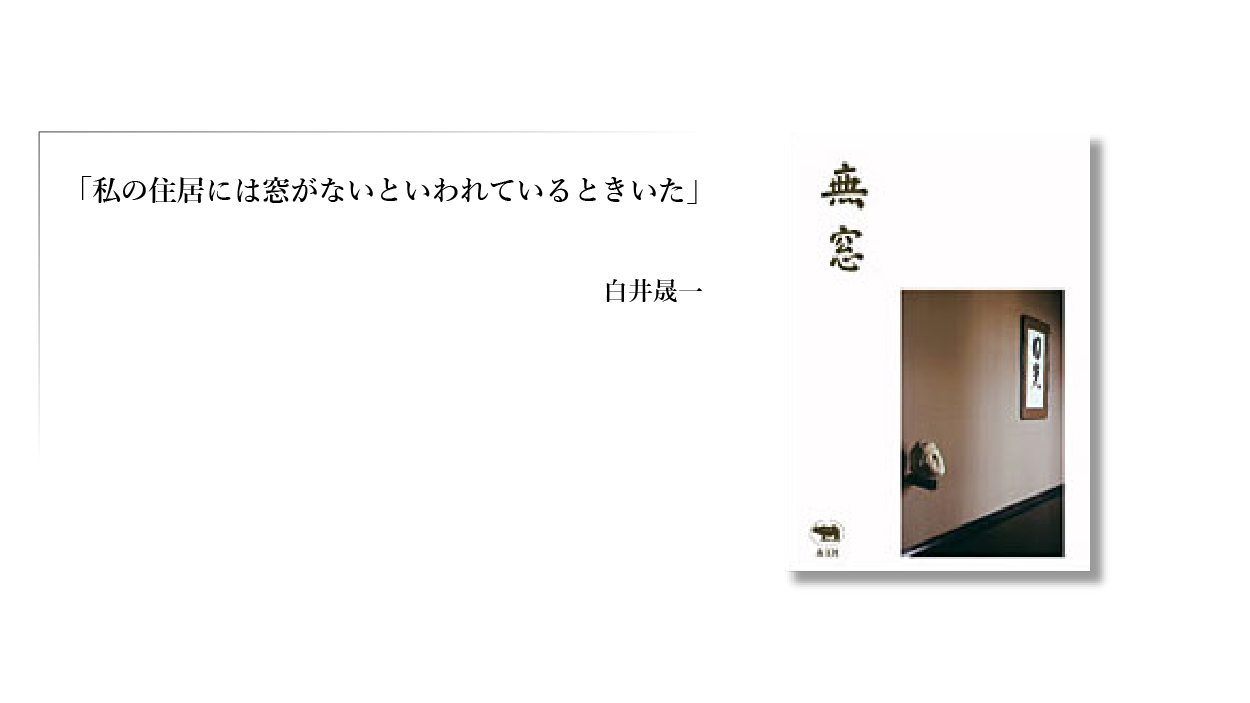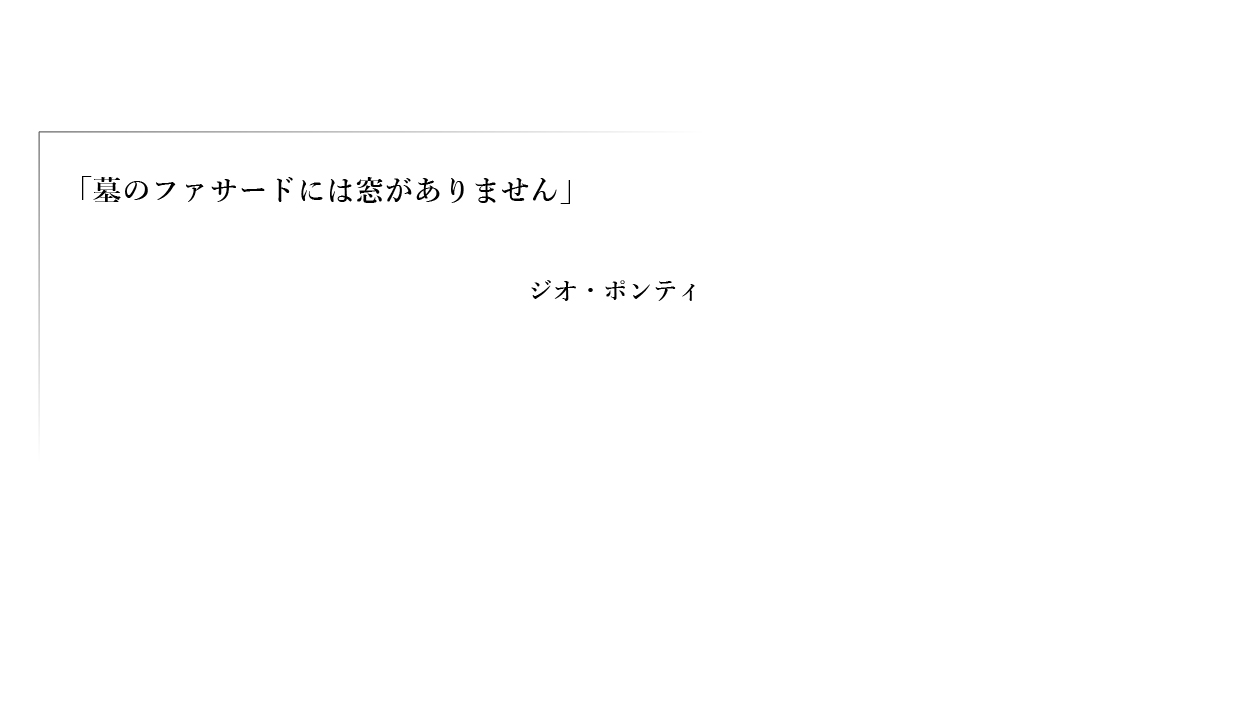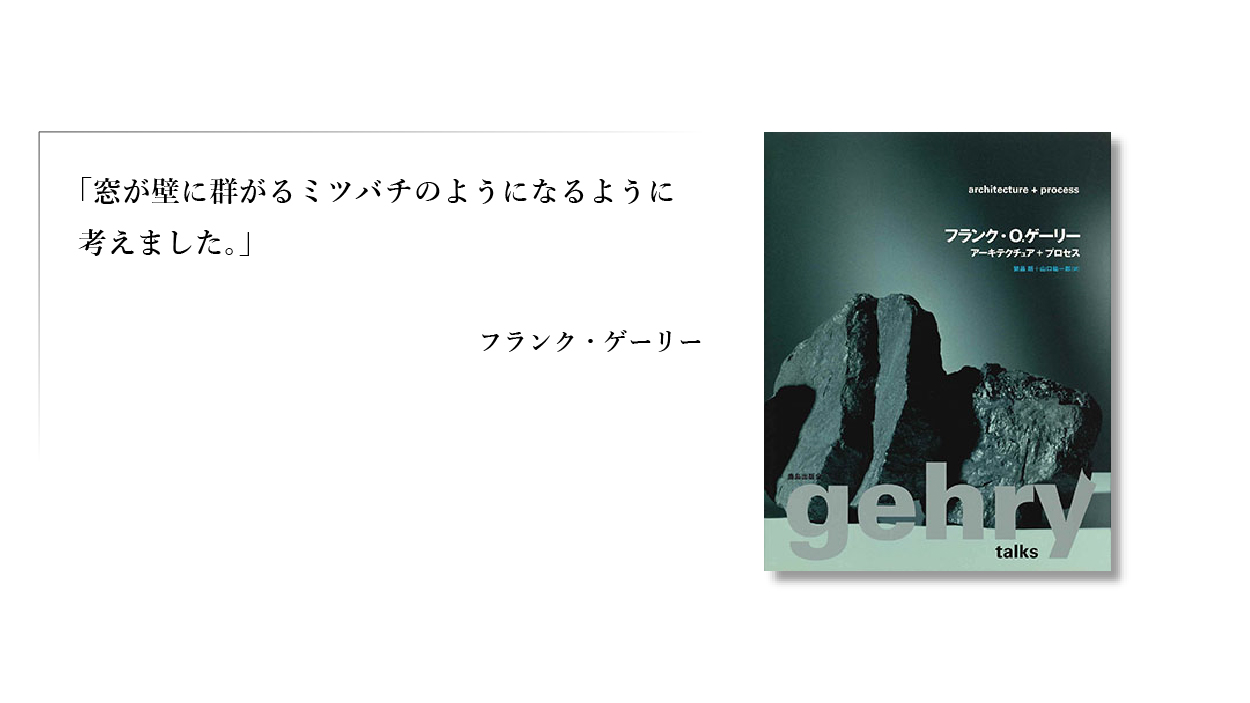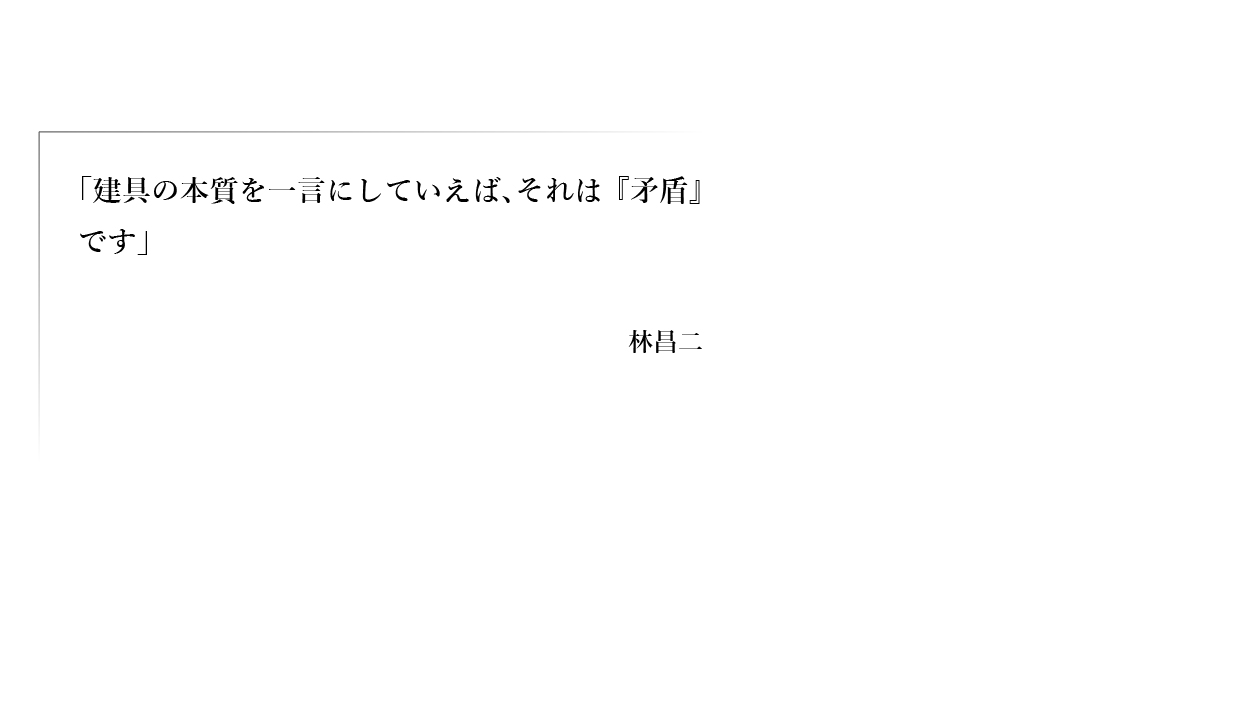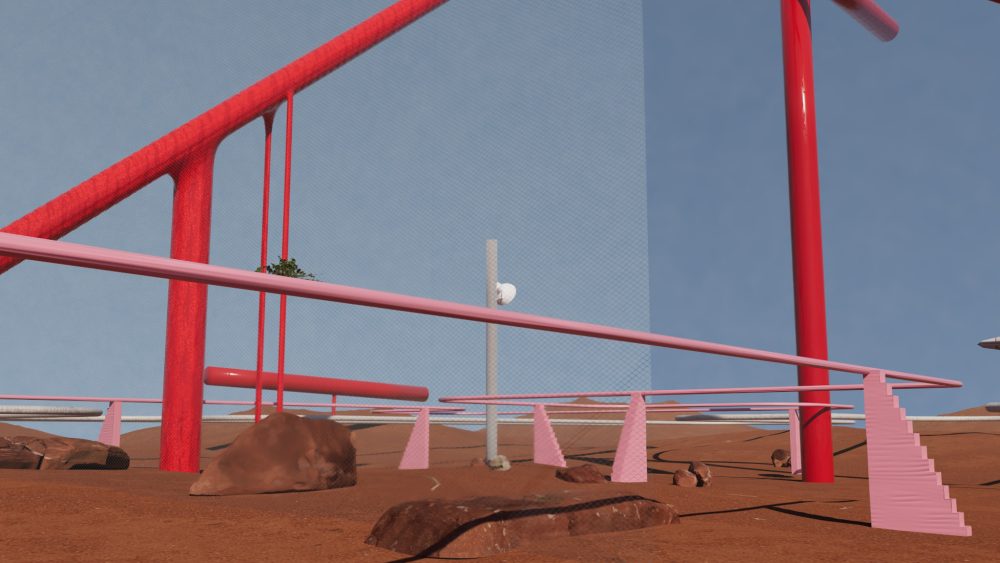窓の格言学
31 Mar 2025
窓研究所は2007年より国内外の大学・研究者と協働し「窓」について多面的に研究する活動「窓学」に取り組んでいます。
「窓の格言学」とは、2012年の「窓学」において、東北大学五十嵐太郎研究室が建築の言説をテーマに、近世以降の西洋と日本の建築家(歴史家、批評家を含む)が書籍や論文において、どのように窓について語ってきたかを調査しまとめたものです。
本記事は窓学研究報告会における五十嵐太郎先生の発表内容を抜粋・編集したものです。
窓の格言とは
格言(アフォリズム)は、非常に短いコンパクトな言葉の中で、叡智や考え方を凝縮したものと言うことができます。近代建築の教科書をめくってみても、例えば、ル・コルビュジエの「住宅は住むための機械である」というような一種のキャッチフレーズや標語に、その時代や建築家の思想があらわれていると言うことができます。
歴史的にも、窓について語った言葉を取り上げたものはなかったので、そういう意味で建築家や建築史家、あるいは思想家、批評家が、窓について語っているものを抽出しています。
事例紹介
いくつか簡単に事例紹介をします。例えば、ル・コルビュジエは「建築、それは採光された床である」と言っています。この言葉は窓について触れてはいないのですが、近代において大きく開口部をとるようになったことで、床に光が届くということを表現しています。やはり彼なりに、印象的な言葉を使いながら、近代建築のやり方を紹介しているわけです。
ジオ・ポンティは、「私たちは建築をつくっているのではなく、ガラスでモンドリアン・スタイルをやっているのです」と言っていますが、これは建築のファサードが面一になって、そこでどのような操作が可能かというようなことを述べています。
ルイス・カーンは、「暗くしようと意図された空間でさえ、それがどのように暗いかをわれわれに感じさせるいくつかの神秘的な開口部から洩れる明るさをもっているはずだ」と言っていて、どんなに暗い空間の中でも、その暗さを逆に感じさせる、ささやかな光をもたらす開口部があるという、趣のある言葉を述べています。
村野藤吾の「見ろ!デパートの窓という窓を。その誘惑を。それを眺める人の目を。その醜悪な顔を」という言葉は、皮肉っぽいですが、資本主義との関係で、デパートの窓が人々を誘惑していることを述べています。
「窓辺を提示すること。荒れ狂う世界に対して、建築ができることは、これしかない」は、2001年の同時多発テロ事件が起きた後に、内藤廣がある種の決意表明として述べたことです。そのような事件の後に、建築家ができるのは、日常性をもった窓辺をつくり、提示していくことだけだと。社会の中において窓がどういうものかを、大きな社会的事件に関連付けて話しているケースです。
アフォリズムが伝えること
このような窓のアフォリズムは、その時代の当事者の証言、あるいは詩的なドキュメントになると思います。
20世紀以前は、窓のつくり方自体が制限されている中で、どのようなことを建築家が語っているのかを見ていく必要があります。20世紀前半の近代建築、モダニズムの時代は、大きな窓ができるようになったことや透明なガラスの開口を大きくとれるようになったことについて、建築家はそれぞれの言葉で触れています。20世紀後半になると、それに対して異なるさまざまな考え方が出てきます。時代の証言については大体その3つに分けられます。
格言から伝わることは、時代の証言以外には、その建築家の独特な考え方や個性、デザインの方法などです。また、文章の表現としては詩的なイマジネーションを喚起するもの、キャッチフレーズとして鋭い響きをもったもの、などが挙げられます。
20世紀以前については、歴史書の中からルネサンスの建築論などを拾って、基本的な窓の性能の話をしているものを挙げていきました。例えば、ニコラス・ペヴスナーという建築史家が、「窓の設け方は、実質上決まり切っていた」と言っています。昔、窓税があったり、壁構造のために、窓のつくり方自体が制限されて、そういうシステムが成立していました。それが、近代においては徹底的に窓のつくり方が変わって、違うフェーズに突入していきました。
20世紀前半は、基本的に窓が大きくなり、ル・コルビュジエの水平連続窓など、さまざまな建築家が窓について語っています。日本において建築活動を行なっていたアントニン・レーモンドの場合は「窓が大きさを増すのは文明の拡大を暗示するということである」と言っています。文明論として、窓について語っているわけです。また一方で、日本の建築の特性を改めて再定義する動きも出てきます。
そのなかで、ルイス・カーンは面白い表現をしています。「壁はそのアーチと注意深くつくられた開口部の抱きを喜びました」。建築自体が主人公になったような、壁の気持ちで喋っています。第三者として窓を語るのではなく、主語が建物になっているような語りで、壁と開口部の話をユニークに表現しています。20世紀前半の、近代建築の中でも反復して窓をつくっていく時代で、ルイス・カーンはそれをうまく説明しています。一方、佐野利器は「見渡す限り四角い窓、此世の姿とは思はれないほどの恐怖とさみしさ」と言いました。この2つは相反する表現です。
それに対して、20世紀の後半は窓に多様性が出てきます。ロバート・ヴェンチューリは、「光の加減のしかたを考察するのではなく、これまでに設計された窓の一覧が必要なのである」ということを言っています。また日本建築の特性については、いろいろな建築家がさらに再定義して語っています。
少し特殊ですが、窓がない建築について、白井晟一は「私の住居には窓がないといわれているときいた」と言い、ジオ・ポンティは「墓のファサードには窓がありません」と述べています。
窓を通して地域性や場所性が表示されているというようなことを述べているものも出てきました。調べていくなかでも、クリストファー・アレグザンダーは、窓に関する言葉を多くつくっていて、他と比較してかなり多くのサンプルが集まった建築家でした。
フランク・ゲーリーは、「窓が壁に群がるミツバチのようになるように考えました」と言いましたが、そのように窓を考えているというのは、すごく詩的な表現だと思います。
そういう意味で窓というのは多義的で、特に20世紀後半で見ていくと、同じ事象について、それを両方の見方をしていくというようなことがあります。林昌二は、「建具の本質を一言にしていえば、それは『矛盾』です」と言いました。例えば、窓には開く、閉じるという相反する機能や要求があって、それを「矛盾」という言葉で説明しているわけです。
研究方法
対象は近世以降の西洋と日本の建築家として、主な著作を調べて、窓・開口・採光・孔・穴といった言葉が入っている言説を取り出していきました。
西洋の建築家154名、日本の建築家177名、計331名の建築家をピックアップしています。そのうち著作のある、あるいはその言説が読み取れる本があるのは、西洋で101名、日本で121名、計222名の建築家でした。そのうち西洋67名、日本70名、計137名の著作について、窓の言説があるかどうかを確認しました。このうち窓に関する言説は、西洋53名、日本64名、計117名の著作において確認されました。
こういったかたちで資料を選定して、サンプル格言数は299となりました。以上を精査して、最終的には西洋と日本がおよそ半々で計120の格言を資料として用意しました。