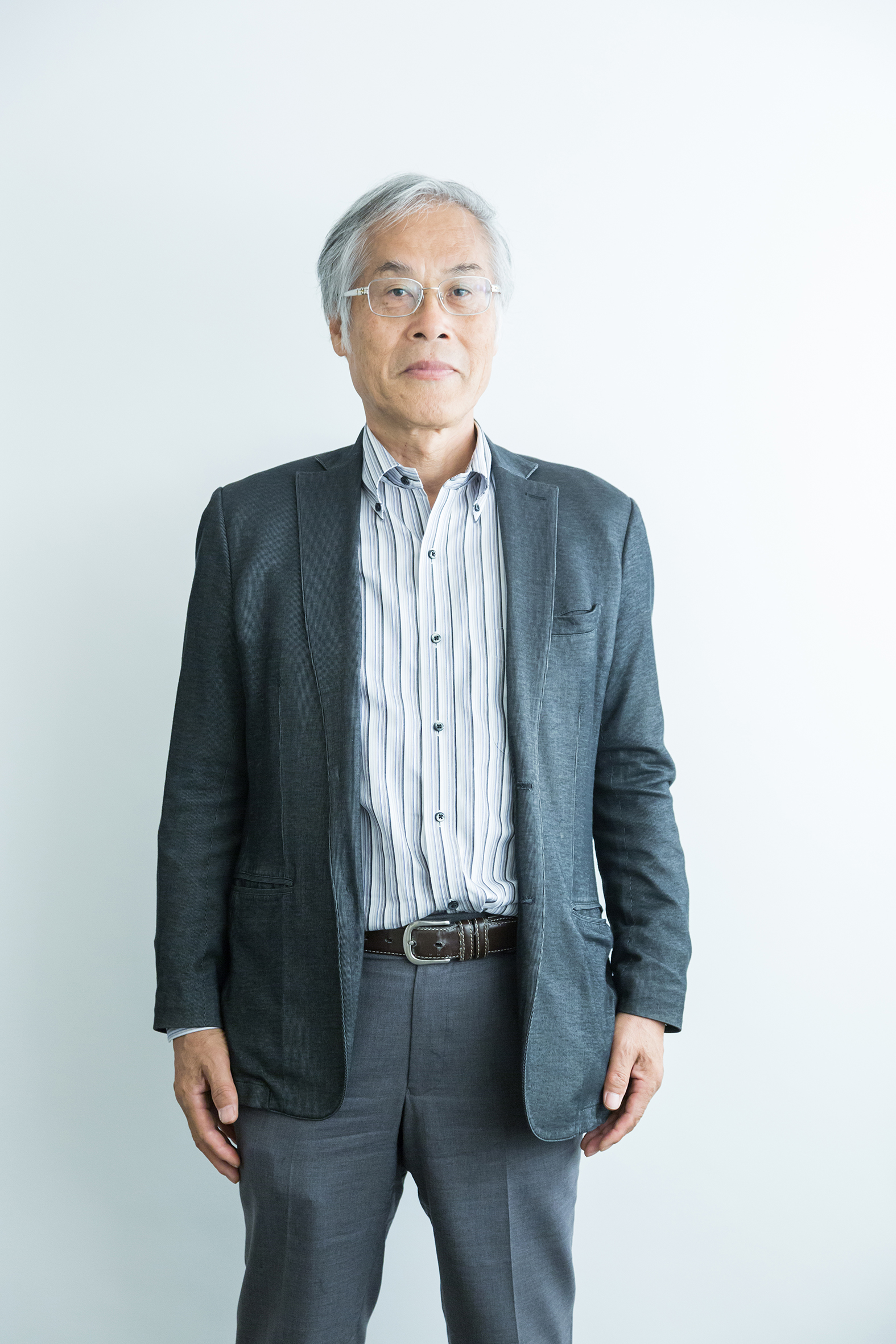藤森照信「穴」
15 Jun 2021
《空飛ぶ泥舟》や《草屋根》、《多治見市モザイクタイルミュージアム》をはじめ、木や土、植物など自然を生かした独創的な建築を手掛けてきた藤森照信氏。本レクチャーでは、歴史家である氏が窓の原初としての「穴」を考察し、自身の空間設計における窓に込めた創作意図を語る。
*本記事は2017年の窓学国際会議での講演内容をもとに再構成したものです。
「窓」というものについてはじめてショックを受けたのは大学院の入試で、内田祥哉先生が「窓を論ぜよ」という問題を出されたときです。それまで大学の先生方は、プラン、構造、外観の表現、それから都市との関係といったことを論じていましたし、私も考えてきました。ところが突然「窓を論ぜよ」といわれて、まったくどうしていいか分からなかった。それまで窓については、なんとなく穴が開いている、というイメージしかなかったのですが、以来ずっと窓に興味をもっております。
次に刺激を受けたのは、原広司先生でした。原先生は内田先生のところで学び、窓や、いわゆるビルディング・エレメント、構法といったものへの発想をもっておられた。内田先生とは違い、原先生は窓や開口部の問題を「有孔体理論」というかたちで論じられました。学生のころに皆で先生の本を読んだのですが、ものすごく難しくて、理解するのが大変でした。
だいぶ後になって原先生と親しくなってから、あれは簡単にいえばどういうことなんですかと聞いたら、それは簡単で、空間はもともと真っ暗な死んだものとしてある。そこに窓が開いて光が差すことで、はじめて空間が動きはじめる。だから建築は、いってみれば暗い中に穴が開くことで誕生するもので、それが有孔体理論である、と。
これが原先生が有孔体理論をまず最初に実現した《伊藤邸》(図版1、2)です。さすがに入り口はありますが、開口部はほとんどありません。寝室には窓がありますが、少し奥に行かないと分からない。真っ昼間でも当然のように中は暗くて、そこにこうした窓がついている。完全な洞窟の中に光が差した状態から空間が動きはじめる、出現するという有孔体理論を実践したものです。
-

図版1 原広司《伊藤邸》(1967)
-

図版2 原広司《伊藤邸》(1967)
ただ原先生に少し言いたいのは、完全に閉じた真っ暗闇の中は、死んだ空間ではないということです。ラスコーの壁画が有名ですけども、実は人類の最初の表現行為として知られているのは、地下に絵を描くことだったわけです。ラスコーの壁画はたまたま何かの事情で洞窟にあいた穴に犬が落ちて、その犬を子どもたちが探しに入ったことで発見されたそうです。入り口から一切光が入らない地下の空間に絵が描かれている。
ラスコーは今は閉じられているので、別の洞窟を見ました(図版3)。入り口からトロッコに乗って洞窟に入っていくと、まず入り口のあたりに人類の住んだ跡があります。もう少し奥に行くと、クマの冬眠の跡がある。そしてさらに15分くらい進んだところ──恐らく地下1キロメートル近いと思いますが──もう一切何もないところに、マンモスの絵が大量に描いてあります。
-

図版3 洞窟画のある洞窟から入り口を見る。この洞窟の地底奥深くにマンモスの絵が大量に画かれている
当時の人にとっては、洞窟というのは地上のものではない、別世界なんです。洞窟絵画は、そこで恐らく生命のよみがえりのようなことを考えてつくられました。人類が成した最初の空間的なことは、私はこれだと思います。要するに外界と完全に切れた中につくられた世界で、そこには一種の地母神、ギリシャ人はそれを「ガイア」と呼んだわけですが、そういったものの空間がある。そこで人類はともし火をつけて、獲物の絵を描いた。私にはそれが恐らく、インテリアの起源ではないかという気がします。
ですから、とても人が暮らすようなところじゃございません。一方、旧石器時代の人は、穴の中や崖のくぼみの中で暮らしておりました(図版4、5)。これはラスコー洞窟もある、フランスのペリゴールという人類文化の発祥の地といっていいような場所です。こうした洞窟は反対側が谷になっていて、当時の人が開放的な環境に住んでいたことが分かります。これは洞窟から入り口を見たところで、この辺りに住んでいたわけです。
-

図版4 ペリゴール地方(フランス)の人の住んだ洞窟
-

図版5 ラスコー近くのクロマニヨン人の洞窟の入り口。クロマニヨン家の裏の洞窟であることから、ここで発見された旧石器時代の人間をクロマニヨン人と呼ぶ。人類は住んでいたが、洞窟画が画かれているわけではない
この辺りから、窓についてのいろいろなことを考えはじめました。窓は光と空気の出入り口ですが、入り口、いわゆるエントランスは、人のためのものです。そのふたつを合わせて「開口部」という。この言い方は、ほとんど建築業界以外では意味不明ですね。開口部を一般的な言葉でいうと「穴」になるわけです。私としては、ぜひ「窓学」が進みました果てには、「穴学」をやっていただきたいと考えております。
さて、これまで見てきたのは洞窟の例ですが、世界中、洞窟があるところはそんなに多くない。では、洞窟がない場所の人々はどのようなところに住んでいたか。オーストラリアのアボリジニという原住民の住居はその良い例です。これはその原住民の人たちがつくった住宅(図版6、7)です。枝の細いものを取ってきて、こうやって組む。出入り口の穴が開いております。もうひとつ、ここには火があります。旧石器時代の人たちは洞窟の中で火を焚いていましたが、こうした洞窟のないところでは、それだと危険なので出入り口の前で焚いている。住宅の内から火を見つつ、外を見る。これは人類の「穴学」の最初を飾る写真だと思い、大変感動しました。
-

図版6 オイニと妻イアルモが建設中の雨季の樹皮の家の骨組み。1929年。インティンガ(Yintjinga)族。オーストラリア、クイーンズランド州北部、ケープ岬半島東部、スチュワート川
Photographer – D. F. Thomson. / The Donald Thomson Ethnohistory Collection. Reproduced courtesy of the Thomson family and Museums Victoria.
-

図版7 丁寧でしっかりした造りの完成した雨季の家。この形式の住宅は、オーストラリアのクイーンズランド州北部、ケープ岬半島沿岸部の部族が使用していた。施工者のオイニが囲いの中から出てくる方法を実演中。1929年。インティンガ(Yintjinga)族。オーストラリア、クイーンズランド州北部、ケープ岬半島東部、スチュワート川
Photographer – D. F. Thomson. / The Donald Thomson Ethnohistory Collection. Reproduced courtesy of the Thomson family and Museums Victoria.
こうして「穴」が窓の元であるということは、私に大変大きなショックを与えました。原先生は《伊藤邸》で昼間も暗い家をつくられたわけですが、私もやはり自分の理屈はちゃんと実践しなくちゃいけないという強い思いがございまして、建築を穴状につくっております。
これは《焼杉ハウス》(2007)という住宅で、穴をイメージしてつくりました(図版8)。焼杉は、東日本の人にはあまり馴染みがなく──最近は伝わってきましたが──西日本で開発されたものです。出所不明、来歴不明、いつできたのか、なぜ西日本にしかないのかも分かりません。東京では杉に墨を塗りますが、関西では焼くのです。
-

図版8 藤森照信+川上恵一《焼杉ハウス》(2007)
撮影 新建築社写真部
-

図版9 焼杉表面
ただ焼いてもしょうがないので、2センチの厚さのうち1センチを炭にしました。焦がした感じは嫌で、ちゃんと炭にしたかった。普通は2メートル単位でつくるのですが、私は8メートルまで焼いて使っています。最初は1対1の間隔で焼杉を並べていたのですが、葬式の幕と同じと気づいてやめて(笑)、少し間隔を縮めています。私は伝統の技法に興味があるのですが、そのまま使う気はさらにない。
これは洞窟なんです。洞窟の条件は、開口部がひとつであること。つまりぽかんと入り口が開いているということですね。それと床・壁・天井が同じ材料だということ。できることなら、天井に丸みがあるほうがいい。それともうひとつ、奥に火があることです。この洞窟の窓は「シカゴ窓」ふうに、真ん中はフィックスで左右が開くものにしています。
これが内部で、床・壁・天井に同じ材料を使っています(図版10)。材料は、床に1番高いもの、2番目に壁、天井には1番安いものを張ります。床・壁・天井を一体化する場合には、1番高い材料を全てに使わないといけませんので、なかなか大変です。
-

図版10 主室から外を見る
撮影 新建築社写真部
これは滋賀県近江八幡の住宅です(図版11)。これも「洞窟」で、主室をつくっています。どーんと窓を開けていますが、もちろん全体は木造です。開口部は一切見えません。
ここでは洞窟だからということで、初めて土を塗りました。塗る前はものすごく不安でしたが、塗ってみてびっくりしました。うっとうしいとか、良いとか悪いといった印象が全てなくなるんです。それだけではなくて、土を触っていると皆没頭してしまう。
-

図版11 藤森照信+中谷弘志《ROOF HOUSE》(2009)
撮影 新建築社写真部
-

図版12 仕上げに土が用いられた内部空間
撮影 新建築社写真部
もし土が印象を残すようなものだったら、人類は大変だったろうと思います。歩くたびに印象があるわけですから。土は人類にとっては不可欠なものだけれども、目や意識に働きかけないという意味で一種の建材における空気みたいなものだと思っております。そういう点では興味深い材料です。施主も「あ、土塗ってあるな、これ」で、もう全然、忘れてしまう。
これは岐阜県多治見市にあるタイルのミュージアムです(図版13)。多治見市では、建築家でない人たちが銭湯などをつくるときに使うようなモザイクタイルが大量につくられてきました。これはそうしたタイルを展示する博物館です。やはり窓は小さくして、穴を印象深くしたかたちにしています。
-

図版13 藤森照信+エイ・ケイ+エース設計共同体《多治見市モザイクタイルミュージアム》(2016)
撮影 新建築社写真部
私は「穴」が開口部の原型であることに興味があり、洞窟や色々なものを見てまわってきましたが、そのとき面白かったもののひとつにローマのパンテオンがありました。パンテオンは直径およそ40メートルの球体で、ドームのてっぺんに9メートルの開口部があります。
天井から光を入れるのですが、開口部には何もはまっていません。だから雨も一緒に入ってくる。窓の原型としての「穴」のもっている思い切りの良さというか、パッと気持ちを開く感じ。あれを一度やりたいと思っていたのですが、このミュージアムで実現することができました。
-

図版14 展示室内部。空に向けて「穴」が開けられている
撮影 新建築社写真部
こうしてポンと穴を開けました(図版14)。幸いにもタイルのミュージアムですから、雨風が入っても全然問題がない。でもなんだかさみしいものだから、そこにタイルで簾のようなものをつくりました。今ではタイルの施工にモルタルは使わないんですね。ここではワイヤにモザイクタイルをボンドでつけています。
これで一応、穴居、穴としての住宅の考えを美術館を使って実現し、空に向かって穴が開いているさわやかさも実現することができました。
私としてはこうして、おおげさな言い方になりますが、人類が誕生した、空間を体験しはじめたそのときまで戻って、開口部や窓を考えたいと思いやってまいりました。少し早いですが、これで私の話を終わりたいと思います。
藤森照信/Terunobu Fujimori
1946年、長野県生まれ。東京大学大学院博士課程修了。東京大学生産技術研究所教授、工学院大学教授を経て、現在は、東京大学名誉教授、工学院大学特任教授、江戸東京博物館館長。45歳より設計を始め今に至る。近著に『磯崎新と藤森照信の茶席建築談義』(六耀社)、『近代日本の洋風建築 開化篇・栄華篇』(筑摩書房)等、建築史・建築探偵・建築設計活動関係の著書多数。近作に《草屋根》《銅屋根》(近江八幡市、たねや総合販売場・本社屋)等、史料館・美術館・住宅・茶室など建築作品多数。