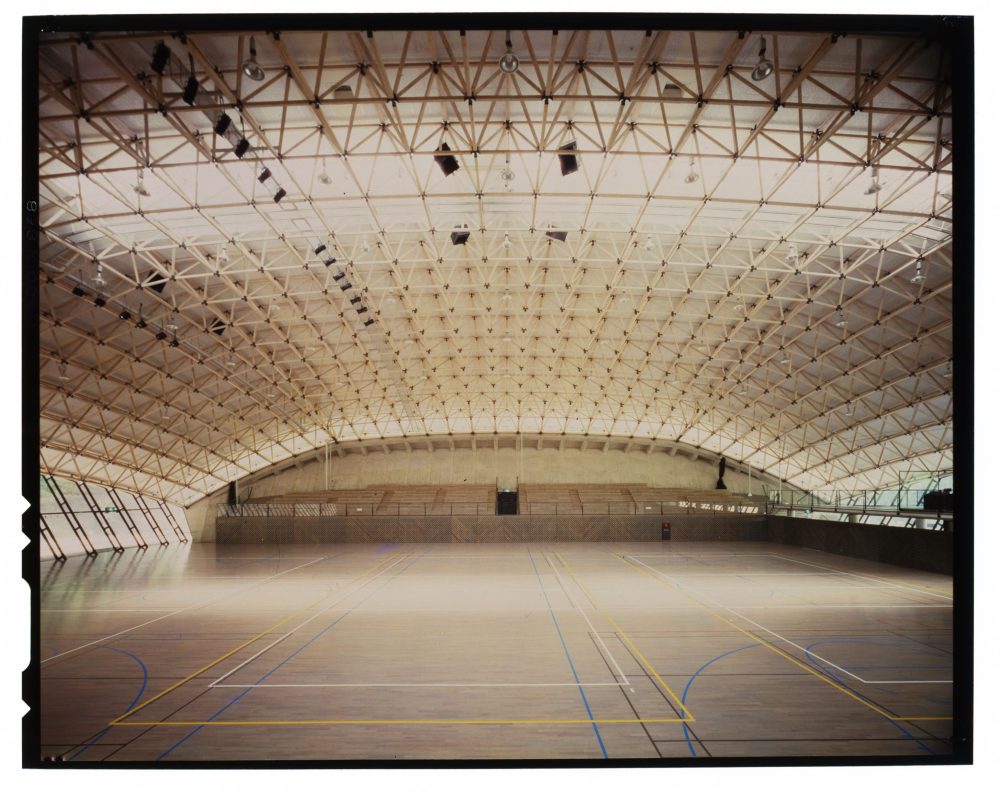Grant Results 2024年度 採択テーマ CCA-WRI Research Fellowship
Salt and Land: Shifting Territories of the Salt Production Sites in the Seto Inland Sea
塩と土地――瀬戸内海の製塩地帯における土地利用の変遷
31 Mar 2025
- Keywords
- Architecture
- CCA-WRI
- History
公益財団法人 窓研究所は、カナダ建築センター(Canadian Centre for Architecture)と共同でフェローシップ・プログラム「CCA-WRI Research Fellowship」を実施しています。本記事は、2024年度リサーチフェローのひとりである中本陽介氏の研究テーマを紹介するものです。
研究テーマ概要
本研究は、日本の瀬戸内海地域における製塩業の近代化過程と、それによって生じた「物質代謝の亀裂(metabolic rift)」に着目するものである。この概念はマルクスによる資本主義的農業批判に由来し、自然の循環過程と人間の生産活動との間に生じる断絶を指す。製塩業においては、沿岸地域のコミュニティと土地との関係が徐々に希薄になる形でこの亀裂が表れている。
本研究では、1950年代から1970年代にかけての製塩手法の変化を主な対象とし、伝統的な入浜式塩田から、電気透析を利用したイオン交換膜式製塩などの機械化技術への移行を辿る。
伝統的な製塩は、沿岸部に広がる塩田と、沿岸・内陸間の交易によって支えられていた。人間の労働と自然のリズムが結びついたこの技術体系は、海洋文化の一部を成していた。しかし、20世紀中頃の技術革新により、これらの伝統的な手法は、より効率的かつ大量生産を可能とする工業的プロセスに置き換えられていった。イオン交換膜の導入により塩の大量生産が可能となり、それに伴い、かつての塩田は次第に工業用地へと転用されていった。
本研究は、瀬戸内地域における塩田の埋立・開拓、および沿岸部における土地利用の変化を調査対象とする。物理的な塩田の消失と工業化の進行は、沿岸の風景を大きく変化させ、土地とそこに暮らす人々の関係に断絶をもたらした。このような変化は、物質代謝の亀裂として位置づけることができる。
こうした変化の背景には、政府による製塩事業の独占や技術革新があり、日本の製塩業は工業化と国際化へと進んだ。かつて海洋文化の一翼を担っていた製塩は、その文化的ルーツから切り離されていく。
本研究は、大地と海の間にある断絶を再びつなぎ直すことを目指し、海を中心とした視点から、沿岸を文化的アーカイブの場として捉える。列島という日本の独特な地形、そして国家主導の近代化の進行は、深い分断を生み出すと同時に、周縁における適応と変容を促してきた。製塩という営みを軸に据えることで、日本の環境史・経済史における「農業中心」の語りを相対化し、沿岸史の再評価を提起するものである。
『Energy Always: 2024 CCA-WRI Research Symposium』(2024年8月7日、モントリオール)記録映像より
中本陽介/Yosuke Nakamoto
東京生まれ。チューリッヒを拠点に活動する建築家・研究者。チューリッヒ工科大学(ETH Zürich)建築学部にて、アダム・カルーソのスタジオで建築設計教育に携わるとともに、同大学建築史・理論研究所(gta)におけるMASプログラムで研究に従事している。
これまでに、ウィーン工科大学、メンドリシオ建築アカデミー、チューリッヒ工科大学で建築を学び、アドルフ・クリシャニッツ(ウィーン)、EMIアーキテクテン(チューリッヒ)、シュタウファー&ハスラー・アーキテクテン(フラウエンフェルト)などの建築事務所で実務経験を積む。2024年夏には、モントリオールのカナダ建築センター(CCA)にてリサーチフェローを務めた。
現代社会における民俗的な痕跡や、価値観の変化が風景に及ぼす影響に関心を寄せ、異文化間の思考と知の交換を軸に研究を展開。近年は、デルフト工科大学でのSUDHT、メンドリシオでのDrawing the Urban、アテネで開催されたEAHNなど、国際会議にも参加している。